図1 体重および摂餌量
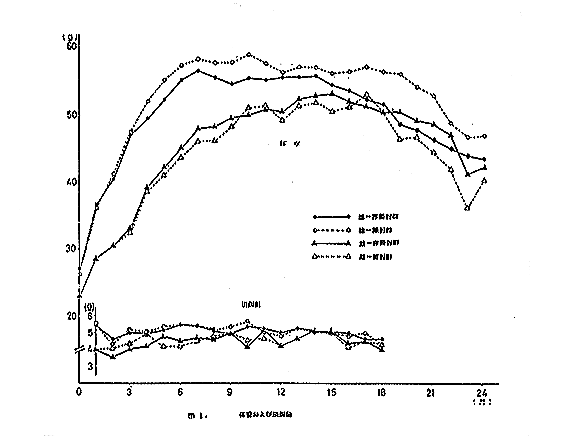 |
γ線照射かまぼこの安全性を調べる目的でマウスによる慢性毒性試験を行なった。
科学技術庁食品照射研究運営会議指定のかまぼこ(紀文製)を用い、日本原子力研究所高崎研究所においてγ線照射(450krad)を行ない、これを薄片状に切断して凍結乾燥した。凍結乾燥物としての歩止りは23%である。この凍結乾燥したかまぼこを粉砕し、オリエンタル製飼育用飼料(MF)に2.0w/w%の割合で混合し、成型して検体添加飼料とした。
静岡県実験動物農業協同組合産のddY系マウスを生後4週令にて購入、1週間当試験所動物舎(温度23±1℃、湿度55±5%)で馴化飼育観察後、健康と認めた雄および雌、各々100匹を選定し、これを雄雌とも各50匹よりなる2群に分け、非照射群および照射群とした。なお、非照射群には無処置かまぼこ2%添加飼料を、照射群には照射かまぼこ2%添加飼料を各々全期間水とともに自由に摂取させた。
一般症状、体重、摂餌量、死亡率(Life Table Techniqueにより求めた)および腫瘍発現状況ならびにその発生率について検討した。なお、摂餌量については、18ヶ月目以降食いこぼしによる変動が大きくなったので測定を中止した。
さらに、24ヶ月間生存していた動物については屠殺後肉眼的検査を行ない、また、途中死亡動物については肉眼的検査を行ない、それぞれ病理組織学的検査に供した。
両群の雄および雌ともに特記すべき症状の発現を認めない。
体重曲線および摂餌量を図1に示す。
体重について、雄では3ヶ月目頃まで群間に著しい差はみられないが、その後、照射群は非照射群に比べて常に増加の傾向を示し、特に9、10、17、18および19ヶ月目では推計学的に有意の差を生ずる。
雌では、18ヶ月目まで群間にほとんど差はみられないが、それ以降、照射群は非照射群に比べて減少の傾向を示す。しかし、実験全期間を通して群間に有意の差は認められない。
摂餌量は、雄および雌とも群間にほとんど差は見られない。
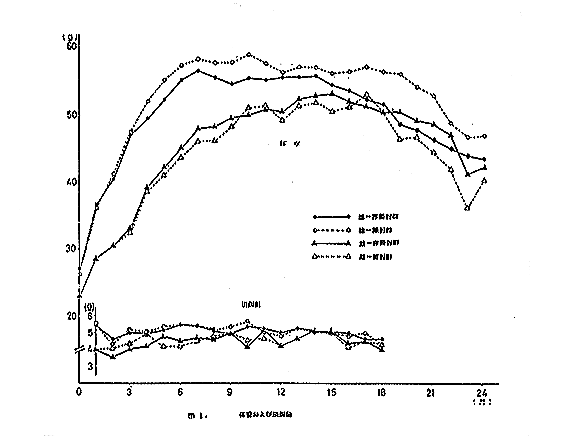 |
表1に示すように雄および雌とも群間に差は認められない。
検査の対象となった動物数は、事故により死亡した動物および死後自己融解が著明なため所見が取れなかった動物を除く全ての動物で、雄では、非照射群49例、照射群48例、また雌では、非照射群48例および照射群49例である。
主な変化を表2に示す。雄および雌各群とも肺の腫瘤が多く見られる。その他、雄では、非照射群および照射群ともに肝臓の腫瘤、脾臓およびリンパ節の肥大が認められる。雌では、非照射群および照射群ともに脾臓およびリンパ節の肥大が認められる。また、非照射群で肝臓、卵巣および乳腺の腫瘤が僅かに多く認められる。
総括を表3および表4に示す。
雄雌とも肺の腺腫が多く認められる。しかし、雄雌とも非照射群と照射群との間に差を見ない。また、その他の臓器にも数例の腫瘍を認めるが、雄雌とも群間に一定の傾向の差は認められない。
図2および図3に示すように雄では、非照射群および照射群とも12ヶ月目より、雌では、非照射群で10ヶ月目より、照射群で11ヶ月目より腫瘍の発現を見る。
腫瘍発生率は、雄では、非照射群で実験期間中に死亡した46例中26例および屠殺した3例中2例の計28例(57%)、照射群で実験期間中に死亡した44例中27例および屠殺した4例中2例の計29例(60%)である。雌では、非照射群で実験期間中に死亡した44例中33例および屠殺した4例中4例の計37例(77%)に、照射群で実験期間中に死亡した48例中32例および屠殺した1例の計33例(67%)である。
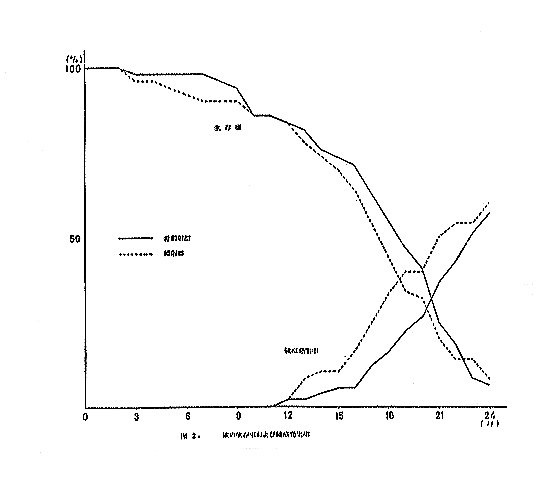 |
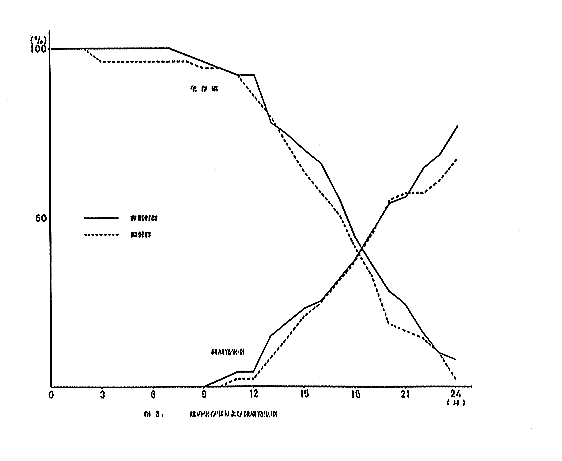 |
γ線照射かまぼこの安全性を調べる目的で450krad照射かまぼこ2w/w%添加飼料を用いてマウスによる24ヶ月間の慢性毒性試験を行なった。
途中死亡動物および24ヶ月間生存した動物の病理学的検査では、肉眼的所見において雄雌各群とも肺の腫瘤が最も多く見られ、組織学的に、これらは腺腫と腺癌であった。その他の多くの臓器にも腫瘍の発現を見るが散発的であり、肺の腺腫および腺癌同様雄雌とも群間に一定の傾向の差を認めない。また腫瘍発現時期および例数とも群間に明らかな差は認められない。
γ線照射かまぼこの安全性を調べる目的で、ラットによる24ヶ月間の慢性毒性試験を行った。
科学技術庁食品照射研究運営会議指定の紀文製かまぼこを必要に応じて作製し、これを二分して、一方を非照射かまぼことし、他方を日本原子力研究所高崎研究所において450kradのγ線照射を行い照射かまぼことし、これらを薄片状に切断し凍結乾燥した。この時の歩止まりは23%であった。この乾燥かまぼこを粉砕し、ラット用粉末飼料(オリエンタル酵母製MF)に非照射及び照射かまぼこ共に2w/w%及び7.5w/w%の割合で混合し、円柱型ペレットに成型して検体飼料とした。これらの飼料を24ヶ月間に亘り自由に動物に与えた。 なお、対照群としてかまぼこを含まないラット用固型飼料(オリエンタル酵母製MF)を自由に与える群を置いた。
静岡県実験動物農業協同組合産の生後4週令の雄雌のウィスター系ラットを購入後、1週間馴化飼育し、5週令時に健康と思われるラットを、雄雌各々1群30匹からなる5群に分け、対照群、非照射群(2%:N−2,7.5%:N−7.5)及び照射群(2%:R−2、7.5%:R−7.5)とした。
なお、動物は当所ラット飼育室(温度:25±1℃、湿度:55±5%、照明:12時間明、12時間暗、100%新鮮空気調和)にて各々個別ケージで飼育し、飲水は自動給水装置により水道水を自由に摂取させた。
一般症状及び死亡の有無については毎日観察し、体重及び摂餌量は実験開始後3ヶ月目までは週1回、12ヶ月目までは隔週、18ヶ月目までは3週に1回、それ以降24ヶ月目まで月1回の割合で測定した。
実験開始後6、12及び18ヶ月目に各群雄雌共に5匹、24ヶ月目に生存する全動物について、尾静脈より採血し血液形態学的検査を、また後腹大動脈より採血し分離した血清を用いて血清生化学的検査を行い、更に病理組織学的検査を実施した。
飼育期間中の自然死動物は発見後可及的速やかに解剖し、肉眼所見を記録した後、組織学的検査に供した。
なお、死亡率の計算はlife−table techniqueを用いて行なった。
また、上記の各時期に行った血液形態学的及び血清生化学的検査と病理学的検査の内容は、次の通りである。
血液形態学的検査
赤血球数及び白血球数(Red cell,White cell)
:トーアミクロセルカウンター
総ヘモグロビン量(Hb):シアンメトヘモグロビン法
ヘマトクリット値(Ht):毛細管遠心法
白血球像:塗抹標本
血清生化学的検査
総蛋白量(Protein):ビュレット法
アルブミン(Albumin):HABCA色素結合法
血糖値(Glucose):グルコースオキシダーゼ法
尿素窒素(Urea−N):飴野・亀岡のジアセチルモノ
オキシム直接比色法
アルカリ性ホスファターゼ(ALP):Kind and
King法
トランスアミナーゼ(GOT,GPT):Reitman−
Frankel法
コレステロール(T−Chol.,F−Chol.):
デタミナー酵素法
遊離脂肪酸(NEFA):パソコプロイン比色法
トリグリセライド(Trigly.):Fleteherの変法
無機リン(S−Pi):Lowy OH and Lopeg
JA法
カルシウム(S−Ca):原子吸光法
マグネシウム(S−Mg):同上
ナトリウム(S−Na):同上
カリウム(S−K):同上
臓器重量の測定:脳、心臓、肺、肝臓、腎臓、脾臓、精巣、
卵巣、下垂体、甲状腺及び副腎
病理学的検査
肉眼的検査:体表面の形状及び臓器・組織の肉眼的検査
組織学的検査:上記の諸臓器のほかに胃、小腸、膵臓、骨髄
及び腸間膜リンパ節の光学顕微鏡による検査
実験結果の統計的有意性は、Student’s t−testにより対照群と非照射群及び照射群あるいは同一添加量の非照射群と照射群の群間で検討した。
24ヶ月までの飼育全期間を通じて、雄雌各群共に特記すべき症状の発現を見ない。
雄では非照射群及び照射群が対照群に比べ実験開始後70週目頃までやや上廻る増加を示し、70週目以降でR−7.5群がやや減少の傾向を示すが、有意の差を見ない。雌では飼育全期間を通じて各群共に殆ど差を見ない。
摂餌量は雄雌共に各群殆ど差を見ない。
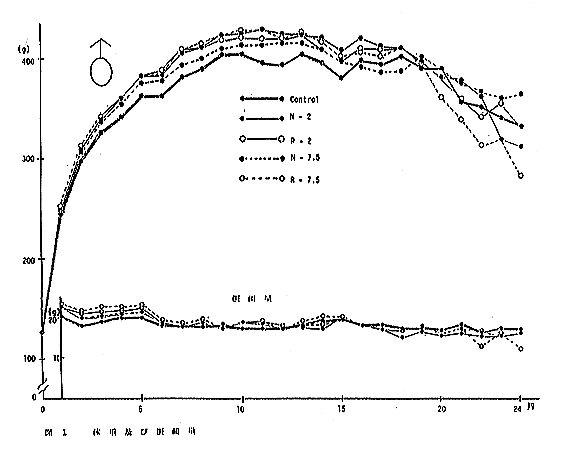 |
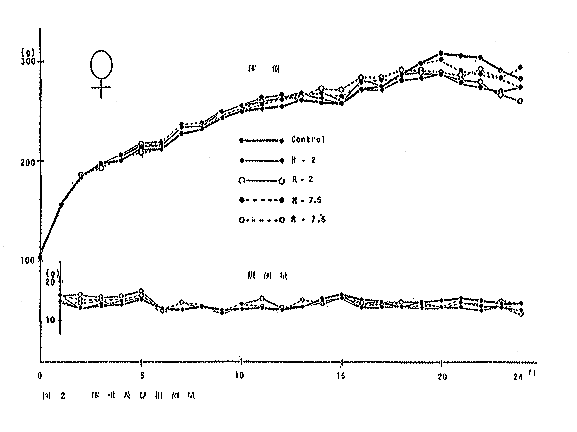 |
雄雌共に実験開始後9ヶ月目より散発的に死亡が見られるが、18ヶ月目より死亡数の増加を示し、雌より雄にやや死亡数が多く認められる。雄では、N−7.5群及びR−7.5群が対照群に比べやや高値を示すが有意の差を認めない。
雌では各群間に殆ど差が見られない。
6ヶ月目(表2):雄では、N−2群でHb及びHt値が対照群に比べいずれも有意の減少を示し、R−2群で同じHb及びHt値がN−2群に比べ有意の増加を示すが、R−7.5とN−7.5群の群間にはいずれの項目にも明らかな差を認めない。雌では各群間に明らかな差は認めない。
12ヶ月目(表3):雄では各群間に殆ど差を見ないが、雌ではN−2群でRed cellが、またR−2群でRed cell及びWhite cellが、いずれも対照群に比べ有意の増加を示すが、R−2群とN−2群の群間には殆ど差を見ない。
18ヶ月目(表4):雄ではR−2群でRed cellが対照群に比べ有意の減少を示すが、N−2群の群間には差を見ない。雌ではいずれの項目にも明らかな差を見ない。
24ヶ月目(表5):雄ではいずれの項目にも明らかな差を見ない。雌では各群共にRed cell、Hb及びHt値が対照群に比べいずれも有意の増加ないしその傾向を示す。またR−7.5群でRed cellがN−7.5群に比べ有意の減少を示すほか、同一添加量による非照射群と照射群の群間には明らかな差を見ない。
上述のように6、12、18及び24ヶ月目の各時期で群間にいくつかの差を見るが、対照群と非照射群及び照射群の群間あるいは非照射群と照射群の群間に、一定の傾向を認めない。
6ヶ月目(表6−1、2):雄ではN−2群でAlbumin及びGlucoseが対照群に比べいずれも有意の増加を、R−2群では、Protein及びS−Kが対照群に比べ有意の減少をA/G比、Glucose及びChol.%が有意の増加を示す。N−7.5群ではProtein及びF−Chol.が対照群に比べ有意の減少を、Glucose,Chol.%及びNEFAが逆に有意の増加を示す。R−7.5群ではProtein及びS−Kが対照群に比べ有意の減少を示し、Glucose及びTrigly.が有意の増加を示す。
またR−2群のProtein及びAlbuminはN−2群に比べ有意の減少を、R−7.5群のAlbuminおよびS−KはN−7.5群に比べ有意の減少を、Glucoseが逆に有意の増加を示す。雌ではR−7.5群でF−Chol.が対照群に比べ有意の減少を示す。またR−2群のNEFAはN−2群に比べ有意の増加を示す。
12ヶ月目(表7−1、2):雄ではN−2群でGlucose及びS−Mgが対照群に比べ有意の減少を示す。N−7.5群ではTrigly.が対照群に比べ有意の増加を、S−Mgが有意の減少を示す。R−7.5群ではGOTが対照群に比べ有意の増加を、S−Mgが有意の減少を示す。
またR−2群のGlucose及びS−MgはN−2群に比べ有意の増加を示し、R−7.5群のF−Chol.はN−7.5群に比べ有意の減少を示す。雌ではN−2群でChol.%及びTrigly.が対照群に比べ有意の増加を示し、S−Caが有意の減少を示す。R−2群ではT−Chol.及びChol.%が対照群に比べ有意の増加を示す。R−7.5群でもT−Chol.及びChol.%が対照群に比べ有意の増加を示す。またR−2群のChol.%,S−Mg及びS−NaはN−2群に比べ有意の増加を示し、R−7.5群ではChol.%及びS−NaがN−7.5群に比べ有意の増加を示す。
18ヶ月目(表8−1、2):雄ではN−2群でS−Caが対照群に比べ有意の減少を示す。R−2群ではProtein,Urea−N及びS−Mgが対照群に比べいずれも有意の減少を示すが、N−7.5群及びR−7.5群ではその群間及び対照群に比べ有意の差を見ない。雌ではR−2群でF−Chol.が対照群に比べ有意の減少を示す。N−7.5群ではGPTが対照群に比べ有意の増加を示す。またR−2群のUrea−NはN−2群に比べ有意の減少を示し、R−7.5群のGlucoseはN−7.5群に比べ有意の増加を示すが、S−Ca及びS−Mgは有意の減少を示す。
24ヶ月目(表9−1、2):雄ではN−2群でChol.%が対照群に比べ有意の増加を示す。R−2群ではGOTが対照群に比べ有意の減少を示し、Chol.%,S−Pi及びS−Caが有意の増加を示す。N−7.5群ではT−Chol.,NEFA及びS−Kが対照群に比べ有意の減少を示し、S−Caが有意の増加を示す。R−7.5群ではChol.%及びS−Piが対照群に比べ有意の増加を示す。またR−2群のA/G比は、N−2群に比べ有意の減少を示し、S−Pi及びS−Caは有意の増加を示す。R−7.5群ではS−PiがN−7.5群に比べ有意の増加を示す。雌ではN−2群でProtein,F−Chol.,Trigly.及びS−Piがいずれも対照群に比べ有意の減少を示す。R−2群ではProtein,T−Chol.,F−Chol.及びTrigly.がいずれも対照群に比べ有意の減少を示し、S−Piが有意の増加を示す。N−7.5群ではProtein,T−Chol.,F−Chol.,Trigly.及びS−Piがいずれも対照群に比べ有意の減少を示し、Glucoseが有意の増加を示す。
R−7.5群ではT−Chol.及びF−Chol.が対照群に比べ有意の減少を示すが、N−7.5群の群間には有意の差を見ない。
上述のように6、12、18及び24ヶ月目の各時期で群間にいくつかの差を見るが、対照群と非照射群及び照射群の群間あるいは非照射群と照射群の群間に一定の傾向を認めない。
6、12、18及び24ヶ月目の各時期に解剖した動物の臓器実測値及び体重比が共に同一方向に変化したものについて述べる。
6ヶ月目(表10、11):雄ではN−2群で肝臓が、N−7.5群で腎臓が、R−7.5群で肝臓が、いずれも対照群に比べ有意の増加を示すが、非照射群と照射群の群間には有意の差を見ない。雌ではN−2群で肺が対照群に比べ有意の増加を、N−7.5群で甲状腺が有意の減少を示す。またR−7.5群で下垂体がN−7.5群に比べ有意の増加を示す。
12ヶ月目(表12、13):雄ではR−7.5群で甲状腺がN−7.5群に比べ有意の減少を示す以外、有意の差を示す臓器を見ない。雌ではR−7.5群で甲状腺が対照群に比べ有意の減少を示すのみで、非照射群と照射群の群間にも有意の差を見ない。
18ヶ月目(表14、15):雄ではR−2群、N−7.5群及びR−7.5群で副腎が対照群に比べいずれも有意の増加を、またR−7.5群で腎臓が有意の増加を示すが、非照射群と照射群の群間には有意の差を見ない。雌ではN−2群で副腎が対照群に比べ有意の増加を示し、R−7.5群の甲状腺が有意の減少を示す。
しかし、非照射群と照射群の群間には有意の差を見ない。
24ヶ月目(表16、17):雄ではR−2群及びR−7.5群で腎臓が対照群に比べ共に有意の増加を示すのみである。雌では同一方向に変化を示す臓器を見ない。
上述のように6、12、18及び24ヶ月目の各時期で群間にいくつかの差を見るが、対照群と非照射群及び照射群の群間あるいは非照射群と照射群の群間に一定の傾向を見ない。
6ヶ月目:雄では対照群で肺膿瘍を1例、N−2群で腎臓髄質不明瞭、肝臓変縁鈍及び肝臓横隔面陥入による表面隆起(いわゆる横隔膜ヘルニア)を各々1例認めるほかには変化を見ない。雌では対照群及びR−7.5群で卵管水腫を、N−7.5群で横隔膜ヘルニアを各々1例認める。
12ヶ月目:雄では対照群で肺膿瘍及び横隔膜ヘルニアを、N−2群で肺表面の灰白色結節を、各々1例認める。雌では対照群で肺炎を1例認めるほか変化を見ない。
18ヶ月目:雄では精巣の萎縮が対照群で5例、N−2群で3例、R−2群で4例、N−7.5群で5例及びR−7.5群で4例を認める。また精巣の腫瘍が上記の順序で各々4、5、3、1及び4例認められる。そのほかの臓器では、肺炎、肺膿瘍、肝臓の白色斑、脾臓の腫大、副腎肥大、下垂体血腫、甲状腺肥大及び下腹部の腫瘤などの変化が散見されるが、いずれもその発生例は少ない。雌では下垂体血腫及び肥大、甲状腺肥大、肺炎及び肺膿瘍、肝臓の表面粗ぞう化子宮蓄膿及び卵巣肥大などの変化を散発的に認める。
24ヶ月目:雄では肺炎が対照群で6例、N−2群で5例、R−2群で3例、N−7.5群で2例、肝臓の表面粗ぞう化が対照群で4例、N−2群で1例、R−2群で2例、N−7.5群で3例、腎臓の表面粗ぞう化が対照群で4例、N−2群及びR−2群で各6例、N−7.5及びR−7.5群で各4例、精巣の萎縮が対照群で3例、N−2群で5例、R−2群で4例、N−7.5群及びR−7.5群で各3例、精巣の腫瘍が対照群で4例、N−2群で7例、R−2群で5例、N−7.5群で4例、R−7.5群で2例に認められる。
そのほかの臓器では肺の充うっ血及び肺炎、脾臓の腫大、下垂体の血腫及び肥大などの変化を見るが、その発生例は少ない。雌では下垂体血腫が対照群で5例、R−2群で2例、N−7.5群で1例、R−7.5群で2例、肺炎が対照群で3例、N−2群で4例、R−2群で3例、N−7.5群及びR−7.5群で各2例、肝臓の表面粗ぞう化が対照群で5例、R−2群で2例、N−7.5群で1例、腎臓の表面粗ぞう化が対照群で1例、N−2群で3例、R−2群で2例、N−7.5群で1例、R−7.5群で2例、脾臓の腫大が対照群で6例、R−2群で1例に認められる。そのほかの臓器では、下垂体の肥大、肺膿瘍、肝臓の白色斑、甲状腺肥大、卵巣肥大及び皮下腫瘤などの変化を散発的に認める。
自然死動物:雄雌共に主な変化として肺の膿瘍及び充うっ血、肝臓の表面粗ぞう化、脾臓の腫大及び雄の精巣の萎縮及び腫瘤の発現が、各群それぞれれ2〜5例に認められる。
上述のように6、12、18及び24ヶ月目の定期解剖例及び自然死解剖例の肉眼的所見には、雄雌共に対照群と非照射群及び照射群の群間あるいは非照射群と照射群の群間に著しい差を認めない。
6、12、18及び24ヶ月目定期解剖及び自然死解剖した組織学的検査の結果、腫瘍については腫瘍の項で述べる。
6ヶ月目(表18):主な変化としては、雄雌共に肺で肺胞壁の肥厚及びリンパ様組織の拡大を見る。そのほかの臓器では、雄の腎臓で細尿管内の硝子様円柱及び上皮性円柱の出現、細尿管上皮細胞の硝子滴変性及び再生を見るが、これらの変化は対照群と非照射群及び照射群の群間あるいは非照射群と照射群の群間あるいは非照射群と照射群の群間に著しい差を見ない。
12ヶ月目(表19):主な変化は、雄雌共に肺でリンパ様組織の拡大、腎臓で細尿管内の硝子様円柱及び上皮性円柱の出現、細尿管の拡張及び細尿管上皮細胞の再生などである。このほかの臓器では、雄の腎臓でボーマン嚢壁肥厚及び間質内円形細胞浸潤を認める。これらの変化には群間に殆ど差を見ない。
18ヶ月目(表20): 雄雌の主な変化は、肺で気管支内及び肺胞内の円形細胞浸潤、肺胞壁肥厚、気管支周囲リンパ様組織の拡大、肝臓で細胆管の増殖、腎臓でボーマン嚢壁肥厚及び糸球体の基底膜肥厚、細尿管内硝子様円柱、細尿管の拡張及び細尿管上皮細胞の再生などを認める。このほかの臓器では、雄の腎臓で間質の結合織増殖及び円形細胞浸潤などを認める。これらの変化には群間に殆ど差を見ない。
24ヶ月目(表21−1、2):雄雌共に心臓で心筋の線維化、肺で気管支内円形細胞浸潤及び肺胞壁肥厚、肝臓で肝細胞の空胞化、限局性壊死及び細胆管の増殖、腎臓でボーマン嚢壁の肥厚及び糸球体の基底膜肥厚、細尿管内硝子様円柱、細尿管の拡張及び細尿管上皮細胞の再生、間質の円形細胞浸潤などを認める。このほかの臓器では、雄の腎臓で間質の結合織増殖を、雌の心臓で心筋の空胞などを認める。これらの変化には群間に著しい差を見ない。
自然死動物(表22−1、2):雄雌の主な変化は、心臓で心筋の線維化、肺で気管支内円形細胞浸潤、肺胞内円形細胞浸潤及び肺胞壁肥厚などの、肺炎像が見られる。肝臓では肝細胞の限局性壊死及び空胞化、細胆管の増殖、腎臓では糸球体の基底膜肥厚、細尿管内硝子様円柱の出現、細尿管の拡張、間質の円形細胞浸潤及び結合織の増殖などいわゆる慢性腎症(Chronic nephropathy)を、脾臓では充うっ血を示すものが多い。これらの変化には群間に著しい差を見ない。
腫瘍(表23):雄では精巣の間質細胞腫が最も多く、このほか下垂体の色素嫌性腺腫、甲状腺の腺癌、肝臓の結節性増殖(Neoplastic nodules)及び細網細胞腫、副腎及び膵臓の腺腫、精巣の中皮腫、小腸の血管内皮腫、皮膚の扁平上皮細胞腫、リンパ節のリンパ肉腫などを認める。
雌では下垂体の色素嫌性腺腫、甲状腺及び副腎の腺腫、子宮の線維肉腫、卵巣の顆粒膜細胞腫瘍と腺腫、大腿骨の骨肉腫、乳腺の線維腺腫と腺腫、腹部皮下織の線維腫などを認める。
腫瘍発現動物数は、雄では対照群、N−2群、R−2群、N−7.5群及びR−7.5群でそれぞれ16、18、14、16及び14例である。雌ではそれぞれ8、5、5、2及び3例である。以上のように腫瘍の発現については、雄が雌より若干多く認められるが、群間に一定の傾向を見ない。
γ線照射かまぼこの安全性を調べる目的でラットによる24ヶ月間の慢性毒性試験を行った。
一般症状、体重、摂餌量及び死亡率では雄雌共に24ヶ月に亘って、対照群と非照射群及び照射群あるいは非照射群と照射群の群間に明らかな差は認められない。また定期的に行った血液形態学的検査及び血清生化学的検査の各時期で若干有意の差を認めるが、群間に著しい差は認められない。病理学的検査でもその臓器重量及び腫瘍発現数にも群間で明らかな差は認められない。なお、途中自然死動物の検査でも腫瘍発現数に差は認められない。
以上、γ線照射かまぼこをラットに投与しても、今回の条件下では照射によると見なされる影響は認められなかった。
γ線照射かまぼこの繁殖生理におよぼす影響および催奇形性の有無を調べる目的でマウスによる次世代試験を行った。
検体として科学技術庁食品照射研究運営会議指定のかまぼこを用いた。非照射かまぼこおよび日本原子力研究所高崎研究所において450kradでγ線照射した照射かまぼこを凍結乾燥により粉末化し、マウス繁殖用粉末飼料(オリエンタル酵母社製、NMF)に各々2W/W%の割合で添加したものを固型化し、動物に与えた。なお、対照動物にはNMF飼料を固型化し摂取させた。
4週令のddY系マウス雄雌各々200匹を静岡県実験動物農業協同組合より購入し、試験に供した。
4週令で購入した動物を1週間飼育観察の後、健康と見られる雄雌120匹を選定した。これらを雄雌各々40匹よりなる3群に分け、対照群、非照射群および照射群とした。3群に分けた動物(以下Pと略す)には、以後全期間各々の検体を与え、4週間後1代目(F1と略す)を得るために各群ごとに雄雌1:1同居による交配を4日間に亘り行った。同居翌朝、膣栓の存在する動物を妊娠動物と見なし、この日を妊娠0日と定めた。妊娠動物は2分し、1群は妊娠末期に繁殖生理に及ぼす影響を検査するために剖検し、他の1群はF1を出産させた。更にF1を離乳時に2分し、1群は離乳時の催奇形性を検査するために剖検し、他の1群は離乳後6週間飼育し2代目(以下F2と略す)を得るために交配させた。その後は図1に示す様に3代目(以下F3と略す)まで実験を行い、各世代で骨格標本を用いての催奇形性について検査した。
なお、全試験期間中動物室は温度25±1℃、湿度55±5%に維持した。
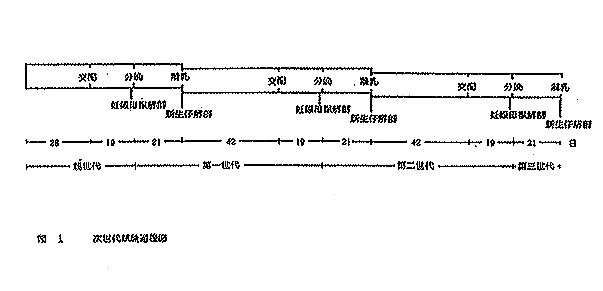 |
一般症状は毎日、体重については一般飼育期間および保育期間(生後3週まで)は週1回、妊娠期間中は毎日測定した。
P、F1およびF2世代において、親動物の交配率および妊娠率を検査した。また、妊娠母獣について、各世代において妊娠18日目に各群15匹の母動物(F2の照射群は16匹)を任意に選び、エーテル麻酔の後開腹し、総着床数、着床痕跡数、胎盤遺残数および浸軟胎仔数を調べ、更に生存胎仔について個別に体重を測定し、性別および外形異常の有無を調べた。また、出産させた動物についても、平均同腹仔数および出産日平均体重を調べた。
離乳時(3週令)に母獣が生存していた乳仔について、生存率を調べた。また、各世代において、F1およびF2については一部、F3については全ての動物を剖検の後、肝、腎および生殖器の重量測定を行った。
妊娠末期胎仔および3週令の動物について、剖検の後90%アルコールで固定し、Dawsonのアリザニン・レッドS染色法で骨格標本を作製し、実体顕微鏡下で観察した。また、化骨進行度を調べる目的で、仙椎と尾椎の合計数、指骨および趾骨に確認された中節骨数、踵骨距骨数を測定し、化骨進行度の指標とした。
各測定値の推計処理は妊娠動物の体重、平均着床数、平均同腹仔数、臓器重量および骨格検査のうち仙椎数+尾椎数について、Studentのt検定を行い、胎仔体重および出生仔体重についてはWeilのWeighting factorを用い、平均値および標準偏差値を求めた後、t検定を行った。交配率および妊娠率についてはχ・E(2)検定を用い、その他の測定値についてはWilcoxonの順位和検定によって、それぞれ対照群と添加群、更に非照射群と照射群間についての比較を行った。
各世代を通して対照群、非照射群および照射群のいずれの群にも特記すべき変化は認められなかった。
結果は表1に示す通りである。F2世代の雌生存胎仔平均体重について、非照射群に比べ照射群で有意に低い値を示すが、その他の項目については明らかな差は見られない。
3週令までは雄雌混合値、4週令以後は雄雌別とし、結果は図2に示す通りである。Pでは雄の照射群が対照群に比べやや低い値を示すが、雌では差が認められない。F1では雄雌共に各群に明らかな差は見られないが、F2では3週以後雄雌共に非照射群および照射群が対照群に比べやや低値を示す。F3では各群とも明らかな差は見られない。
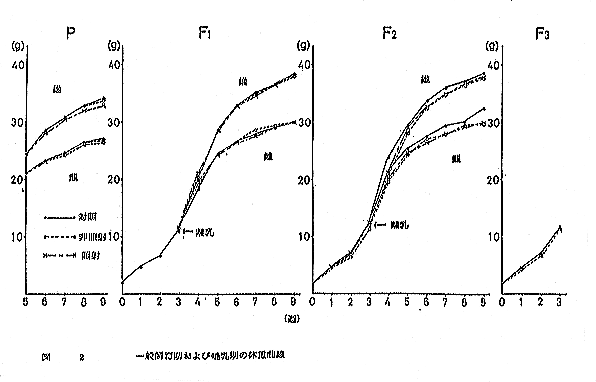 |
妊娠母獣の妊娠0日目に対する体重の増加量を測定し、その結果を図3に示す。各世代を通じ、群間に著名な差は見られない。
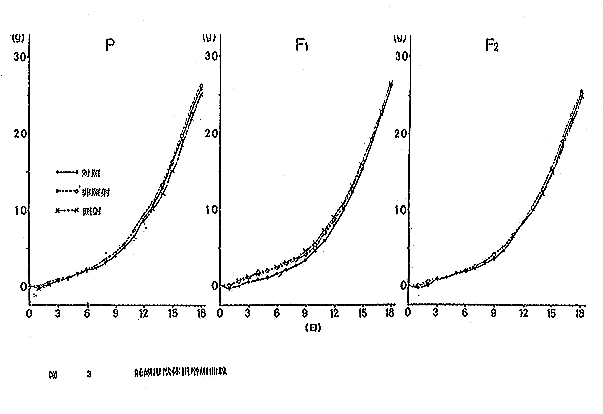 |
(イ)離乳時の生存率:結果は表2に示す通りである。各世代とも群間に著明な差は見られない。
(ロ)剖検所見および臓器重量:肉眼所見としては、1側腎の欠損がF1の対照群に1例、非照射群に3例、F2の非照射群に1例、更にF3の対照群に3例、非照射群に3例、照射群に4例それぞれ認められ、腎の変形がF3の照射群に1例見られる。
臓器重量については表3および表4に示す通りである。非照射群と照射群の間に有意差が認められたものについて述べると、雄ではF2およびF3の肝比重量が照射群で低値を示すが、精巣比重量では照射群で高値を示す。雌ではF2の腎および肝実重量が照射群でそれぞれ高値を示す。F3では卵巣実重量、腎および卵巣比重量が照射群で高値を示すが、肝比重量は低値を示す。この他の項目についても対照群に比べ、非照射群ならびに照射群で有意な変化が認められるが、いずれも軽度の変化である。
結果は表5に示す通りである。
F1世代:頚肋については、対照群が12例(7.9%)、非照射群が20例(12.1%)、照射群が33例(21.9%)と照射群でやや高い値を示す。頚椎については、椎弓先端の一部が椎体から分離しているものを椎弓分離とし、先端が椎体から離れずに2つに分かれたものを椎弓分岐としたが、いずれも照射群でやや高い値を示す。その他の項目ならびに化骨進行度については群間に著明な差は見られない。
F2世代:頚椎の椎弓分岐について、照射群でやや高い値を示すが、有意差は認められず、その他の項目についても群間に一定の傾向は認められない。
F3世代:頚肋について、照射群でやや高い値が見られる以外その他の項目について著明な差は認められない。
結果は表6に示す通りである。
F1世代:いずれの項目についても群間に著明な差は認められない。
F2世代:頚肋について、照射群で高い値を示し、有意差が認められるが、その他の項目について群間に一定の傾向が見られない。
F3世代:胸骨の欠損および仙椎前骨数異常がいずれも1例照射群にのみ認められるが、その他の項目について群間に明らかな差は見られない。
なお、頚肋については、末期胎仔のF1、F3および新生仔のF1、F3において照射群でその出現率が高かったが、世代の進行に伴う出現頻度の増加は見られず、世代間に一定の傾向がないこと、またマウスの頚肋については、16〜29%程度の出現がいわゆる正常動物で見られる。したがって、この頚肋の出現は照射によるものとは考えられない。
照射かまぼこの繁殖生理におよぼす影響ならびに催奇形性の有無を調べる目的で、マウスによる連続3代に亘る次世代試験を行った。一般症状、体重、繁殖生理値、妊娠末期および離乳期の検査ならびに骨格検査について、3世代に亘り検討したが、照射によると考えられる明らかな傾向は認められなかった。
(1)玉川 実ら、応用薬理、24、741〜750(1982)
(2)横井義之、応用薬理、12、201〜214(1976)
(3)亀山義郎ら、先天異常、20、25〜106(1980)
照射食品の遺伝学的安全性を評価するためには試験法の選択がきわめて重要である。数多くの遺伝毒性試験のうちどれを取り上げるべきかについては、試験対象の重要度に応じて配慮されるべきであろうが、かまぼこはその消費量もかなり大きいことを考慮して、厚生省が公にした「食品添加物などの遺伝的安全性評価の基準」に示された各種の試験法をほぼカバーするに足りる項目の試験法を選択した。なお哺乳動物を用いる特定座位試験は現時点において、最も信頼するに足る試験法とされているが、その実施には莫大な費用を要し、しかも試験法自体検討の余地が大きいとされている点を考慮して今回は実施を見送った。照射食品について哺乳動物による特定座位試験が実施されたという報告は諸外国においても皆無であり、哺乳動物による優性致死試験の結果が最も重視されているのが現状である。
今回実施した試験項目は次のとおりである。
1.細菌を用いた突然変異誘発試験
1)細菌に対する突然変異誘発試験
2)マウスによる宿主経由試験
2.哺乳動物培養細胞を用いた突然変異誘発試験
1)染色体異常試験(試験管内)
3.哺乳動物の生体を用いた突然変異誘発試験
1)染色体異常試験(マウス生体による小核試験)
2)マウスによる優性致死試験
検体の製造は株紀文に依頼し、照射は日本原子力研究所高崎研究所で実施した。照射線量は0.6Mrad(0.3Mrad/時)。検体は照射・非照射とも直ちに凍結乾燥し、−20℃で保存した。
(イ)検定菌:Salmonella typhimurium TA100,TA98,TA1535,TA1537,TA1538およびE.col
WP2 uvrAを使用した。
(ロ)試験検体:照射および非照射かまぼこの凍結乾燥物を水またはメタノールで抽出したものを試験試料とした。
(ハ)試験操作法:プレート法(Plate incorporatio
method)によった。
試験結果は表B−1に示すごとくで、6菌株のすべてについて照射・非照射を問わず、陰性対照にくらべて変異集落の増加は認められなかった。
以上の結果から、照射かまぼこは使用した試験系について突然変異性を有しないものと結論される。
検定菌としてSalmonella typhimurium G46を用い、BDF1雄マウス(24〜26g)に照射および非照射かまぼこの70%メタノール抽出物0.15gを経口的に5日間連続投与した。
表B−2に示すごとく1平板あたりの変異コロニー数に関して、対照、照射および非照射群の間に有意の差は認められなかった。
チャイニーズ・ハムスターの胎仔細胞(CHE)とヒトのリンパ球(HLC)に70%メタノールのカマボコ抽出物を最終濃度1mg/ml、2mg/mlになるように培地に加え、24時間後に染色体標本を作製した。観察はハムスター細胞では100個、ヒトリンパ球では50個の分裂中期像について行なった。
照射、非照射のいずれにおいても、有意な染色体異常の増加は認められなかった。
照射および非照射かまぼこの70%メタノール抽出物をBDF1(9週令)雄マウスに経口的に5日間連続投与した。投与24時間後に殺し、骨髄細胞の塗抹標本を作製した。観察はマウス1匹あたり、1500個の多染性赤血球をカウントし、その中の小核を有した多染性赤血球の出現頻度を求めた。
表B−4に示すごとく照射および非照射群のいずれにおいても小核の有意な増加は認められなかった。
BDF1雄マウス(静動協)に対して6週令から14週令までの8週間にわたり照射および非照射かまぼこ飼料を与えた。陰性対照には固型CMF飼料を与え、陽性対照群はmethyl methanesulfonate(MMS)を同期間4日毎に1回(計14回)、1回につき12.5mg/kgを腹腔内投与した。実験に用いた雄マウスは各群30頭とし、陽性対照群のみ20頭とした。投与後1頭の雄マウスに対し1頭の雌を4日間にわたり交配し、この交配を2回くり返した。交配後妊娠中期に雌マウスを屠殺、開腹し、黄体数、生存および死亡胎仔数を調べ、優性致死誘発率を求めた。優性致死誘発率は下記の2通り(A,B)の式により算出した。
A=[1−(妊娠雌あたりの生存胎仔数:処理群/妊娠雌あたりの生存胎仔数:対照群)]×100
B=[1−(妊娠雌あたりの生存胎仔数/胎仔数:処理群) ÷ (妊娠雌あたりの生存胎仔数/胎仔数:対照群)]×100
また陽性対照群以外の群において処理期間中、週に1度体重および摂餌量を測定した。
体重および摂餌量は投与期間を通じて、多くの場合、陰性対照群をうわまわっていた。
表B−5にそれぞれの群の平均黄体数、着床数、生存胎仔数、ならびに誘発優性致死率を示す。非照射および照射のかまぼこ群のすべてにおいて、誘発優性致死率は負の値を示した。このことは陰性対照群の着床数の少なかったことと、上に述べた様に実験群での体重および摂餌量が陰性対照群よりほとんどの場合統計学的に有意に高いことに起因するものと思われた。
またかまぼこの非照射、照射群間において有意な差は認められず、これらの結果からかまぼこのCo−60による照射によって優性致死誘発作用を有する物質の生成などは起さないものと結論された。