図1 無酸素下におけるグルコースの放射線分解
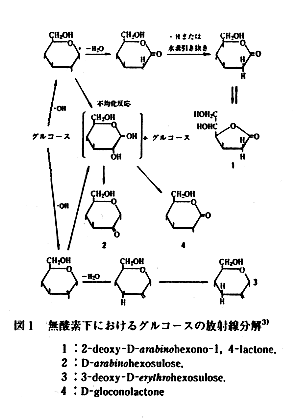 |
放射線処理による食品の殺菌、殺虫、発芽防止や熟度調整といった効果は、加熱処理等の他の方法と同様化学変化に基づくものである。しかし食品の放射線保蔵は比較的新しい方法であり、また一般消費者の放射能アレルギー故に、健全性に関する検討に多大の労力が費されてきた。この結果、食品照射に関しては、これまでに他のいかなる処理法も比べものにならないデータが蓄積されている。従来照射食品の健全性評価は動物試験に頼ってきた。しかし長期間、多種品目の動物試験を、全ての品目についてあらゆる可能な条件下で行うことは、コストの面からも不可能である。一方、食品や食品の主要構成成分の変化が放射線化学的に明らかにされるにつれ、これらの放射線化学的データが照射食品の健全性評価に用いられるようになってきた。
FAO/IAEA/WHOの合同専門家委員会*1)は1976年の会合で、放射線分解生成物のほとんどのものは非照射食品中にも見出せること、また10kGy以下での生成量は極く微量であることから、いかなる毒性問題もないと結論づけている。1980年には、主要食品成分の放射線分解生成物は、食品の由来いかんにかかわらず同じ成分からは同一な生成分を生ずること、分解生成物の多くは既に許容されている他の食品加工手段によって生成するものと同一であることなどから、これら放射線分解生成物の性状や濃度から判断して毒物学的な危害を生ずることはないと結論している。またこれまでに行われた放射線分解生成物の分析結果から、一連の照射食品を評価するのに際し、1つの食品データを他の食品にも及ぼして考えることの妥当性が明確にされた。
今後さらに放射線化学的、毒物学的研究が積み重ねられれば、照射食品の健全性評価は化学的評価だけで行うことが可能になるであろうとの考えが出されている。このような考えのもとに、放射線分解生成物に関するデータを用いて、モデル食品等における健全性評価の試みがこれまでにいくつか報告されている。そこで、これらの報告を中心に、主として健全性評価のための放射線分解生成物といった観点からまとめてみた。
また最近の動向として、米国FDAの1986年の最終規則に盛り込まれている放射線分解生成物についての考え方についても付記する。
食品構成成分に対する放射線照射効果には、成分分子に直接エネルギーが吸収されて反応が起こる直接効果と、水分子にエネルギーが吸収されて生じたラジカルなどが成分分子と反応して変化をもたらす間接効果とがある。大部分の食品は多量の水を含むので、主として間接効果が寄与している。
そこでまず水の放射線分解生成物と食品成分分子との反応について簡単に述べておく。
放射線による水分子の分解生成物と生成のG値*2)(100eVのエネルギーが吸収されたときに生成または分解される分子の数)は、以下のような簡単な式で示される。
H2O〜→OH(2.7)+H(0.6)+eaq・E(−)(2.7)+H2O2(0.7)+H2(0.5)
これら分解生成物のうち成分分子に変化をもたらす主要な活性種はOHラジカル、H原子、水和電子(eaq・E(−))である。
OHラジカルは強力な酸化剤であり、芳香族やオレフィン系化合物に付加したり、C−HやS−H結合からHを引き抜く。eaq・E(−)も反応が高く、大部分の芳香族化合物、カルボン酸、ケトン、アルデヒド、チオールに速やかに付加する。H2O2は再結合反応によって形成されるが、酸素が存在しないとその形成は非常に低い。H原子はC−H結合からHを引き抜くかオレフィン系化合物に付加するが、比較的収率は低い。
単糖類の放射線分解について数多くの研究が行われているが、ここでは川岸ら*3)によって明らかにされているグルコース水溶液の例を示す。先に示した水の放射線分解によって生じた主要ラジカルのうち、H原子やeaq・E(−)はグルコースとの反応性が低く(k=10・E(6)〜10・E(7)M・E(−1)sec・E(−1))無視できる程度である。OHラジカルとの反応速度は1.9×10・E(9)M・E(−1)sec・E(−1)と大きく、放射線分解反応の大部分を占める。
無酸素下でのグルコースの放射線分解は図1に示すように、主反応はOHラジカルの水素引き抜きによって生じた糖ラジカルの脱水反応によるデオキシジカルボニルの生成である。特に2−deoxy−D−arabinohexono−1,4−lactone(1)の生成が顕著でG値は0.6である。その他の(2)〜(4)に示した物質が生成するが、微量成分としてグリオキザール、グリコールアルデヒド、マロンアルデヒド、ジヒドロキシアセトンなどC2、C3化合物も同定されている。
酸素が存在するとグルコースラジカルは速やかに酸素と反応し、ハイドロパーオキシラジカルを経てジカルボニル糖およびC−C結合開裂によるC3〜C5の糖を生成する。この場合OHラジカルによる水素原子の引き抜き反応の位置特異性がみられず、R1からR5に示すラジカルすべてに起因する生成物が同定されている(図2)。
放射線化学反応を定量的に表わす値としてG値が用いられる。表1には、グルコースの主要な放射線分解生成物のG値および、DIEHLら*4)がもとめた5kGy照射時の100g当りの生成量を同時に示した。G値から生成量は次式により計算されている。
C=1.04×G×M×10・E(−2)
(C:生成分子の濃度mg/100g、M:分子量、D:線量kGy)
なお、この5kGy照射時の生成量に関しては、モデル食品系の項で改めて述べる。
| 化 合 物 |
G 値 |
5kGyでの収量 (mg/100g) |
||
| 無酸素下 |
酸素存在下 |
無酸素下 |
酸素存在下 |
|
| Glucose(decomposition) |
−3.5 |
−3.5 |
−32.5 |
−32.5 |
| Gluconic acid |
0.35 |
0.4 |
3.5 |
4.1 |
| Glucuronic acid |
0.9 |
− |
9.0 |
− |
| Glucosone |
− |
0.4 |
− |
4.1 |
| Erythrose |
0.25 |
− |
1.6 |
− |
| Deoxycarbonyls and other deoxy compounds |
− |
0.3 |
− |
2.7 |
| 2−Deoxygluconic acid |
− |
1.0 |
− |
9.4 |
| C2−fragments* |
0.85 |
0.8 |
2.6 |
2.4 |
| C3−fragments* |
0.80 |
0.8 |
3.7 |
3.7 |
| *C2、C3フラグメントの生成は疑わしい。 |
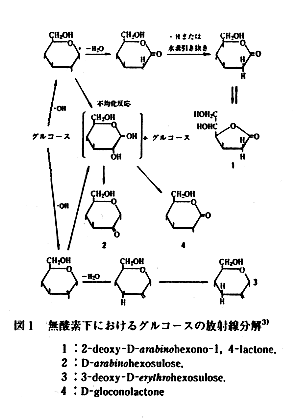 |
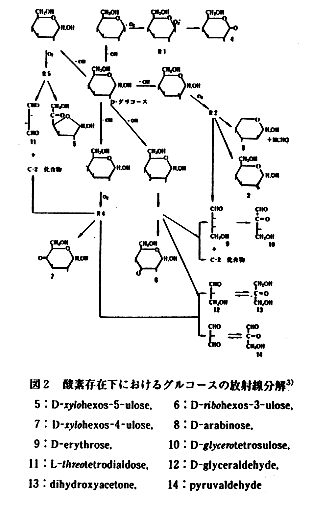 |
他の糖類の場合でも、放射線化学的観点からはその反応系はグルコースなどの単糖類の場合と同様である。例えば二糖である蔗糖は、グリコシド結合へのOHラジカルの攻撃によりグルコースとフラクトースに分割される。生成した単糖は初めから存在していた場合と同様に反応し、新しい生成物は何も作らない。多糖類の場合でもグリコシド結合が照射によって分解され、最終産物は単糖と同様の分解生成物である。
多くの果実は、大量の水と炭水化物が主成分であり、この他少量のタンパク質、脂肪、微量成分が含まれている。BASSON*5)は、果実は炭水化物の濃縮水溶液に少量のタンパク質、脂肪、ビタミン、無機物等の含まれるモデル系に近似されるとして、放射線分解物の生成量を求めている。
彼はグルコースの分解速度に対する他の化合物の影響を決めるために、その濃度や反応速度から計算して、以下のように結論している。
(a)e・E(−)aqによるグルコースの分解はG=0.02、全糖の分解はG=0.06。
(b)H原子によるグルコースの分解はG=0.10、全糖の分解はG=0.34。
(c)OHラジカルによるグルコースの分解はG=0.83、全糖の分解はG=2.60。
(d)(a)(b)(c)からモデル果実の放射線分解は糖の分解(G=3.0)と、分解生成物ハイドロパーオキシラジカルの形成(G=2.8)とに要約される。
(e)ハイドロパーオキシラジカルは不均化反応によってH2O2(G=1.4)を生ずる。H2O2は水の分解からも直接生ずる(G=0.8)ので全収量はG=2.2である。
放射線分解生成物のうちα、β−不飽和カルボニルやH2O2は毒性を有する物質である。しかし実際の果実が照射される条件下すなわち空気中での照射では、α、β−不飽和カルボニルは生成されない。また、これらは2−デオキシ糖の水溶液の加熱でも生成するが、缶詰の場合何ら毒性を示さないことが長年にわたり証明されている。H2O2はアミノ酸その他の食品構成成分とキレートを生成することにより毒性を示すが、グルコースが存在すると反応してグルコン酸を生成する。また遊離H2O2の半減期は1日以内であることから、これら分解生成物の毒性に関しては何も考慮する必要はない。
実際の果実の構造、種子、細胞壁、皮などを考慮すれば、水溶液とはいえず、固体、液体、ゲル層が混在している状態で、単純なモデル水溶液とは異なる。しかし毒物学的観点からは、食用部分からの分解産物だけが問題となる。食用部分は主に均一な柔組織からなり、大部分は液状であるからここで用いられているモデル水溶液の近似は妥当と考えられる。生体系では酵素活性等生理変化がおこるが、これは量的な影響を及ぼすだけで質的な変化をもたらすことはない。
照射により食品中に形成される揮発性成分の大部分は脂質に由来する。NAWAR*6)は脂質のモデル化合物の放射線分解機構に基づき、食品中の放射線分解生成物とくに揮発性成分についてその種類および生成量に関する詳細な考察を行っている。ここでは、彼の報告を中心に脂質の放射線分解について述べる。
照射による脂質の変化は、以下に示すように分子状酸素との触媒反応による自動酸化と、放射線エネルギーによる直接あるいは間接作用による反応に大別される。
無酸素下で脂肪酸を照射すると脱炭酸がおこり、炭素数の1個少ないアルカンおよびアルケンをはじめとする炭化水素が生成する。すなわち放射線分解生成物はもとの脂肪酸組成に大きく左右されている。
酸素存在下で脂肪酸類を照射したときには、フリーラジカルの連鎖反応による自動酸化がおこる。照射によるフリーラジカルの形成により、二重結合のα位の水素が引き抜かれ、その位置への酸素の攻撃によって過酸化ラジカル(ROO・)が形成される。このROO・は他の分子(RH)からHを引き抜きヒドロパーオキシド(ROOH)を形成する。
RH+ ・OH→R・ +H2O
R・ +O2→ROO・
ROO・ +RH→ROOH+R・
このヒドロパーオキシド分子のO−O結合の切断が速やかにおこり、アルコキシラジカルの中間体が得られ、さらにC−C開裂によって、アルデヒド、炭化水素、酸などの分解物を生ずる。
食品中の脂質の大部分はトリアシルグリセリドの形であることから、このモデル化合物を用いた脂肪の放射線分解機構が詳細に検討されている。図3に示すように、トリアシルグリセリド分子のカルボニル基の近くの5カ所と、脂肪酸部分のC−C結合の全ての部位で切断が生じ、表2に示すような種々の放射線分解生成物が生ずることが明らかにされている。
| 切断個所 |
分解生成物 |
| a |
Cn脂肪酸 プロパンジオール ジエステル プロパンジオール ジエステル |
| b |
Cnアルデヒド ジグリセリド オキソプロパンジオール ジエステル 2−アルキル シクロブタノン(Cn) |
| c |
Cn−1アルカン Cn−1 1−アルケン ホルミルジグリセリド |
| d |
Cn−2アルカン Cn−2 1−アルケン アセチルジグリセリド |
| e |
Cn脂肪酸メチルエステル エタンジオール ジエステル |
| fi |
Cn−x炭化水素 より短鎖の脂肪酸トリグリセリド |
| i=1,2,…,n−3 x=炭素数 3〜 n−1 |
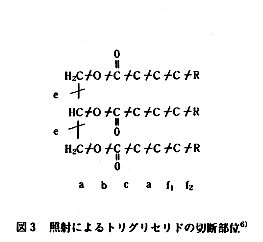 |
複雑な食品中の脂質画分から生成する放射線分解生成物は、天然の脂肪や脂肪酸のモデル系で得られる化合物に定性的には類似している。例えば60kGy照射したポーク中の6種の主要生成炭化水素は、ヘプタデセン、ヘキサデカジエン、ペンタデカン、テトラデセン、ヘプタデカン、ヘキサデセンの順に多い。脂肪1kg当りのmg数としては、各々90、89、55、38、34、22と計算され、照射試料中の脂肪酸組成を反映している。これらの計算値は実際の照射ポークでの分析値と一致している。また照射サバ切身中に同定されている主要な炭化水素は、抽出・照射されたサバ油に見出されるものと本質的に同じものである。
以上のように、照射によって食品に生ずる揮発性成分はとくに脂質区分の組成に基づいており、さらに線量、照射雰囲気や温度等の因子が関与している。したがって、モデル系や与えられた条件下で照射された食品で得られたデータから、組成のちがう食品に異なった処理条件下での照射効果を類推することが可能であると結論している。
食品の加熱処理は食品照射と同じ殺菌や貯蔵期間の延長を目的としており、また既に受け入れられている日常的処理法である点から、放射線処理と加熱処理とを比較することは食品照射を考察する上で有用である。図4はエチルステアリン酸について、180℃加熱および120kGy照射処理によって生ずる揮発性成分のガスクロ分析の比較結果を示したものである。このように実際に用いられるよりはるかに高い線量照射しても、通常の調理やフライ温度処理で生ずるよりも少ない分解物しか生成していない。すなわち、放射線処理によっておこる化学的、栄養的変化は、加熱処理より大きくなることはない(多くの場合小さい)ということを示している。
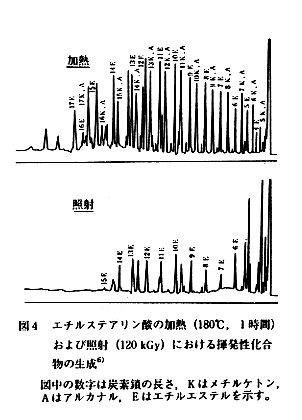 |
アミノ酸水溶液を無酸素下で照射すると、還元的脱アミノ反応と脱炭酸反応とがおこる。次式に示す還元的脱アミノ反応の結果、NH3とカルボン酸が生成する。
RCHNH2COOH+H→RCHCOOH+NH3
RCHCOOH+RCHNH2COOH→RCH2COOH+RCNH2COOH
脱炭酸反応は、次式のように元のアミノ酸より炭素原子が1個少ないアミンを形成する。
RCHNH2COOH→CO2+RCH2NH2
酸素が存在すると次式に示すように酸化的脱アミノ反応が起り、ケト酸を生ずる。
RCHNH2COOH+ ・OH→RCNH2COOH+H2O
RCNH2COOH+O2+H2O→NH3+RCOCOOH
表3には、アラニンおよび含硫アミノ酸であるシステインを水溶液中で照射したときの主な分解生成物とそのG値を示した。含硫アミノ酸はeaq・E(−)との反応性が高く(〜1×10・E(10)M・E(−1)sec・E(−1))、分解を受けやすい。また芳香族や複素環式アミノ酸も比較的放射線感受性が高い。
著者らは、ヒスチジン溶液の照射によって生成するヒスタミン量について検討を行っている*7)ので、ここではヒスチジンの例を示すことにする。ヒスチジンは照射によって図5に示す分解物を生ずることが知られている*8)。しかしヒスチジン溶液からのヒスタミンの生成は図6に示すように、N2中での照射により増大し、約30kGyで飽和値に達した。O2中では痕跡程度の生成しか認められなかったが、これはO2中では酸化的脱アミノ反応が優先するためと考えられる。N2中におけるヒスタミン生成曲線の低線量域での直線部分から、ヒスタミン生成のG値は0.077と求められた。またヒスタミンをN2中で照射した時の分解のG値は1.09であった。このようにヒスタミン生成のG値より分解のG値がはるかに大きいため、ヒスタミンの蓄積は最高でも4μg/ml以下に抑えられたものと考えられる。一方複合系である魚粉やフィッシュソルブル中にヒスタミンが照射によって蓄積されることはなかった。本研究は、飼料用魚粉中のヒスタミンがニワトリの筋胃潰瘍をひきおこす可能性が高いということで、その蓄積を検討したものである。しかし分解が著しいため蓄積量はモデル水溶液でもごくわずかであり、実際の複合系である魚粉の照射ではほとんど認められなかった。なお本題とは外れるが、その後ニワトリの筋胃潰瘍の原因物質はジゼロシンという新しい化合物であることが明らかにされている*9)。
| 生 成 物 |
G 値 |
|
| アラニン |
アラニン(分解) |
−5.0 |
| NH3 |
4.48 |
|
| アセトアルデヒド |
0.59 |
|
| ピルビン酸 |
1.92 |
|
| プロピオン酸 |
1.04 |
|
| エチルアミン |
0.17 |
|
| システイン |
システイン(分解) |
−9.3 |
| アラニン |
2.6 |
|
| シスチン |
3.4 |
|
| H2S |
2.5 |
|
| H2 |
1.1 |
|
| ※1:1.0M溶液、無酸素下 ※2:0.01M溶液、無酸素下 |
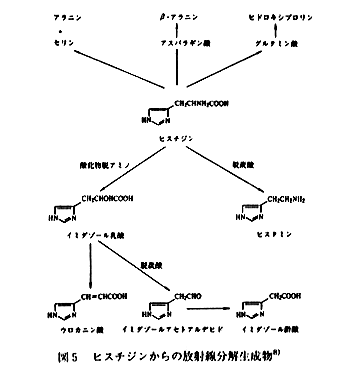 |
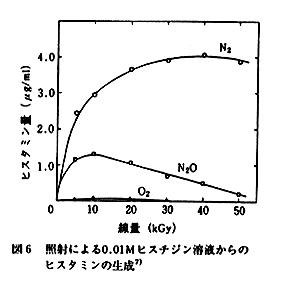 |
タンパク質の放射線分解は、構成アミノ酸やペプチド結合の反応に大部分帰することができる。関与する反応は、脱アミノ、脱炭酸、SHグループの酸化、S−S結合の分解、アミノ酸残基の修飾、ペプチド結合の分解や重合等である。
照射した肉のタンパク質部分から生成する物質が、アミノ酸、ポリペプチドあるいは純粋なタンパク質の照射により得られる物質とよく似た性質をもつことは既に明らかにされている。またタンパク質は、その種類や起源にかかわらず、放射線に対してほぼ同様の反応機構を示す。したがって、これを一般化することにより、個々のタンパク質食品をいちいちテストしなくても健全性を評価することが可能になる。
一方、タンパク質は照射によって容易にクロスリンクすることから、非通常型アミノ酸であるジアミノ酸生成の可能性が指摘されている*10)。著者らは非通常型アミノ酸の一つであるリジノアラニンについて検討を行った*11)。リジノアラニンは、タンパク質のアルカリ処理や加熱処理によって生ずる非通常型アミノ酸であり、ラットに対する毒性や有効性リジンの損失による栄養価の低下をもたらす物質である(その生成機構は図7に示す)。しかしタンパク質水溶液を照射した場合、タンパク質の種類(ウシ血清アルブミン、オボアルブミン、リゾチーム)、タンパク質濃度(0.2〜10%)、照射時のpH(7〜13)の変化に関係なく、用いた全ての条件下でリジノアラニンの生成は認められなかった。表4はリゾチームをpH8および13で照射したときのアミノ酸含量の変化を調べた結果であるが、リジノアラニンの生成は50kGyでも認められていない。一方、このpH13と同条件下で40℃、4時間の熱処理を行うと、タンパク質1モル当り2.8残基のリジノアラニンが生じている。したがって、リジノアラニン生成の問題点に関して、放射線殺菌処理法は加熱処理法よりもすぐれた方法であることは明かである。
| 線量(kGy) |
アミノ酸含量(残基/mol) |
||||
| LAL |
LYS |
HIS |
ARG |
||
| 非照射 |
ND* |
5.7 |
1.0 |
10.6 |
|
| pH 8.0 |
1 |
ND |
6.0 |
1.1 |
10.8 |
| 10 |
ND |
5.4 |
0.8 |
9.8 |
|
| 50 |
ND |
4.4 |
0.3 |
8.7 |
|
| pH13.0 |
1 |
ND |
5.6 |
1.2 |
10.6 |
| 10 |
ND |
5.3 |
1.1 |
9.9 |
|
| 50 |
ND |
4.2 |
1.0 |
6.5 |
|
| 加熱処理** |
2.8 |
3.1 |
1.2 |
10.9 |
|
| * 検出されず ** 40℃、4時間処理 |
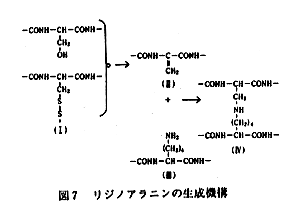 |
各食品構成成分の分析結果に基づいて、DIEHLら*4)はモデル食品(炭水化物、脂肪、タンパク質、各6.6%、水80%)を仮定し、5kGy照射したときの分解生成物量を計算した。
炭水化物に関しては、既に表1に示したグルコースを5kGy照射したときの生成量を基本にしている。炭水化物とOHラジカルの反応速度はタンパク質との反応速度の約1/10であり、炭水化物と反応するのは生成OHラジカルの1/10だけである。酸素存在下での主生成物グルクロン酸は9mg/100g、無酸素下での主生成物2−デオキシグルクロン酸は9.4mg/100gである。等量のタンパク質と炭水化物を含む場合、グルコースからの最大収量は1/10すなわち約0.9mg/100gとなる。実際の食品では、放射線のエネルギーは多糖類からグルコースへの分解反応や、脂質など他の成分にも消費されることから、分解生成物は0.5mg/100g以下である。
同様な考え方に基づいた計算により、タンパク質では個々のアミノ酸分解生成物は5mg/100g以下、脂肪では個々のアルカンや他の分解産物が0.05mg/100g以上の濃度で存在することはないと結論されている。
この他、微量食品成分に対する照射効果についても検討されている。タンパク質、炭水化物、脂質以外の食品成分は食品中の含量は低いにもかかわらず、放射線感受性が高い場合には分解生成物の収量が多い可能性がある。核酸はとくに放射線感受性の高い物質である。しかし一般に食品中の含量は100mg/100g以下であり、5kGyでは分解生成分が0.1mg/100g以上となることはない。またビタミンも比較的放射線感受性が高いが、通常の食品中での分解生成物は1mg/100g以下であろうと考えられている。
以上の結果を要約すると、モデル食品100gを5kGy照射したときの分解生成物は、炭水化物で0.5mg以下、脂質で0.05mg以下、タンパク質で5mg以下であり、ビタミン等の微量成分では1mg以下である。このモデル食品系での考え方は、乾燥や凍結食品あるいは組成の著しく異なる食品に対しても適用できるが、照射雰囲気や温度、組織や細胞中での不均一性に関してはさらに考慮する必要がある。しかし実際の食品系で得られた分析結果では、高水分含量のものでも5kGyで1mg/100g以下の放射線分解生成物しか生じておらず、このレベルに近いのは炭酸ガスだけである。毒性に関与する可能性のある化合物はこのレベルの1/10か1/100にすぎないと結論されている。
| 化 合 物 |
G 値 |
5kGyでの収量 (mg/100g) |
||
| 無酸素下 |
酸素存在下 |
無酸素下 |
酸素存在下 |
|
| Glucose(decomposition) |
−3.5 |
−3.5 |
−32.5 |
−32.5 |
| Gluconic acid |
0.35 |
0.4 |
3.5 |
4.1 |
| Glucuronic acid |
0.9 |
− |
9.0 |
− |
| Glucosone |
− |
0.4 |
− |
4.1 |
| Erythrose |
0.25 |
− |
1.6 |
− |
| Deoxycarbonyls and other deoxy compounds |
− |
0.3 |
− |
2.7 |
| 2−Deoxygluconic acid |
− |
1.0 |
− |
9.4 |
| C2−fragments* |
0.85 |
0.8 |
2.6 |
2.4 |
| C3−fragments* |
0.80 |
0.8 |
3.7 |
3.7 |
| *C2、C3フラグメントの生成は疑わしい。 |
1980年の合同専門家委員会の結論として、「毒物学的、栄養学的、微生物学的、および技術的な観点から総合的に判断して、平均線量10kGy以下でいかなる食品を照射しても全く問題はない」との勧告が出された。また1983年にはFAO/WHOの Codex Alimentarius Commission(国際食品規格委員会)は上記結論に基づき、照射食品の国際的な流通を促進するため照射食品の国際規格を設定した。このような国際機関の積極的な動きに応じて、最近各国で食品照射の実用化が活発になってきている。とくに注目されるのは米国の動向であり、1983年香辛料と乾燥野菜、1985年に乾燥酸素剤、旋毛虫の防除を目的とした豚肉の照射を許可し、1986年には生鮮食品の殺虫(1kGy以下)許可と香辛料の殺菌線量の30kGyへの引き上げを行った。
1986年4月18日付けのFDA最終規則*12)には、放射線分解生成物についての考え方も示されている。FDAは放射線分解生成物は照射食品に特有なものであろうと考え、非照射食品に存在することが知られていない物質という意味でURP(ユニークな放射線分解生成物)という用語を用いている。しかしURPとして特定された物質は、通常の食品中の成分であるがルーチン分析では微量すぎて検出されていないだけという可能性が強い。1kGyの照射で生ずる放射線分解生成物は約30ppmであり、その90%は食品の天然の成分である。残り10%(3ppm)がURPということになるが、個々のURPの濃度は1ppm以下である。したがって、1kGy以下の線量で照射した食品中の個々のURP濃度は極めて低く、どのURPも他の食品成分と毒物学的に似ていることから、人間が食べても安全であると結論している。また香辛料のように人間の食品にほんの少し(0.01%以下)しか使用されないものに関しては、50kGy照射しても50ppb以下の分解物しか生成せず、毒性試験なしに使用してもよいと勧告している。
FDAの提案に対して寄せられた5000以上のコメントの中に、フリーラジカル、過酸化物、H2O2等の生成を問題視するものが含まれていた。しかしこれらの生成物は収率も低く不安定であることから、安全に関して何の心配もないとしている。また放射線照射した糖水溶液が生体外で毒性になることを認めた上で、照射食品の毒性を予想したり推察するのには適さないモデルであると明確な結論を下している。
以上のように、FDAの最終規則では、これまでに得られた放射線化学的な知識が大きな役割を果たすに至っている。
1980年のFAO/IAEA/WHOの合同専門家委員会で「10kGy以下の照射に対して、今後新たな毒性データは要求しない」との結論が出されたが、「10kGy以上の大線量照射を行った食品の健全性についてはデータが不十分である」として結論を保留している。したがって、今後は高線量照射した食品について、放射線化学的、毒物学的研究を続行していくことが必要である。放射線処理に特有なURPが生成するかどうかといった検討は、高線量照射でとくに重要となるであろう。また分析技術の向上に伴い、これまで知られてなかった毒性物質(例えばタンパク質の項で述べたリジノアラニンやジゼロシン等)が化学処理や加熱処理した食品から新たに見出されるようになってきたが、これらの物質が放射線処理法でも生成するかどうか、また生成する場合にはその収率等を明らかにしていくことも必要となる。このように加熱処理等の従来から認められている処理法と比較検討することは、消費者に対する健全性証明の一助ともなり得るであろう。
完全殺菌に必要な高線量の照射に関して十分なデータが蓄積され、主食品の完全殺菌が認められるようになれば、放射線処理の利用分野のより一層の拡大が期待できる。
1)Report of the Joint FAO/IAEA/WHO Expert committee:WHO Technical Report Series No.604(1977).No.659(1981).和訳:食品照射、16,61(1981). 2)I.G.Draganic and Z.D.Draganic:”The Radiation Chemistry of Water” Academic Press,New York,p.123(1971).
3)川岸舜郎・並木満夫:食品成分の相互作用(並木、松下編、講談社)、P.16(1980).
4)J.F.Diehl and H.Scherg:Int.J.Appl.Radiat.Isotopes,26,499(1975).
5)R.A.Basson:Atomic Energy Board Report PER−15(1977).
6)W.W.Nawar:Food Reviews International,2,45(1986),”Radiation Chemistry of Majar Food Components,”ed,by P.S.Elias and A.J.Cohen 7)T.Kume el al.:Agric.Biol,Chem.,47,1973(1983).
8)J.Liebster and J.Kopoldova,”Advances in Radiation Biology,”Vol.1,Academic Press,New York,p.215(1964).
9)野口:化学と生物、23、77(1985).
10)W.M.Garrison:LBL−8928(1981).
11)T.Kume and M.Takehisa:J.Agric.Food Chem.,32,656(1984).
12)FDA:Federal Register,51(75),13376(1986), 和訳:原子力資料、No.189(1986)。
|
|