Table 1 The number of microorganisms adhering to Japanese tea
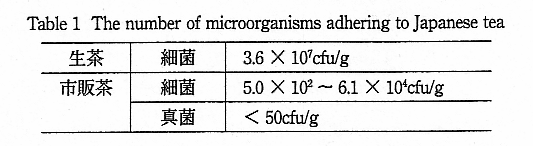 |
実験方法
1. 試料
2. 電子線照射処理
3. 微生物試験
4. 電子線感受性
結果および考察
1. 日本茶付着微生物数
2. 製造工程における菌数変化
3. 付着微生物の経時変化
4. 抹茶付着微生物数
5. 熱湯処理
6. 付着微生物の EB 感受性
7. 日本茶付着微生物種
嗜好飲料として親しまれている日本茶は、近年飲用によるさまざまな薬効が解明されることに伴って、健康飲料としての需要も増えてきている。日本茶は一般的製造工程において、茶葉中の酵素活性停止、細胞からの含有成分抽出および芳香促進を目的とした加熱処理が行われる。したがって、この加熱処理と飲用時の熱湯抽出による微生物殺滅効果が期待されることから、これまで付着微生物についての考慮はあまり払われていない。しかし、抹茶のように加工食品の添加物として利用する場合、残存耐熱性微生物の増殖による腐敗や食中毒の危険性が危ぶまれる。現在、工業的に利用し得る微生物殺滅法のうち、放射線法は室温下で非破壊的連続処理が可能であり、適切な処理条件を設定することによって確実な殺滅効果が期待できる。本研究では、日本茶原料に付着する微生物の同定と付着数、日本茶製造工程における菌数変化、ならびに電子線 (以下、EB) 照射法による微生物殺滅効果を調べ報告する。
試料として、日本茶製造工程からの採取試料 12 種類および市販日本茶試料 30 種類の計 42 種類の日本茶を用いた。
日本電子照射サービス㈱関西センターの 4.8MeV の EB を用い、線量は 0.5 〜 40kGy とした。上記試料のうち、煎茶 4 種類、玉露 2 種類、抹茶 2 種類を照射試料とした。
生菌数の測定には、第 14 改正日本薬局方1) 収載の「生薬の微生物限度試験法」に基づき、カンテン平板混釈法を採用した。試料量は 1.0g とし、分離液には、リン酸緩衝液、ペプトン食塩緩衝液、生理食塩水のそれぞれ界面活性剤添加、不添加の 6 種類を、分離法には、超音波処理、振とう処理を比較検討した結果、0.1% Tween80 添加リン酸緩衝液で、超音波で処理した場合にコロニーがより多く、また再現性よく計数されたのでこの分離条件とした。培地には、カテキンなどの抗菌成分の影響をさけるため界面活性剤が添加されているものを用いた。日本茶付着微生物の同定には「バイオバーデン試験法及び環境微生物試験法2)」に基づき属決定を行い、さらに Bacillus 属については芽胞形成菌の簡易同定法3) に基づいて菌種を決定した。
線量に対する生残曲線から D10 値を求め、次式に代入して殺菌線量 SD を求めた。
SD(kGy) = D10×log(N0/NSAL)
ここで、N0 ; 汚染生菌数、NSAL ; 菌数目標値である。
Table 1 に示すように、採取された生の状態の茶葉 (以下、生茶) には 107 〜 108 cfu/g の細菌が付着していたが、市販茶では 102 〜 104 cfu/g であり、真菌においては、ほとんどの試料で 50cfu/g 以下であった。
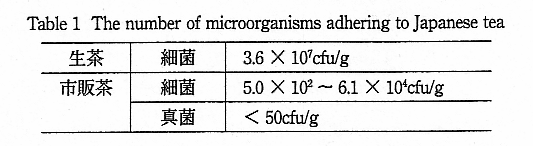 |
製造工程毎の茶葉の微生物数を比べると、Fig. 1 に示すように、生茶には 107 〜 108 cfu/g の細菌が付着しているが、蒸熱処理によって生茶の主要付着微生物である栄養型細菌がまず死滅し、細菌数はいったん約 2 桁減少する。今回の調査では、葉打ち工程で再び 107 cfu/g レベルにまで増加したが、その後の 4 段階の加熱揉み工程で細菌数は減少し、最終の乾燥工程では煎茶では 103 〜 104 cfu/g になる。玉露、抹茶の場合も同様に 103 〜 104 cfu/g にまで減少する。
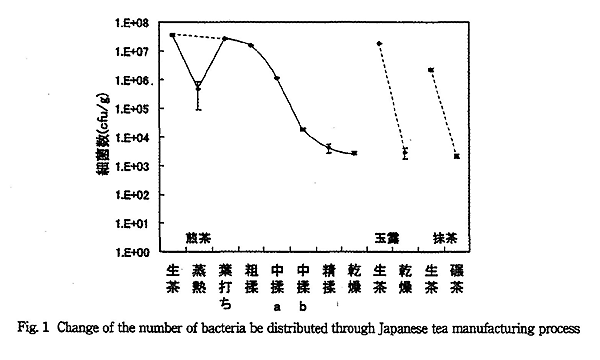 |
日本茶は前項に示した工程を終えた後、袋詰めされ出荷されるが、袋詰め保管中にもカテキンなどの抗菌成分の作用によってさらに微生物数は減少する。Fig. 2 は抗菌成分による減少効果を確認するため、いくつかの試料について袋詰め状態での付着微生物数を経時的に測定した例である。試料によってかなりの差があるが、約半年経過で微生物数は 1/3 〜 1/10 にまで減少するので、保管期間を考慮すれば食品衛生法4) での添加物の条件であるグラムあたり胞子数 103 個以下の条件を満足する。
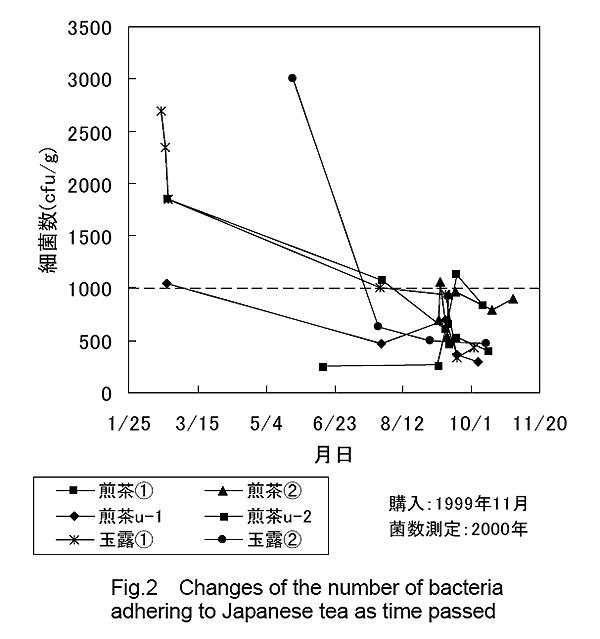 |
春に入手した抹茶の付着菌数の例を Fig. 3 に示す。細菌数は 102 〜 103 cfu/g であったが、価格的に上級から下級になる試料ほど付着微生物が増加する傾向がある。これは、下級の製品には様々な茶葉をブレンドして製造されていること、また、抗菌成分としてのカテキン含有量の相違などが考えられる。
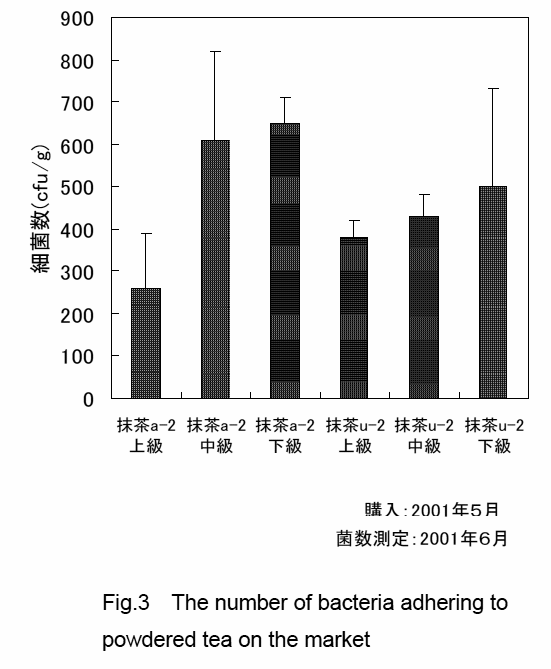 |
煎茶は、原則として湯で煎出し飲用される。この際、加熱による付着微生物の殺滅が期待される。茶湯調製の条件で処理した場合の菌数変化を Fig. 4 に示す。熱湯処理手順としては、試料 1.0g を分離液に無菌的に入れ軽く混和した後 80℃ の温浴中に 15 分間浸し、その後 10 分間超音波処理とした。その結果、予想に反して、熱湯処理後、試料によって多少異なるが生残微生物数はそれほど減少しない。つまり、製品としての日本茶に付着している微生物はほとんど耐熱性の芽胞形成菌であり、日本茶を飲用する前の熱湯浸出では微生物数の減少は期待出来ないことが確かめられた。
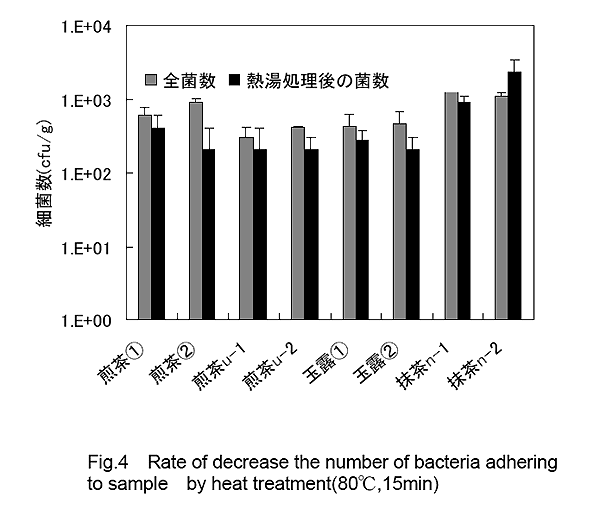 |
Fig. 5 に電子線照射処理における付着微生物の生残曲線を示す。初期菌数が小さいためきれいな生残曲線ではないが、D10 値を求めると 1.4 〜 3.8kGy となり、ほとんどの試料で約 2kGy の EB 照射により菌数は 102 cfu/g 以下となる。試料としてのお茶の種類によって指数関数型およびシグモイド型の抵抗性の強いものも見られる。殺菌保証レベルを NSAL = 102 cfu/g とした場合、殺菌線量 SD 値は 0.9 〜 2.5kGy である。
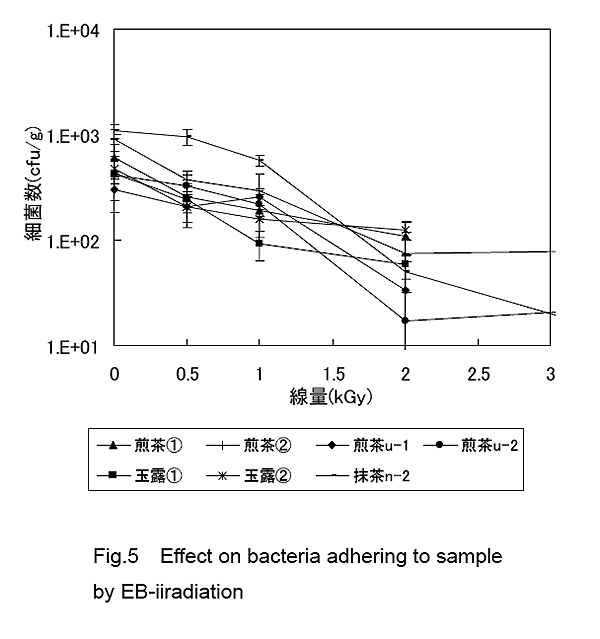 |
生茶に付着する微生物の大半は芽胞を持たない栄養型細菌であるが、まず蒸熱工程でこれらの栄養型細菌は死滅し、それ以後、熱抵抗性の強い芽胞形成菌である Bacillus 属や Micrococcus 属および Staphylococcus 属などが検出された。Staphylococcus 属は、黄色ブドウ球菌 (Staphylococcus aurus)、表皮ブドウ球菌 (Staphylococcus epidermidis) および腐生ブドウ球菌 (Staphylococcus saprophyticus) の 3 菌種があり、このうち黄色ブドウ球菌のみが病原性を有す5)。今回はこれらの菌種ごとの詳しい同定は出来なかったので、病原性を持つ黄色ブドウ球菌か否かは不明である。また、一部の試料から毒素型食中毒を引き起こす B. cereus6) が検出されたが、B. cereus の場合の発病限界は約 106 個と報告されており5)、総細菌数のレベルから判断してこれによって発病する恐れは少ないと思われる。EB 照射試料の付着微生物種は主に B. subtilis などの芽胞形成菌であり、その他 B. firmus、B. pumilus、B. polimixa などが検出された。B. subtilis は枯草菌とも呼ばれ、空気中に浮遊塵とともに存在する土壌由来菌で病原性はないと言われている7)。結果的に煎茶、玉露、抹茶の試料による付着微生物に違いはあまりなかった。
日本茶は、成分としてカテキンを含んでおり、その抗菌作用によって保存中に茶葉付着微生物数は減少する。そのため、普段飲用するには茶葉付着微生物による汚染はそれほど問題にはならない。しかし、抹茶など、加工食品に添加して用いる日本茶は、茶葉に残存する微生物数増加の可能性が懸念されるので、何らかの殺滅処理が必要であると考えられる。今回用いた EB 照射法は、0.9 〜 2.5kGy 程度の EB 照射で茶葉に付着する微生物数を 102 cfu/g まで減少させることが可能であり、EB の特性上、製造工程にも組み込むことができるため、日本茶を殺菌するにはよい方法ではないかと考えられる。
1) 日本薬局方解説書編集委員会 ; 「第 14 改正日本薬局方解説書」, 廣川書店, 東京 (1996)
2) 佐々木次雄 ; 「バイオバーデン試験法及び環境微生物試験法」, 日本規格協会, 東京 (1996)
3) 越川富比古 ; 防菌防黴, 24, 657 (1996)
4) 厚生省生活衛生局 ; 食品衛生関係法規集, 中央法規, 東京 (1990)
5) 坂崎利一 ; 「食中毒」, 中央法規, 東京 (1988)
6) 糸川嘉則 ; 「食品、食品添加物」, 地人書館, 東京 (1992)
7) R. Y. スタニエ ; 「微生物学 (下)」, 培風館, 東京 (1984)
(2002 年 6 月 10 日受理)
|
|