図-1 59kGy照射した凍結鶏肉の雌ラットによる体重増曲線
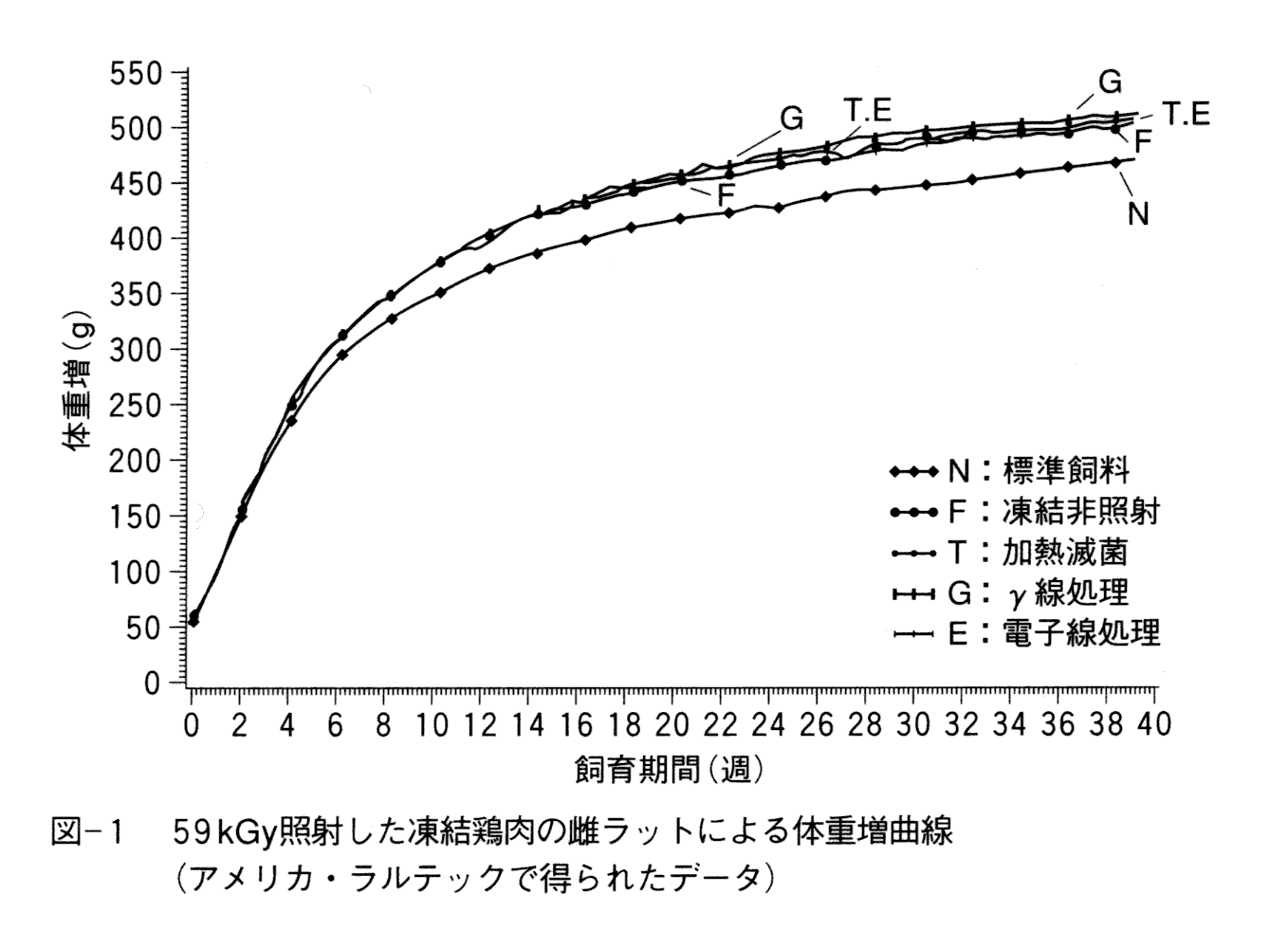 |
食品照射における健全性評価とは食品としての安全性と栄養適性、生残微生物の安全性を評価することである。生残微生物の安全性については先に述べたので省略する。さて、食品照射研究初期の1970年以前には、放射線の食品成分への影響は明らかになっていなかったため、食品添加物と同じ100倍量の照射食品を動物に与える試験が実施された。この考えによると、必要線量の10倍以上を照射して、過剰の照射食品を動物に投与する必要がある。たとえば、米国陸軍が行った照射ベーコンの動物試験では飼料組成の約50%が過剰照射されたベーコンで占められ、ビタミン等の栄養バランスも無視されたものであり、それが原因しての動物の異常が観察された。実験室で使われるラット(ドブネズミ種)やマウス(ハツカネズミ種)などは個体間の遺伝差が少なく、近親交配され、無菌環境下で飼育されており、環境の変化に弱いものが多い。しかし、照射食品では通常の雑菌が存在する環境下で飼育するため汚染微生物による病気が原因した誤差が生じることもあり得る。これに対して、放射線滅菌した実験動物用飼料での動物試験ではデータの誤差も少なく生育も加熱滅菌より良好な傾向がある。一方、実際の食品では照射する食品の種類は膨大であり、香辛料のように動物試験が行われにくいものもある。このため、健全性の評価には国際的な協力が必要であった。
照射食品の健全性評価を国際的に行おうとする動きは1961年のFAO(国連食糧農業機関)、IAEA(国際原子力機関)、WHO(世界保健機関)による合同専門家委員会のころから始まった。この会議では照射食品の健全性試験は食品添加物と同じ基準で行うことが合意された。この当時は放射線による分解生成物がどのような物質か解っていなかったため食品添加物と同じと見なされた。そして、1971年には健全性評価のための国際プロジェクトがわが国や米国、旧西ドイツ、フランス、英国など24カ国が参加して開始された。この一連の研究によって、放射線分解生成物も明らかになってきたため、1967年のFAO・IAEA・WHO合同専門家委員会では、「食品の放射線処理は加熱や冷凍と同じ物理的処理であり、食品添加物としての扱いは妥当でない」とする見解を示した。1977年にはFAO・IAEAの飼料の放射線殺菌に関する専門家会議が開催され、50kGyまでの照射は飼料としての安全性に問題ないと勧告した。さらに、1980年には国際プロジェクトの成果を基にFAO・IAEA・WHOの合同専門家委員会が開催され、「10kGy以下の総平均線量でいかなる食品を照射しても、毒性学的、栄養学的および微生物学的に全く問題のないこと、ならびに、今後はこの線量以下で照射した個々の食品の健全性試験は不要である」という結論を出した。1997年には米国等で行われた10kGy以上照射された肉類の動物試験の成果や放射線分解生成物の研究結果、変異原性試験の成果を基にWHOは10kGyの上限を撤廃するように勧告した。しかし、2003年に欧州連合は10kGy以上の照射食品の健全性は一部の食品類が調べられていないという理由によって基本的には10kGy以下の照射食品についての安全性を認めた。
ここでは、誘導放射能の評価、動物試験による安全性評価、変異原性試験、栄養学的評価、放射線分解生成物の概略について述べることにする。
米国では1960年代に陸軍のNatick研究所で電子線による誘導放射能生成についての研究が行われ、11MeV以下で照射した牛肉等からは誘導放射能が検出できないことを明らかにした。1970年代には英国、フランス等でも誘導放射能の評価が行われ、電子線の10〜11MeV、X線の5〜10MeVでも自然放射能に比べ数%しか誘導放射能が生成しないことを明らかにした。わが国でも、(社)日本アイソトープ協会の食品照射研究委員会の研究により、X線は5MeV、電子線は10MeVの上限までは誘導放射能の生成は無視できることを明らかにした。
すなわち、X線も電子線もエネルギーが極端に高いと原子核が励起されて中性子が放出され、誘導放射能生成の原因になる。X線のエネルギーが10MeV以下で中性子を放出する元素は2H、13C、17O、18Oであり、ことに2Hは2.22MeV、17Oは4.14MeV、13Cは4.95MeVで中性子を放出する。しかし、これら2H、13C、17Oなどの元素の中性子発生比率は著しく低く、変換される元素も放射性元素ではない。放出される中性子が熱中性子となるまで減速されて放射化する食品中の放射性元素は38Clと24Naが比較的多く、42Kや32Pなども極微量に生成する。しかし、40Kや14Cなどの食品中の自然放射能が1kgあたり40〜600ベクレルに対し5MeVのX線や10MeVの電子線で誘導される放射能は0.2または0.3ベクレル以下と報告されている。しかも、比較的生成量が多い24Na等でも半減期は15時間以下であり、極微量に生成される32Pでも14.3日である。X線も電子線も11MeV以上になると放射化される元素数が増加するため、誘導放射能生成量は急激に増加する。このため、電子線は10MeV、X線は5MeV以下のエネルギーでの利用が妥当であろう。しかし、照射施設に用いるコンベア等に用いる金属材料によっては放射化されやすいものがあるため、7.5MeV以上の電子線の利用では放射化されにくい材料を用いるべきであろう。
照射食品の安全性評価の研究は先ず米国陸軍のNatick研究所で1954年から1964年にかけて種々の動物を用いた長期飼育試験や世代試験などが行われた。試験品目は22種であり、牛肉や鶏肉、魚介類などは27.9kGyまたは55.8kGy照射された。また、馬鈴薯やオレンジ、小麦粉などは1kGy以下照射された。これらの試験では主に純系のラットやマウスを用い、サルやビーグル犬も用いられた。また、米軍の若いボランテイア10〜15名による15日間の食事試験も行われ、高線量の照射食品(20〜40kGy)が提供された。これら一連の試験はおおむね良好な結果が得られたが、特定食品の過剰摂取や栄養バランスを検討していない研究もあった。これらの成果を基に1964年には照射ベーコンがFDA(米国食品医薬品局)から許可されたが、1968年には安全性のデータに不備があるとして、FDAから許可が取り消された。これは、FDAの安全性評価に対する考えが厳しくなったことが関係しており、確実な安全性が証明されることが求められた。その後、1980年にFDAは照射食品の安全性評価のための指針を作成し、放射線分解生成物のデータを基に「1kGy以下の線量では無条件で許可、1kGy以上では食事中に占める照射食品の比率が0.01%以下なら無条件で許可、0.01%以上では数種の毒性試験を行う」という方針を示した。
照射食品の動物を使った安全性評価の本格的な研究は1971年の国際プロジェクトからであった。本プロジェクトには米国、フランス、旧西ドイツ、オランダ、英国、日本など24カ国が参加した。そして、照射食品の動物試験の成果と放射線分解生成物の研究を基にFAO・IAEA・WHO合同専門家委員会は1980年に10kGy以下の照射食品の健全性に問題がないと宣言した。一方、米国FDAは1982年までの入手可能な毒性試験400件以上の結果について評価を行った。この評価では線量が記載してないとか、試験動物数が少なすぎるとか、非照射の対象がなかった等の不適切な試験結果は除外された。そして、適切な試験結果からの評価に基づき、90日間の亜慢性毒性試験、3世代飼育の繁殖試験、300〜999日間の慢性毒性試験(長期飼育試験)のいずれでも3〜93kGy照射した食品での体重増、臓器重量、血液検査、尿検査、繁殖性、催奇形性等での異常は認められなかったと結論している。
一方、1984年には米国のラルテック社で行われた59kGy照射した冷凍鶏肉を用いての動物を使った毒性試験の結果がFDAより報告され、健全性に問題のないことが明らかにされた。本研究では照射鶏肉を35%含む飼料をラット、マウス、ハムスター、ウサギ、ビーグル犬に与える慢性毒性試験(280〜999日)、優性致死試験、世代試験等が行われた。例えば、ラットの飼育試験では各群とも雌雄115〜175匹の動物が用いられた。そして、図-1に示すように40週の飼育期間中の体重増はガンマ線、電子線、加熱蒸気滅菌、非照射で差が全く認められず、他の試験項目でも照射による悪影響は認められなかった。なお、国際的な動物飼育試験の標準はラットやマウスでは雌雄30〜50匹であり、照射食品では個体差によるデータのばらつきが見られることが多い。しかし、ラルテック社のマウスの結果では照射鶏肉群で睾丸腫瘍が増加するという結果が得られたが、FDAによる再評価の結果では非照射群でも腫瘍が認められ、照射による発癌性の証拠はないと結論された。その他、オランダで行われた37または74kGy照射した豚肉製ハムの繁殖試験や3または6kGy照射した鶏肉の慢性毒性試験でも動物に対する異常は認められなかったと報告されている。ハンガリーで行われた15kGy照射した混合香辛料等を飼料中に25%加え、ラットを14日間飼育した結果でも催奇形性や体重増での照射の影響は認められなかった(表-1)。
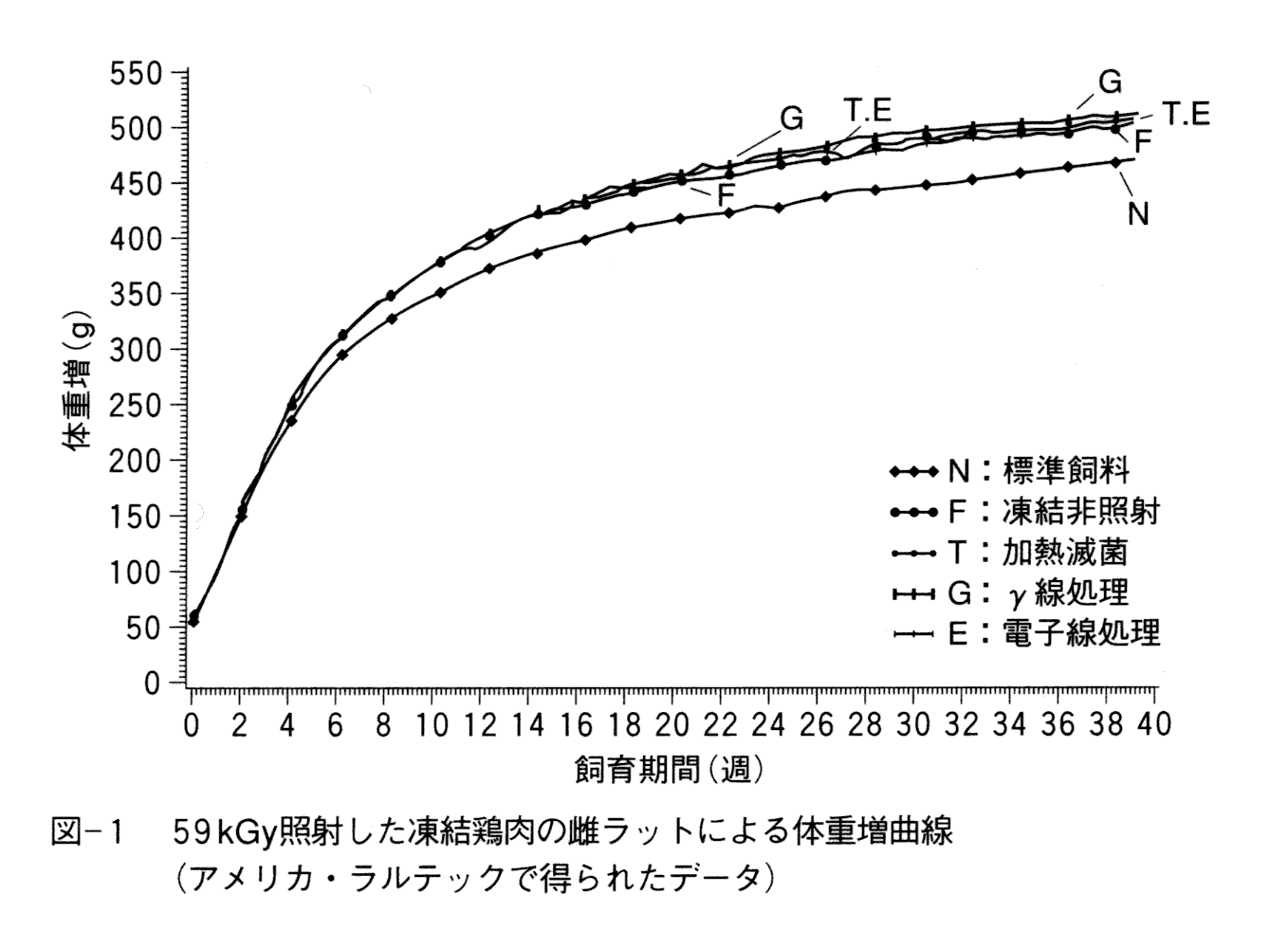 |
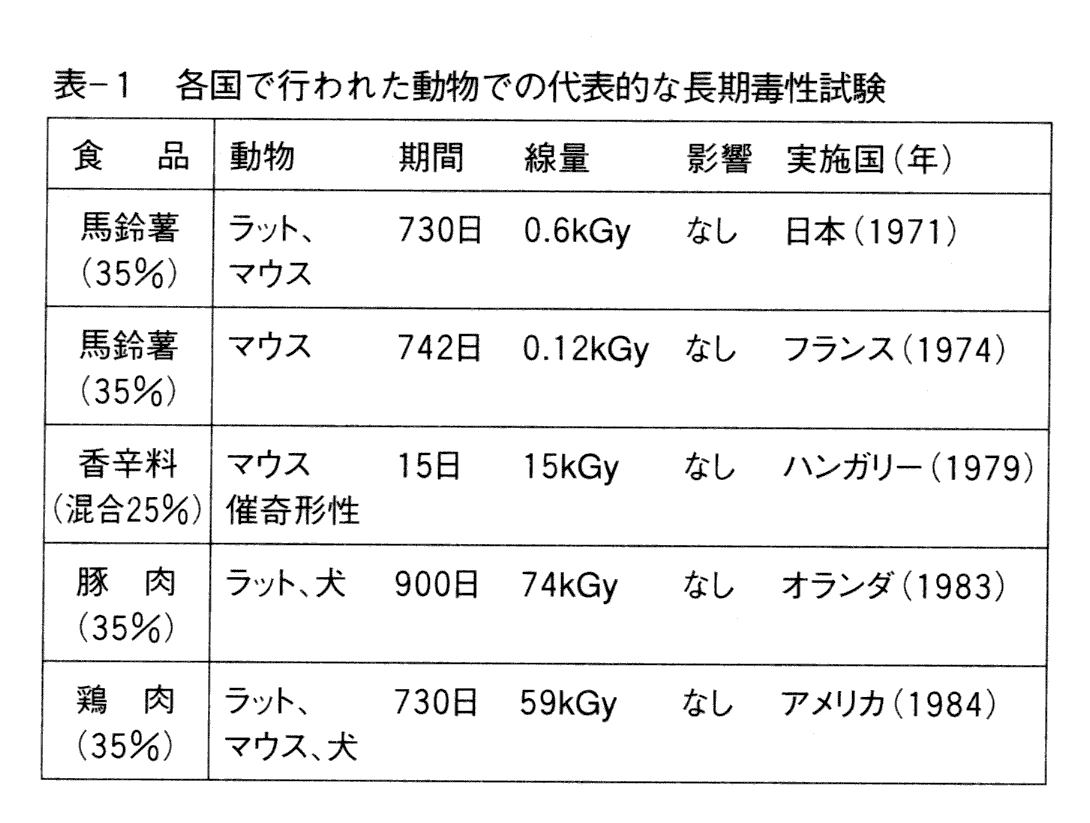 |
わが国では照射食品の動物を使った毒性評価は1967〜1983年の原子力特定総合研究で行われた。馬鈴薯やタマネギの研究では薬剤と同じ100倍量の考えで「食品の投与量x吸収線量」により、表-2に示すような過剰投与による飼育試験が行われた。その結果、タマネギのように飼料中に乾燥重量で25%の過剰投与することによって非照射および照射試験区の動物とも同じように血液等に異常が生じた。すなわち、人換算では1日に平均的に摂取する333倍または450倍も給餌したことになる。このため、タマネギでは2または4%添加で試験をやりなおさざるを得なかった。なお、7品目の各試験に用いられた動物数は国際的な標準に従ったため、個体差によるデータのばらつき等の問題点があった。このような問題点も含めて試験結果を評価して、特定総合研究で取り上げられた照射7品目およびガンマ線を1kGy照射したグレープフルーツではマウス、ラット、サルによる慢性毒性試験および繁殖試験(3世代試験;催奇形性も含む)で動物に対する照射による異常は認められなかったと結論した。
一方、わが国や英国、ドイツ、オーストリア、ハンガリーなどの先進国では実験用無菌動物などの飼料の放射線滅菌が25〜50kGyで実用化となって30〜40年たっているが、蒸気滅菌処理より良好な飼養効果を示し照射による異常は認められていない。この場合、加熱蒸気によって滅菌された飼料でラットの体重増が抑制されたのはペレットが硬化したことも関係しているが、ビタミンや必須アミノ酸等の分解も関係しているようである。
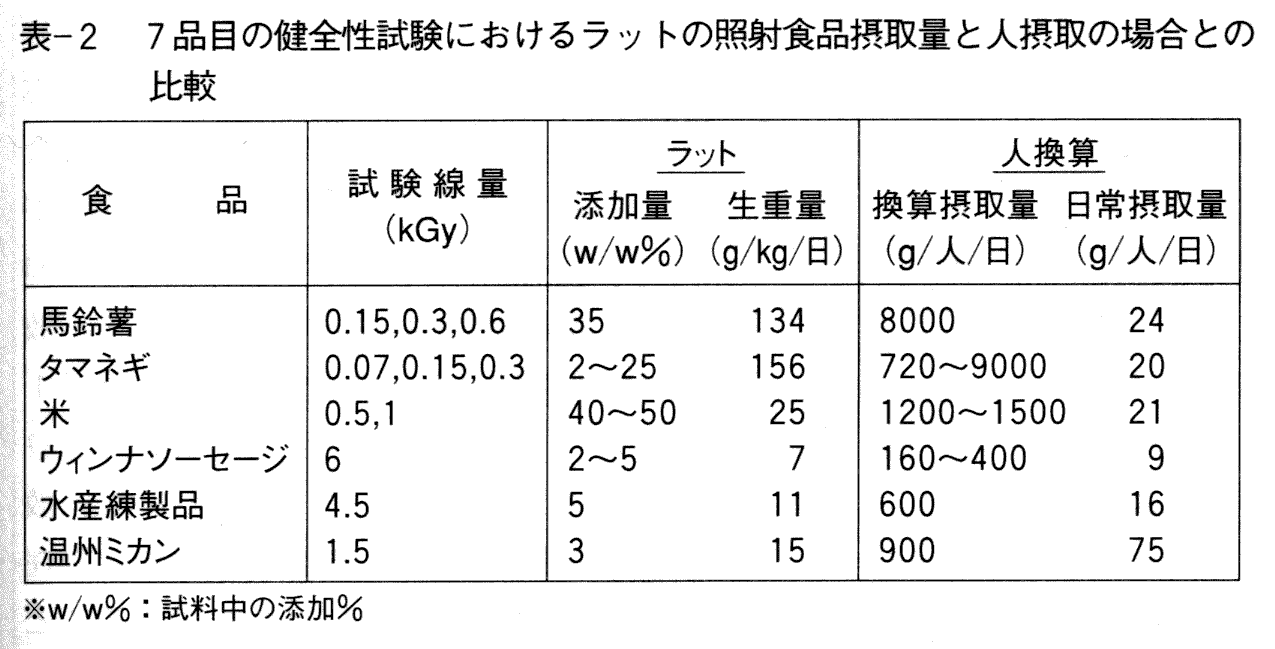 |
変異原性試験とは化学物質などがDNAに作用することによって傷害を与え、その結果としてDNA損傷や突然変異、染色体異常などを引き起こすかどうかを検査する試験法であり、遺伝毒性試験ともいう。動物などの場合、DNAや染色体への傷害は癌誘発の原因になることもある。変異原性試験は食品添加物の安全性評価法として1970年ころから開発されており、動物を使った毒性評価の代替法に近い試験法とも見なされている。照射食品の安全性評価に変異原性試験が導入されたのは1970年代からであり、わが国でも原子力特定総合研究の途中から追加試験が実施された。
照射食品の変異原性試験で問題になるのは放射線分解生成物である。インドの栄養研究所は0.75kGy照射した小麦を栄養失調児または実験動物に与えると優性致死変異(流産、胎児死亡)または血液中のポリプロイド(染色体異常の一種)が増加すると報告した。しかし、わが国を含む約20件の研究成果では優性致死またはポリプロイド増加を示す結果は得られず、インド政府の調査でも栄養研究所の結果には観察方法そのものに問題があると結論している。一方、ブドウ糖や蔗糖を照射すると変異原性物質が生成するという報告があったが、わが国などの研究では生体内試験で変異原性を示さないことが明らかにされた。
わが国では原子力特定総合研究により照射された7品目およびグレープフルーツの変異原性試験が実施されたが、遺伝子突然変異、染色体異常、小核によるポリプロイド誘発、優性致死試験のいずれでも変異原性物質が生成しないことを明らかにしている。
照射食品の栄養評価は食品中の栄養成分分析、動物の成長および生理機能に与える影響等の試験を基に総合的に評価されてきた。食品の主要栄養成分である澱粉などの多糖類は低線量でも分子鎖が切断されやすいが、エネルギー源としての栄養価は高線量でも低下しない。タンパク質は放射線に安定であり、10kGy以上の高線量でもアミノ酸組成はほとんど変化しない。また、酵素活性や免疫化学的性質もほとんど低下しない。脂質は放射線で酸化劣化が起こりやすいが、酸素濃度を低減すれば、高線量でも酸化劣化は無視できる。例えば、鶏肉を−25℃で59kGy照射しても高分子不飽和脂肪酸の減少は認められていない。また、ラットの飼料を70kGyまで照射したり、豆を210kGy照射しても栄養学的な異常は認められていない。
栄養成分のうち、放射線で最も分解が起こりやすいのはビタミン類である。しかし、表-3に示すように凍結下で59kGy照射された鶏肉中のビタミン類の低減は蒸気滅菌と大差がないという結果が得られている。
世界各国のこれまでの研究を総括すると、1)1kGy以下の低線量では栄養成分の低減はほとんど問題にならない、2)1〜10kGyでも脱酸素下での照射では栄養成分の低減はほとんど問題にならない、3)10〜75kGyの照射では脱酸素と凍結下または乾燥下で照射するため栄養成分の低減は少ない、4)ビタミン類については、水溶性ビタミンではビタミンB1やビタミンCが放射線で分解されやすく、脂溶性ビタミンは水溶性ビタミンに比べ放射線で分解されにくいがビタミンEやビタミンA、ビタミンKが分解されやすい。しかし、これらのビタミン類の分解は加熱と大差がないか、加熱より安定である。なお、必須アミノ酸類も加熱蒸気滅菌では11〜27%分解するが、放射線では分解はほとんど起こらない。照射食品は加熱調理して摂取する場合が多いが、照射と加熱による栄養成分の分解促進効果は認められていない。
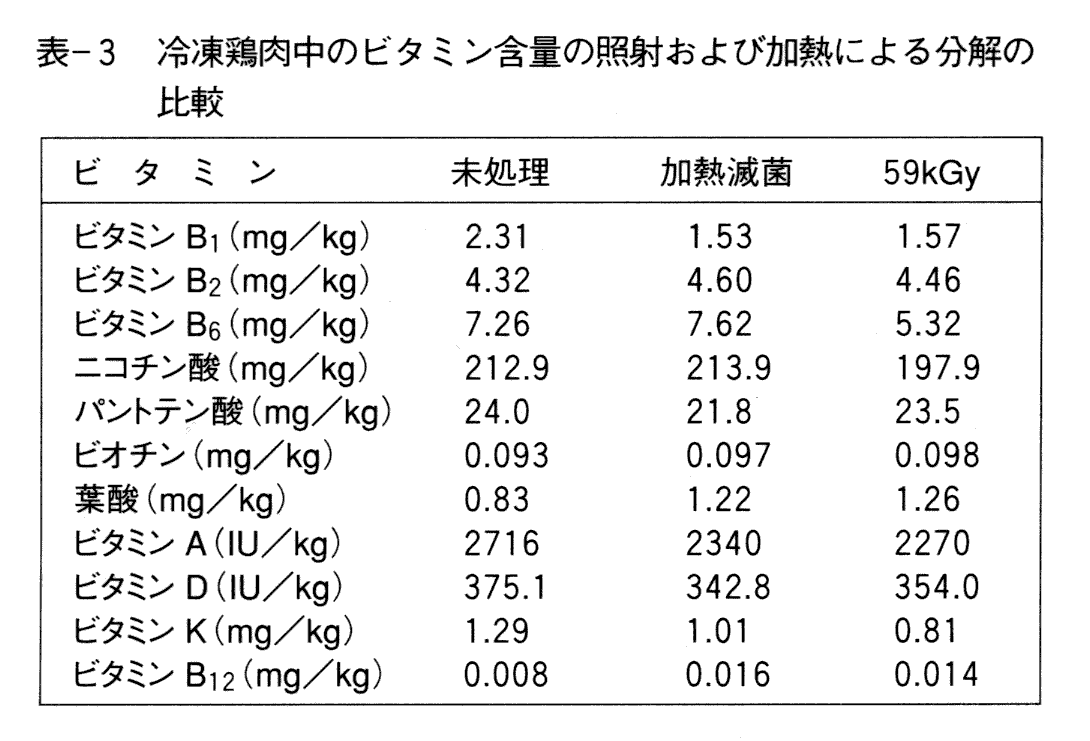 |
放射線による食品成分の分解生成物の分析による安全性評価の研究は1970年頃から米国や旧西ドイツ、英国などで開始された。しかし、実用的な照射条件での食品中の放射線分解生成物は極微量である。このため、実用線量の10倍以上照射したり、高酸素下とか水溶液中など放射線分解が起こりやすい条件で研究が行われた。放射線分解生成物の量とか種類は食品の化学組成によって決まり、生成量は線量に依存して直線的に増加する傾向にある。また、同じような食品成分では照射によって同じような化学反応を起こすことがわかっている。例えば、10kGy以上照射されたハムや豚肉、牛肉、鶏肉のESRスペクトルは似ており、放射線分解生成物も似ている。放射線分解生成物の全体の生成量は1kGyの照射では最大で1kg当たり30mgと計算されている。そして、放射線分解生成物の多くは自然界に存在しているか加熱処理でも生成することがわかっている。
米国FDAは1980年に照射食品から得られた63種の揮発成分のうち10%が放射線特有の分解生成物であるとした。しかし、これらの化合物について再評価したところ食品脂質からの3種類の揮発性炭化水素化合物のみが非照射から分離されないことがわかった。しかし、これらの化合物は非照射食品中に存在する類似化合物より炭素数が1個少ない分子量であり、WHO専門家グループの見解では非照射食品中にも見出されるという。また、非揮発性の脂質とタンパク質ラジカルの結合によって生成する放射線特有の分解生成物は消化時に酵素によって加水分解されるという。すなわち、食品の主要成分である脂質、タンパク質、糖類の放射線分解生成物は主に酸化還元反応によって生成され、加熱調理や自然劣化でも生成するものが多いことがわかっている(図-2)。一方、加熱でで生じる「こげ」や糖とアミノ酸の加熱反応では強い変異原性物質が生成することもわかっている。
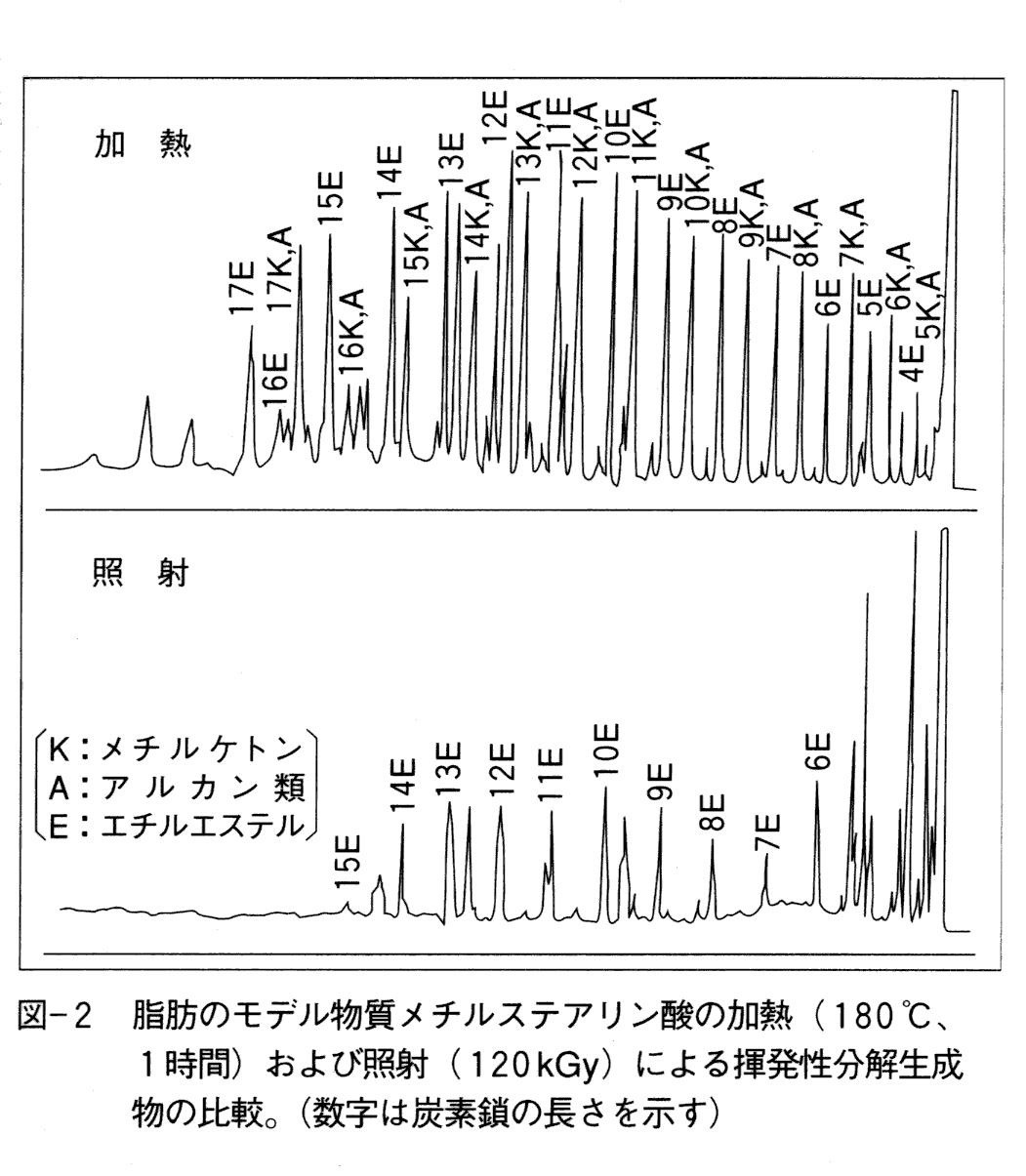 |
ビタミン類の場合、放射線による分解は酸化分解が中心であり、加熱調理による分解と似ている。DNAの場合は分子鎖切断がほとんどであり、DNAを構成する塩基の酸化分解も若干起こるが生成量は極微量である。食品中の残留農薬は殆ど分解されないと報告されており、分解率は10kGyで100万分の1以下である。また、農薬から遊離した塩素や臭素と食品成分や放射線分解生成物が反応する可能性もほとんどない。
放射線特有の分解生成物として近年問題になっているのは高脂質含有食品に高線量照射で生成する2−アルキルシクロブタノン類である。これらの化合物は脂質のグリセリン結合部が放射線の解離反応によって生成するもので、59kGy照射した鶏肉の脂質1g当たり17μg生成される。ドイツの研究では癌細胞の1本鎖DNAの電気泳動による分析で変異原性の可能性が指摘された。しかし、ビタミンCなどにもDNAに対して同様の作用があるし、標準的な変異原性試験では遺伝毒性は認められていない。一方、高濃度投与すると発癌促進作用の可能性があるとの研究があるが、ラット各群6匹の結果では再現性に問題がある。また、通常の照射食品の脂肪酸中には癌を抑制するものもあり、それらの脂肪酸に比べ2−アルキルシクロブタノン類の生成量は極微量であるため問題にする必要性はないであろう。
このように照射食品の健全性は世界的に見ても60年以上にわたる研究によって問題のないことが証明されている。WHOは、食品照射は食品による疾病などからの安全確保と食料資源確保の上で重要であり、人類の栄養確保および健康管理に重要な役割をはたすと期待している。
1)川嶋浩二、林 徹、河端俊治(訳):WHO技術報告シリーズNo.659 照射食品の健全性・FAO/IAEA/WHO合同専門家委員会(1980)報告、食品照射、16巻、89 - 111(1981)。
2)FAO/IAEA : Consultants' Meeting on the Development of X-ray Machines for Food Irradiation, Vienna, Austria, 16 - 18 October 1995.
3)世界保健機関:照射食品の安全性と栄養適性、コープ出版、1996年。
4)WHO : High-Dose Irradiation ; Wholesomeness of Food Irradiated with Doses above 10kGy, Report of a Joint FAO/IAEA/WHO Study Group, WHO Technical Series 890, Geneva, 1999.
5)Scientic Committee on Food in EU : Revision of the opinion of the Scientific Committee on Food on the irradiation of food, European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General SCF/CS/NF/IRR/24 Final, 24 April 2003.
6)Joint FAO/IAEA Division of Atomic Energy in Food and Agriculture : Decontamination of Animal Feeds by Irradiation, STI/PUB/508, IAEA, Vienna, 1979.
7)W. W. Nawar : Volatiles from food irradiation, Food Reviews International, 2(1), 45 - 78(1986).
8)松山 晃、降矢 強、市川富夫、内山貞夫、伊藤 均、林 徹:照射食品、総合食品安全事典、p.842 - 877、産業調査会・事典出版センター、1999年。
9)食品照射研究委員会:研究成果最終報告書、(社)日本アイソトープ協会、1992年。
|
|