表-1 食品照射の工程管理に利用できる線量計の候補
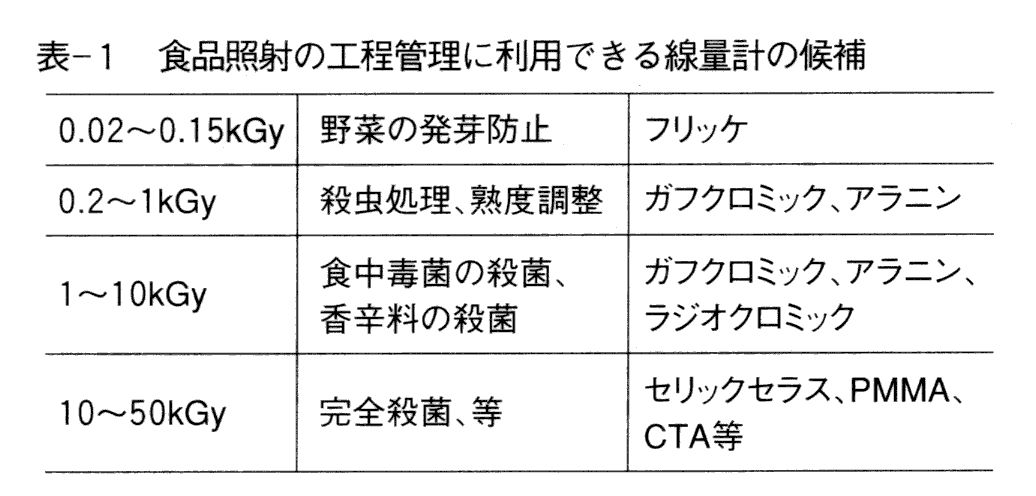 |
食品照射での必要線量は0.02〜50kGyと照射処理の目的によって大きく異なる。従って、各食品は目的によって上限線量と下限線量を正確に測定してから照射する必要がある。例えば、肉の食中毒菌殺菌の目的で上限線量を大幅に越えて照射すれば異臭が発生する可能性があるし、下限線量より少なく照射すれば食中毒菌の殺菌が不完全になる。線量計も0.02〜50kGyの範囲を単独で測定できるものはなく、低線量、中線量、高線量に合った線量計が必要である。わが国での馬鈴薯の商業用照射施設がスムーズに稼働したのは幅が約1mのコンテナーの線量分布をビルドアップで計算しただけでなく、実際に馬鈴薯をコンテナーに詰めて、フリッケ鉄線量計で測定してから設計したからである。
研究者が行う食品照射の実験においても線量測定は重要であり、線量という物差しが狂っていればデータそのものの信頼性が失われるであろう。例えば、照射施設の公称線量はあくまで空間線量分布であり、研究者は各実験に用いる照射物内の吸収線量を測定しておくべきである。微生物を例にとると、吸収線量評価がいいかげんだとデータが2倍以上異なることがある。また、電子線やガ ンマ線、X線は透過力が大幅に異なるため、試料の形状や厚さなどにも工夫が必要であろう。
照射食品の検知は各梱包物内に線量計が設置されており、標示がきちんと行われておれば、必要ないであろう。しかし、違法な照射とか標示がない場合もあり得るので、消費者は照射食品の検知が可能なことを望んでいる。照射食品の化学的分解生成物は加熱調理と似ているので通常な化学分析では検知は困難である。したがって、物理的方法とか特定放射線分解生成物の化学分析、生物学的方法から照射の有無が判別可能となっている。
ここでは、食品照射における線量測定、照射技術、検知法について述べると共に、今後の食品照射の展望について述べることにする。
食品照射に利用できる放射線はガンマ線、X線、電子線に限られている。微生物や害虫等に及ぼす各種放射線はエネルギーが異なっても吸収線量が同じなら、散乱線の影響も含め同じような効果を及ぼす。例えば、コバルト−60のガンマ線でもセシウム−137のガンマ線でも微生物の放射線感受性は同じである。しかし、電子線や制動放射X線のように通常のコバルト−60線源に比べ線量率が1,000〜10,000倍も高いと食品内等の酸素拡散速度の影響を受けて、殺菌線量などは約10%多く必要となる。
照射工程における線量管理は照射食品の品質管理法として重要である。食品照射の研究ではフリッケ鉄線量計が主に用いられてきた。食品照射の工程管理に利用できる線量計は今後も種々開発されると思われるが、表-1に示すような線量計が候補例である。馬鈴薯やタマネギ、ニンニク等の0.02〜0.15kGyの発芽防止には希釈操作なしに吸光度を測定できるフリッケ鉄線量計が最適であろう。0.2〜1kGyの殺虫処理等にはガフクロミックやアラニン線量計が適しており、フリッケ鉄線量計も希釈操作をすれば利用できる。1〜10kGyの食中毒菌の殺菌や香辛料の殺菌にはガフクロミックやアラニン、ラジオクロミック線量計が適していよう。30〜50kGyでの滅菌線量ではセリックセラスやPMMA(ポリメチルメタアクリレート)、CTA(三酢酸セルロース)などが用いられる。これらの線量計は照射時や照射後の温度の影響や線量率の影響等について調べておく必要があろう。また、フリッケ鉄線量計等の標準線量計との校正も必要である。
また、照射工程の管理には梱包物の表面にカラーラベル(カラーインジケータ)を添付して、照射によって色が変化するようにして、非照射物と混同しないように工夫する必要がある。カラーラベルも線量範囲によって発色の程度が異なるので、照射目的に適したカラーラベルを用意しておく必要がある。
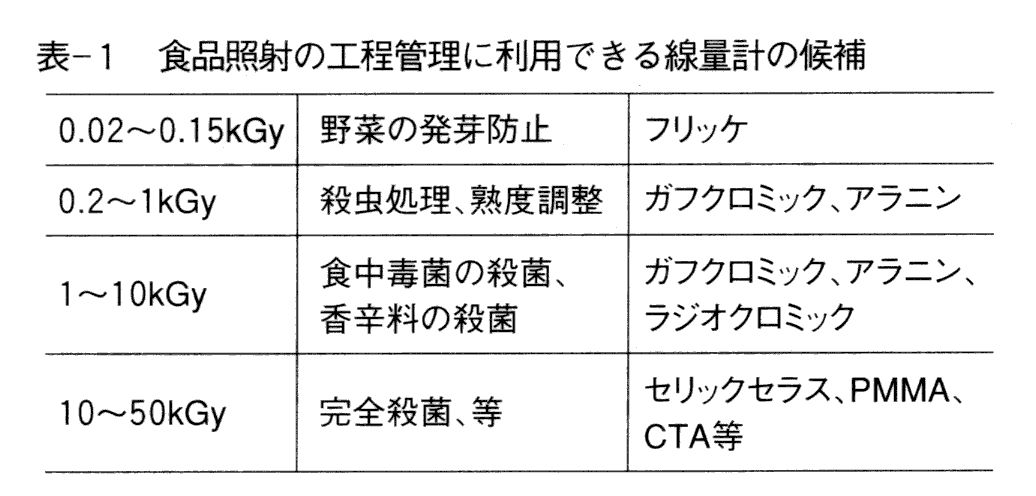 |
食品の照射効果は吸収線量に依存するので、食品梱包物の各部位でほぼ均一の線量が照射される必要がある。ガンマ線やX線は透過力が優れているため約1mの厚さの梱包物でも照射可能であるが、電子線は透過力が弱いため梱包物の厚さを薄くするか、食品表面の照射に適している。
ガンマ線を放出する放射性物質は多種類あるが、商業用線源として用いられているのはコバルト−60(半減期5.3年)である。セシウム−137(半減期27年)もガンマ線源として利用可能であるが潮解性など取り扱いが難しく、食品照射では商業的に利用されていない。大規模なガンマ線照射施設は図-1に示すようにコバルト−60線源が水中に格納できるように工夫されている。コバルト−60のガンマ線は水深4.5mで遮蔽されるためプールの深さは6〜7mで十分である。照射室は約2m厚のコンクリートで遮蔽されており、室外に放射線が漏れないように工夫されている。ガンマ線源は昇降装置によって自動的にプールから上昇し、照射用梱包物はコンベアで迷路を通って連続的に照射される。また、照射中には作業員は照射室に入れないように工夫されており、照射作業中に放射線が少量でも漏れると感知器が警報を鳴らすように工夫されている。商業的な照射施設は梱包物をホークリフトでコンベア架台に乗せる方式が多く、線源強度は50〜200万キュリー(18〜37ペタ・ベクレル)である。1日当たりの処理量は香辛料の場合で平均線量10kGy照射で20〜30トン、線量均一度は約1.5(線量範囲8.5〜12.5kGy)であり、処理コストは1kg当たり約50円であろう。北海道士幌農協の馬鈴薯照射施設では線量が0.06〜0.15kGyのため照射コストは1kg当たり2〜3円である。
電子線や制動放射X線の照射に用いる電子加速器は主に静電加速方式と高周波加速方式に大別できる。静電加速器は直流高電圧により電子にエネルギーを与える方式であり、出力が大きい照射装置が得られやすい。しかし、電子のエネルギーは5MeV以下であり、梱包状よりも粒状または粉末などの照射や薄い包装食品の照射に適している。高周波加速器は高周波を使用して電子を繰り返し加速するもので10MeVの高エネルギーの加速も可能である。10MeVのエネルギーでは10〜20cm厚の梱包物の照射に適している(図-2)。香辛料を例に取れば、電子線のエネルギー10MeV、電流20mAで平均線量10kGyの照射では20cm厚の梱包物で線量均一度が約1.5で照射でき、1時間当たり40〜50トンの処理が可能であり、照射コストも1kg当たり約20円となる。電子加速器の照射室の遮蔽・安全管理はガンマ線照射施設と同じである。電子線を重金属のタングステン板またはタンタル板に照射すると制動放射X線が発生する。電子線の3〜5MeVで発生する制動放射X線の透過力はコバルト−60ガンマ線と同じか、それより良好とされているが転換効率が5MeV電子線でも約7%であり、実際の照射に利用できるのは約1%程度とされている。しかし、照射方法を工夫すれば電子線エネルギーの約6%が利用可能との報告もある。制動放射X線の照射コストはガンマ線より高いとされているが、人口密集地でも設置可能なため輸送費などを考えれば経済的に引き合う可能性がある。
食品を商業的に照射するためには照射時の吸収線量を定常的に測定し過剰照射や照射不足が起こらないようにする必要がある。また、照射施設では食品以外の異物が照射食品中に混入したり、微生物や害虫の再汚染が起こらないように衛生管理を厳重に行う必要がある。また、食品梱包物にはカラーラベルを添付して照射の有無を肉眼で判別できるように工夫することが望ましく、作業ミスによる再照射を防ぐことが必要である。さらに、照射物には照射済みの標示をする必要がある。これらの工程管理はコーデックスの「照射食品に関する一般規格」を参考にするべきである。また、食品の放射線処理は衛生的に製造された製品を対象とするべきであり、不適切な衛生管理をごまかす手段としての照射は国際的に禁止されている。再照射については1kGy以下の殺虫処理等を目的とした照射物以外は再照射は禁止されている(もちろん、この場合でも再々照射は禁止されている)。
商業用の照射施設は食品の集荷地または港に設置するか、食品の加工処理工程の一部に組み込むように設置することで、人件費や輸送コストを低減できるであろう。
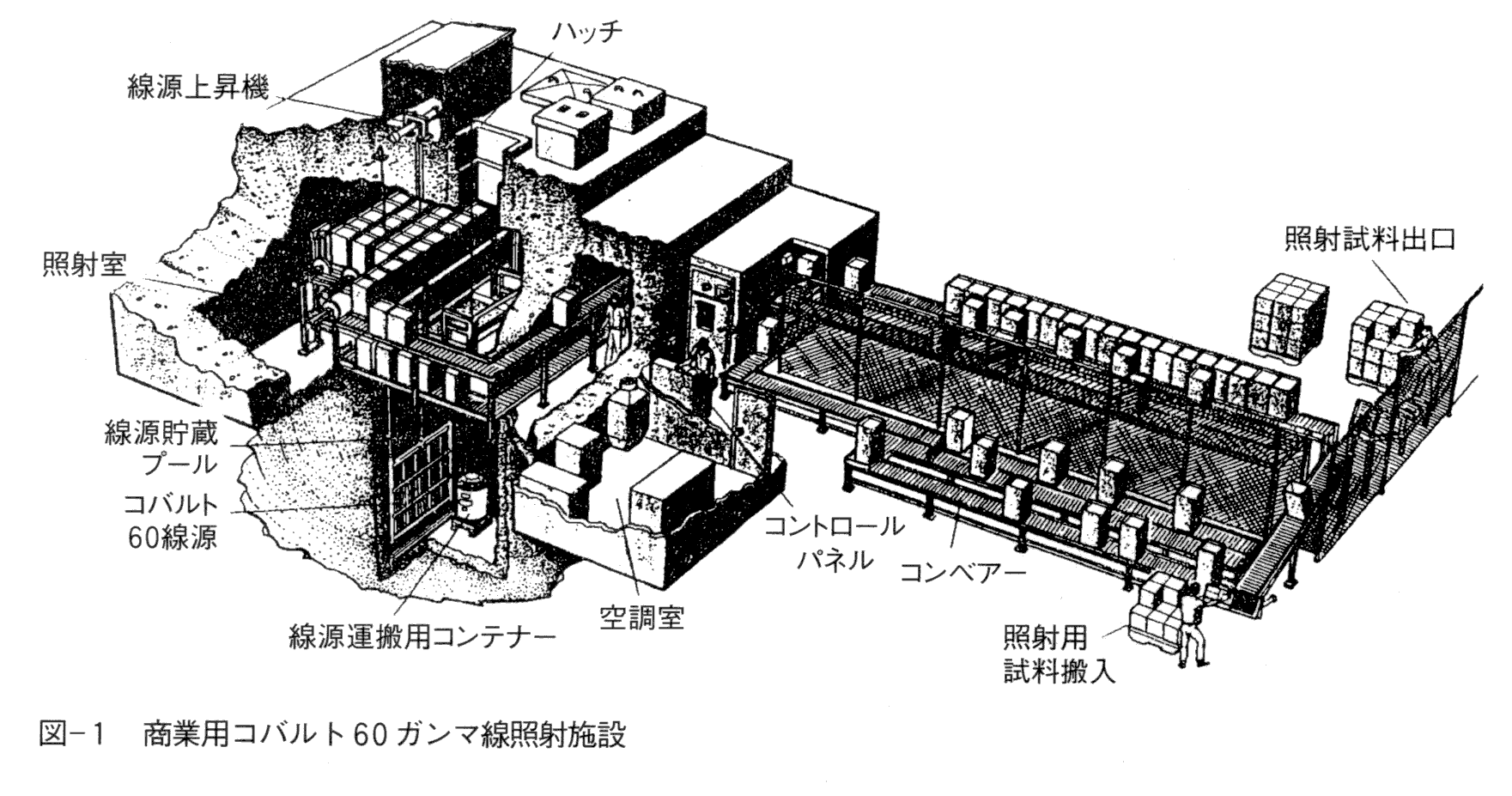 |
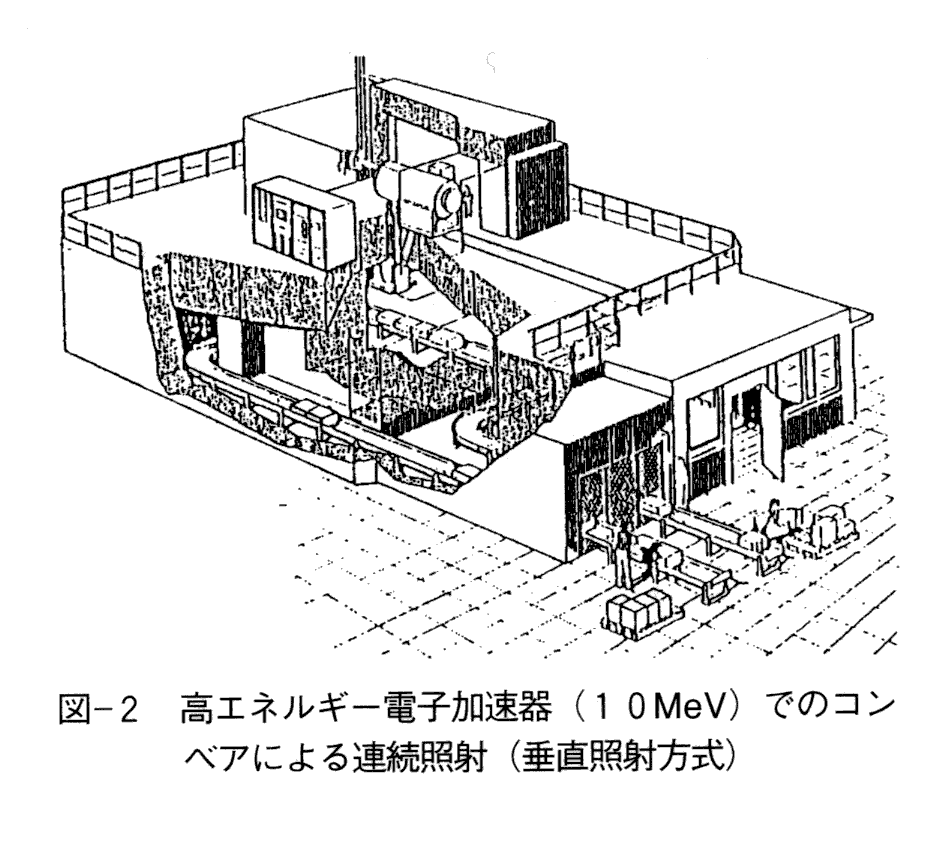 |
照射食品は薬剤処理と異なり食品中に残留化学物質がなく、放射線により化学変化が起こったとしても加熱や凍結乾燥処理によって起こる変化と大差がない。従って、通常の化学分析では検知は困難である。照射食品の検知法では迅速に分析でき、必要な試料が少なくてすみ、適用できる線量範囲が広く取れ、安価に分析できることが望ましい。さらに検知と同時に吸収線量を推定できることが望ましい。わが国では原子力特定総合研究において検知技術の研究が行われたが、見るべき成果は得られなかった。1980年代に入ると国際的に食品照射の実用化が開始され、検知技術も新しい観点から開発されるようになった。また、国際プロジェクトも組織され、物理学的方法、化学的方法、生物学的方法で多くの有望な検知技術が開発されるようになった。
照射食品ではフリーラジカルが生成され、DNA鎖などの切断、脂質の分解などが起こる。これらの変化を検知に用いるには、1)放射線特有の変化であり、2)変化が長期にわたり安定に存続する、3)線量の相関性がある、4)試料によるばらつきが少ないこと、などが重要である。国際的に有望な検知技術は表-2に示すように、ESR法、熱ルミネッセンス法、DNAコメットアッセイ法など10種類の方法がある。
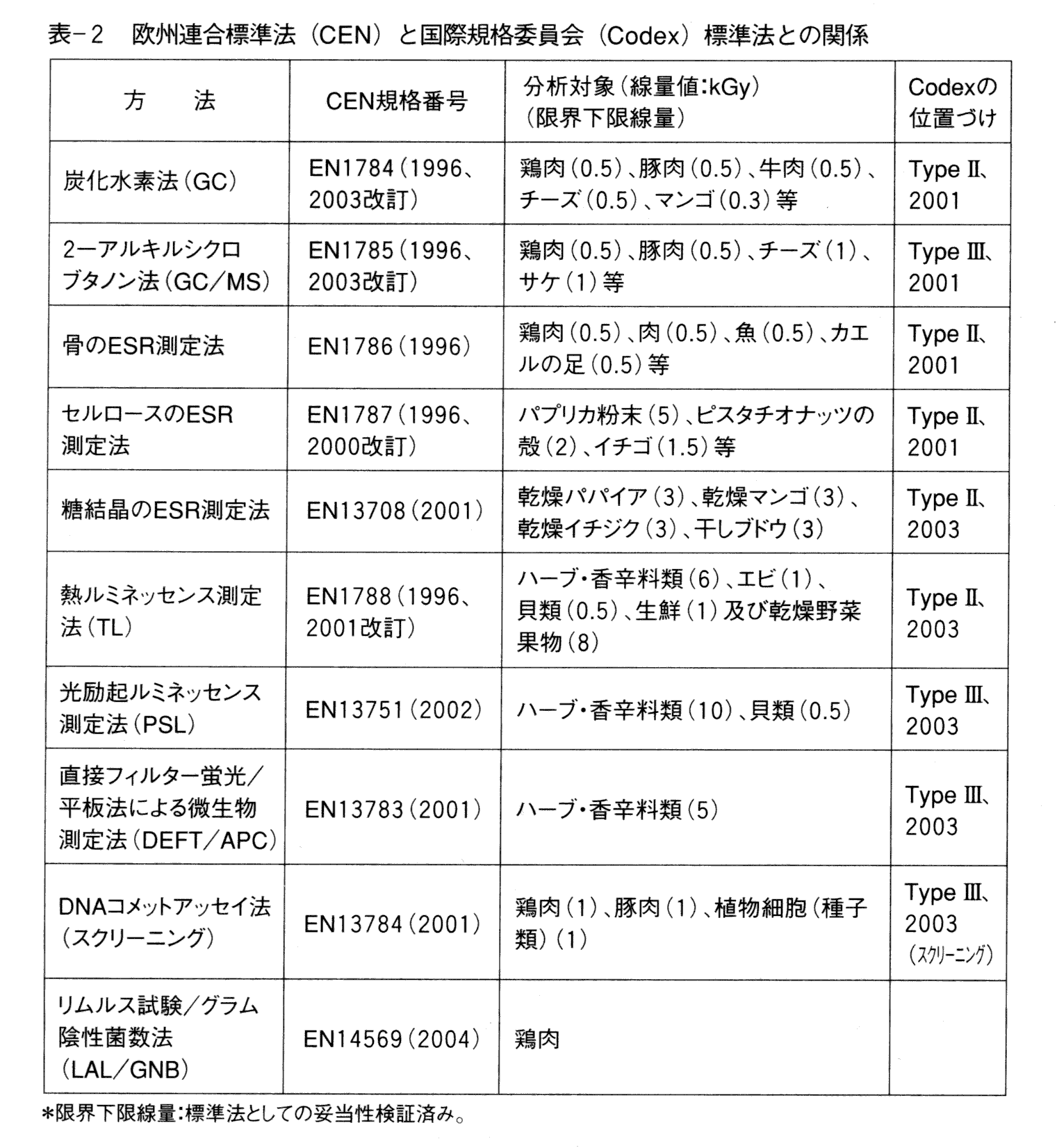 |
[物理的方法]
物理的な検知法としてはESR法、熱ルミネッセンス法、光励起ルミネッセンス法、電気インピーダンス法などがある。照射された食品中にはフリーラジカルが生成するが、多くの食品成分は水と共存しているため、すぐに消失してしまう。しかし、食品中に微量に混在している骨片やセルロース結晶中のフリーラジカルは比較的安定であり、これをESR(電子スピン共鳴)法で測定することができる。ESR法では骨片やセルロースを含む試料を十分に乾燥してから測定する必要があり、1〜25kGy照射された鶏肉の骨片や香辛料で数ヶ月の期間にわたり検知が可能である。
熱ルミネッセンス法は食品中に混在する砂などの鉱物の結晶が照射によって自由電子と正孔が生じ、これに70〜400℃の温度を加えると発光する現象を利用したものである。1985年頃より照射香辛料の検知法として有望であると報告されるようになった。熱ルミネッセンス法による香辛料の検知には前処理なしにそのまま測定する方法(直接法)、鉱物質を抽出する方法(抽出法)、抽出した鉱物の校正照射(1kGy)前後の発光量の比を測定する方法(標準化法)がある。この中で、直接法は短期的には検知が可能であるが3ヶ月以上の貯蔵では検知が困難であるとされている。抽出法は3ヶ月から1年貯蔵でも検知が可能であるが、完全な検知は困難である。一方、標準化法では1kGy前後では90%、5kGy以上では100%の検知が可能であり、長期貯蔵でも検知が可能である。
光励起ルミネッセンス法は熱ルミネッセンス法と似ており、前処理なしに試料を測定できるという利点がある。この測定原理は珪酸塩やカルシウムなど食品由来の無機物に強い光があたると照射後に準安定状態にあった電子が発光中心の正孔と再結合する際に発光する現象を利用するもので、0.4kGyでも測定可能である。光励起ルミネッセンス法では香辛料や乾燥野菜を4ヶ月貯蔵でも測定可能であるが、長期貯蔵物では測定は困難である。
香辛料などに含まれる澱粉などの多糖類は照射により粘度が低下する。この変化を回転粘度計で測定することによって多糖類を多量に含む食品類の検知が可能である。例えば、照射した黒コショウなどの10%水懸濁液をpH12.5に調整してから100℃・30分沸騰してから測定すると非照射に比べて粘度が著しく低下する。電気インピーダンス(交流電気抵抗)の測定は照射馬鈴薯の検知技術として有望視されている。
[化学的方法]
食品の照射による分解生成物の分析から検知する方法としては脂質の分解によって生成する揮発性炭化水素を分析する炭化水素法がある。加熱調理でも炭化水素が生成するが、放射線ではヘキサデカンおよびヘプタデカン等の生成が多いことを利用した検知法であり、肉類やチーズ、マンゴー、パパイヤ等に適用できる。2−アルキルシクロブタノン類は脂質を照射した場合に微量に生成し、脂質を多く含む照射食品の検知に応用できる。ただ、生成量が微量なため特殊な分析装置が必要で、しかも低線量照射食品には適用しにくいという欠点がある。
[生物学的方法]
馬鈴薯やタマネギ、ニンニク等では発芽能や発根能の観察が最も確実な検知法であるが、収穫前に発芽防止剤が散布されている可能性もあるため、薬剤の検出との組み合わせが必要であろう。また、馬鈴薯の発芽部を組織培養して形態的変化を観察する方法もある。生鮮果実の種子は0.1kGy以上の照射で発芽率が低下する。この原理を利用するとグレープフルーツやレモン等の種子を有する果実の検知が可能である。この方法は検知に6〜14日かかるのが欠点であるが、ジベレリン添加などによって発芽促進処理をすれば短期間の検知が可能になる。
照射後に生残する微生物の種類を比較すると照射の有無をある程度検知することが可能である。ことに、肉類や魚介類では1kGy以上照射するとサイクロバクターと腐敗性酵母菌が10℃以下の貯蔵で優先的に増殖して来るので検知が可能である。香辛料等の場合には直接フィルター蛍光観察法とプレート法による生残菌数測定の比較によって検知が可能である。また、芽胞細菌の耐熱性が低下することを利用した検知も可能である。
細胞内のDNAのコメットアッセイ法は照射によって起こるDNA断片を電気泳動にかけて彗星のように見える尾の長さを顕微鏡で観察する方法であり、基本的にはDNAを含むあらゆる食品に適用できる。しかし、DNAの断片化は他の処理法でも起こるためスクリーニング法として使われ、他の検知法との組み合わせが必要である。
わが国の食料自給率は約40%と他国に比べ異常に低く、海外から多量の食料を輸入している。海外の国々には当然のことながら、わが国には分布していない農業害虫や寄生虫、病原菌が生息しており、輸入食品を通じてわが国に侵入してくる可能性がある。しかし、検疫処理で広く使用されてきた臭化メチル薫蒸はオゾン層破壊物質として2005年で一部の検疫処理を除いて使用禁止となり、臭化メチルには毒性もある。このため、輸入穀類等はホスフィン(燐化水素)等で殺虫処理が行われている。しかし、ホスフィンは臭化メチルと比べ穀類内への浸透力が低く、耐性虫が発生するという問題点がある。海外から輸入されてくる生鮮果実の中には蒸熱法(果実の中心温度46.8℃、10分間)で殺虫処理されているものもあるが、蒸熱処理によって品質に悪影響を受ける。これに対して、放射線処理法は殺虫線量が0.2〜0.5kGyであり、生鮮果実や穀類の品質への悪影響はほとんどない。
香辛料や乾燥野菜等は気流式過熱蒸気で殺菌処理されているが、香気成分が著しく低減したり色調が変化するなどの問題点がある。このため、加工食品によっては人工の香り成分等が使用されている。放射線殺菌法は7〜10kGyで照射されるが、香気成分や色調変化がない優れた殺菌法であり、多くの国で実用化されている。わが国では2000年に全日本スパイス協会が厚生労働省に許可要請を行っているが、今だに許可になっていない。
わが国で生産されている肉類や食鳥肉、魚介類でもサルモネラや腸管出血性大腸菌のO157などで汚染されていることがあり、リステリア菌や腸炎ビブリオ菌、カンピロバクターなどでの汚染も起こっている。また、薬剤耐性病原菌も食品中に広く分布している。これらの食品類も放射線で殺菌することで食中毒発生や病気の頻度を低減できるであろう。
一方、馬鈴薯やタマネギ、ニンニクなどの根茎野菜類は4〜5年前までは収穫前に発芽防止剤が散布されて発芽抑制処理が行われていたが、現在では使用が中止されているためソラニンによる中毒も報告されている。このため、ニンニクでは−2.5℃で発芽を抑制しているが、店頭や家庭で腐敗しやすいという問題がある。放射線処理は0.02〜0.15kGyで発芽抑制効果があり、しかも室温貯蔵でも長期にわたり腐敗が起こらない有効な処理法である。
食品照射を普及させるためには消費者の理解が必要である。そのためには放射線と放射能の混同の問題や安全性等についてマスコミ等を巻き込んだ宣伝活動が必要であろう。
米国政府は食中毒対策として肉類や食鳥肉の食中毒菌の殺菌に注目しており、食品医薬品局は1997年に牛肉などの照射を許可した。農務省は照射のための規格を作り、その内容は1)最高線量は冷蔵肉(食鳥肉を含む)は4.5kGy、冷凍肉は7.0kGy、2)照射の目的は腸管出血性大腸菌、サルモネラ、リステリア菌、カンピロバクターなどの食品由来の病原菌および寄生虫の殺滅、3)放射線処理はHACCP(危害分析・重要管理点)システムの一部として行う、4)標示はわかりやすくし、照射の目的を記載する、などである。また、米国は検疫処理で使用されてきた青果物の臭化メチル燻蒸の代替法として放射線処理を推進している。米国では各州ごとに検疫処理が必要であり、農業害虫の他州への拡散は深刻な問題である。そして、農務省は外国産の熱帯果実に寄生している7種類のミバエ類およびマンゴーゾウムシの殺虫(最低線量0.10〜0.25kGy)についても照射を認めている。米国では香辛料の放射線殺菌は年間6万トン程度照射され、牛肉挽肉も大量に照射されている。また、ハワイ等では熱帯果実の放射線殺虫も行われており、宇宙食や病人食、軍用食などの放射線殺菌も行われている(表-3)。
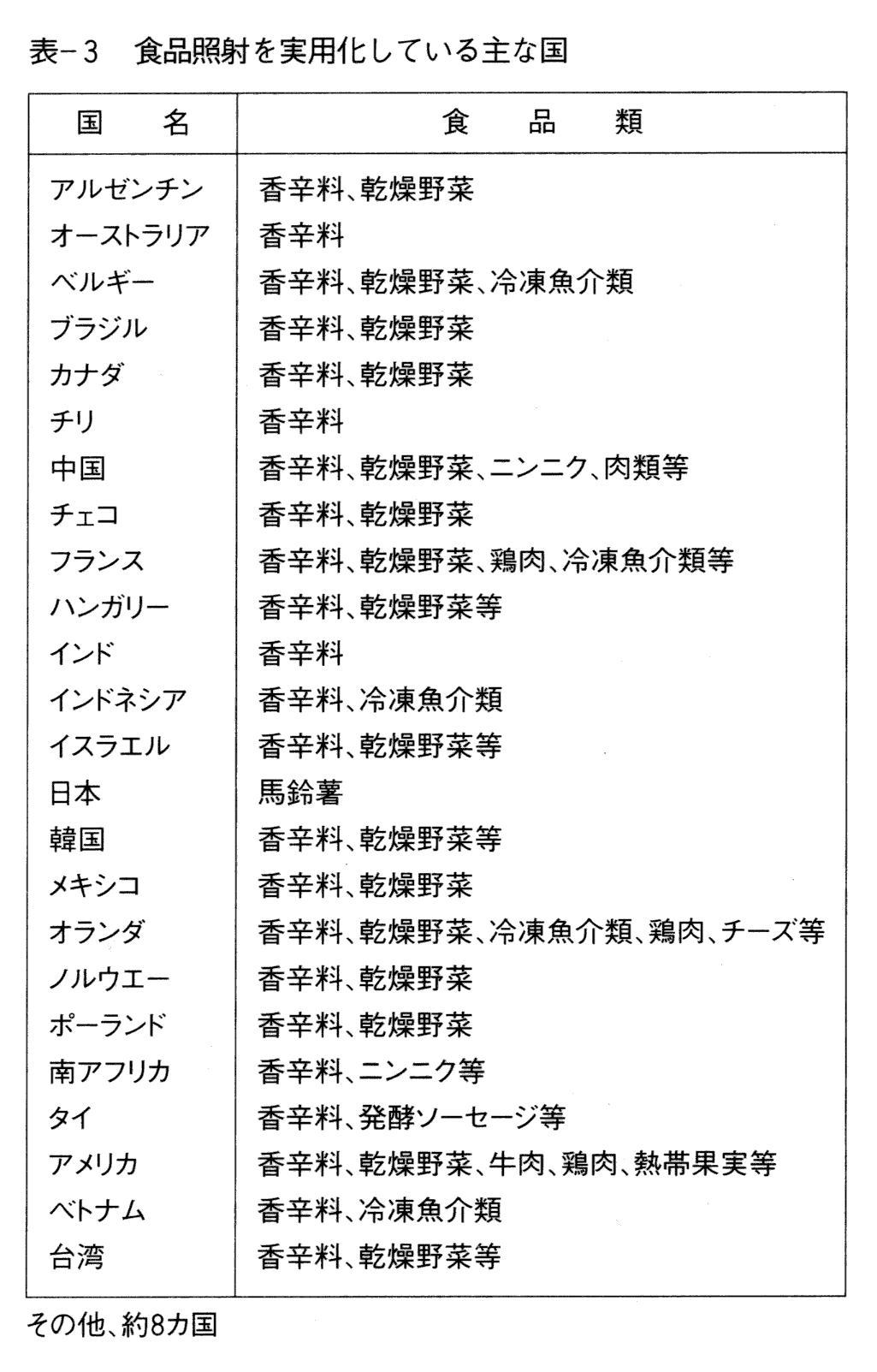 |
欧州連合は香辛料類の放射線殺菌については共通に認めているが、他の食品類については各国の規制にまかせている。欧州連合の中ではフランス、オランダ、ベルギー、ハンガリー等の国々で食品照射の実用化が活発である。オーストラリア、ニュージランド、カナダ、中南米諸国、南アフリカ、イスラエルなどの国々でも食品照射が許可され、実用化されている。
アジアでは中国が食品照射を大規模に実用化しており、ニンニクを年間8万トン以上照射しており、香辛料も2万トン以上が照射されている。韓国や台湾、タイ、インド、インドネシアなどでも香辛料などが商業的に照射されている。このように、米国や中国、韓国、欧州連合などで食品照射の実用化が進展しており、わが国だけが食品照射を認めないのは困難な情勢になっている。
1)(財)放射線照射振興協会・大線量測定研究委員会編:工業照射用の電子線量計測、地人書館、平成2年。
2)須永博美、伊藤 均、高谷保行、滝澤春喜、四本圭一、田中隆一、徳永興公:植物検疫を目的とした食品照射技術の検討、JAERI−Tech99-046、1999年。
3)世界保健機関・国際食料農業機関(林 徹訳):食品照射、光琳、1989年。
4)K. W. Bogl, D. F. Regulla, M. J. Suess(Ed.): Health Impact, Identification, and Dosimetry of Irradiated Foods, Report of a WHO working group on health impact and control methods of irradiated foods, Institut fur Strahlen Hygiene, ISH-Heft 125, Neuherberg/Munich, 1988.
5)後藤典子、田邊寛子、宮原 誠:照射鶏肉の炭化水素法及びESR法による検知、食品照射、35巻、23 - 34(2000)。
6)河村葉子、小島佳奈、杉田たき子、山田 隆、斉藤行正:熱発光法による照射香辛料の比較検討、食品衛生学会誌、36巻、55 - 61(1995)。
7)T. Hayashi, S. Todoriki and K. Koyama : Irradiation effects on pepper starch viscosity, J. Food Sci., 59, 118 - 120(1994).
8)Y. Kawamura, S. Uchiyama and Y. Saito : A half embryo test for identification of gamma-irradiated grapefruit, J. Food Sci., 54(2), 379 - 382(1989).
9)H. Cerda : Detection of irradiated frozen food with the DNA comet assay : Interlaboratory test, J. Sci. Food Agric., 76, 435 - 442(1998).
10)等々力節子:照射食品の検知技術、FFIジャーナル、209(12)巻、1060 - 1068(2004)。
|
|