図-1 輸入香辛料のアフラトキシン汚染件数
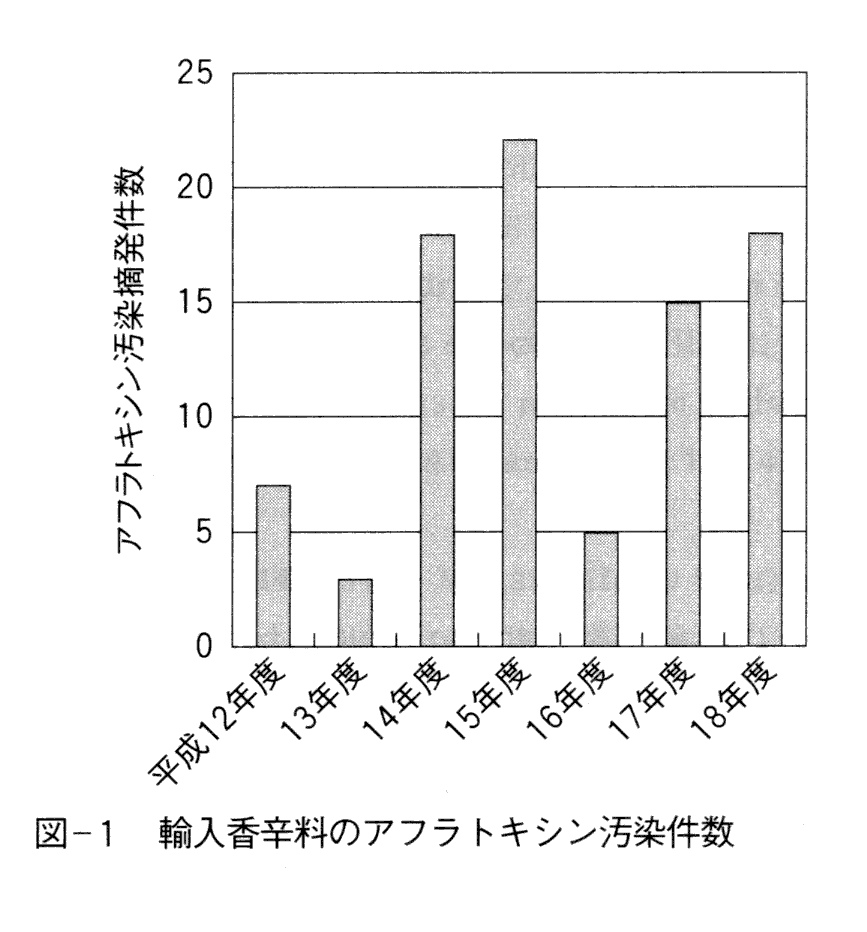 |
香辛料の放射線殺菌は、米国などで実施されている滅菌を目的とした30 kGyの照射と、EUなどで採用されている殺菌を目的とした10 kGyがある。日本では、殺菌目的の10 kGy照射が検討されている。この理由は、コーデックスの食品一般規格として、10 kGy以下の照射は安全性に問題はないと結論されており、実用許可を得られやすいことがある。また、食品成分の変化は線量が低いほど少なく、コストも安くなるなどの理由もある。殺菌の場合、病原菌や腐敗菌など特定の菌の殺滅を目的としており、香辛料の場合には大腸菌群やカビ毒産生菌の滅菌と一般細菌の菌数低減が目的となる。
強力な発がん性を有するカビ毒アフラトキシンの防止に放射線を利用するための研究は数多く報告されており、照射した糸状菌でのアフラトキシン産生能の増大などの問題点を指摘した報告もある。本稿では、これまでに取り上げられてきた香辛料照射におけるアフラトキシンの問題点に関する議論を整理し、香辛料の照射を実用化する上での一助としたい。
輸入香辛料のアフラトキシン汚染について、厚労省の輸入食品監視業務ホームページ1)に、輸入届出における代表的な食品衛生法違反事例が示されている。アフラトキシン汚染が摘発された例としては、米国からの穀類やピーナッツが圧倒的に多いが、香辛料の汚染も毎年摘発されている。平成12年度からの輸入香辛料のアフラトキシン汚染摘発件数を図-1に示す。少ない年もあるが毎年検出されており、15年度など多い年では20件以上が報告されている。また、香辛料別に見た摘発件数は、チリパウダーが圧倒的に多く、ナツメグやバジルなどが続いている(図-2)。輸入国別では、パキスタン、スリランカ、タイ、米国、インド、中国の順に摘発件数が多い(図-3)。このように、香辛料のアフラトキシン汚染摘発の件数は多く、その防止対策は重要である。
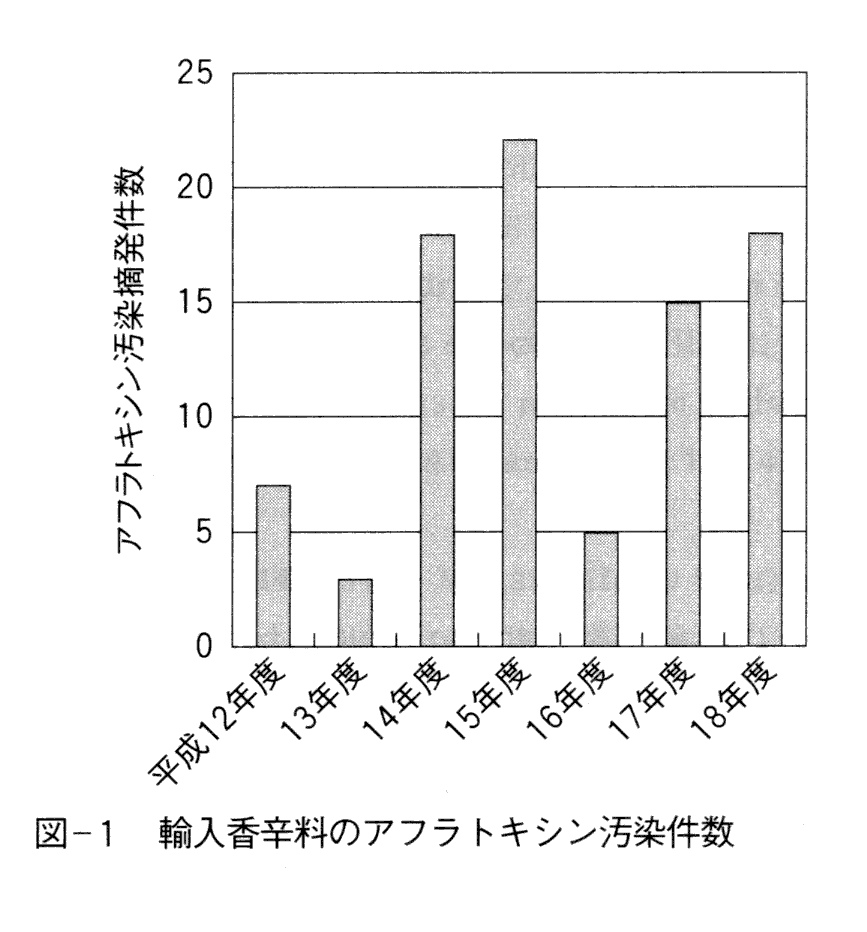 |
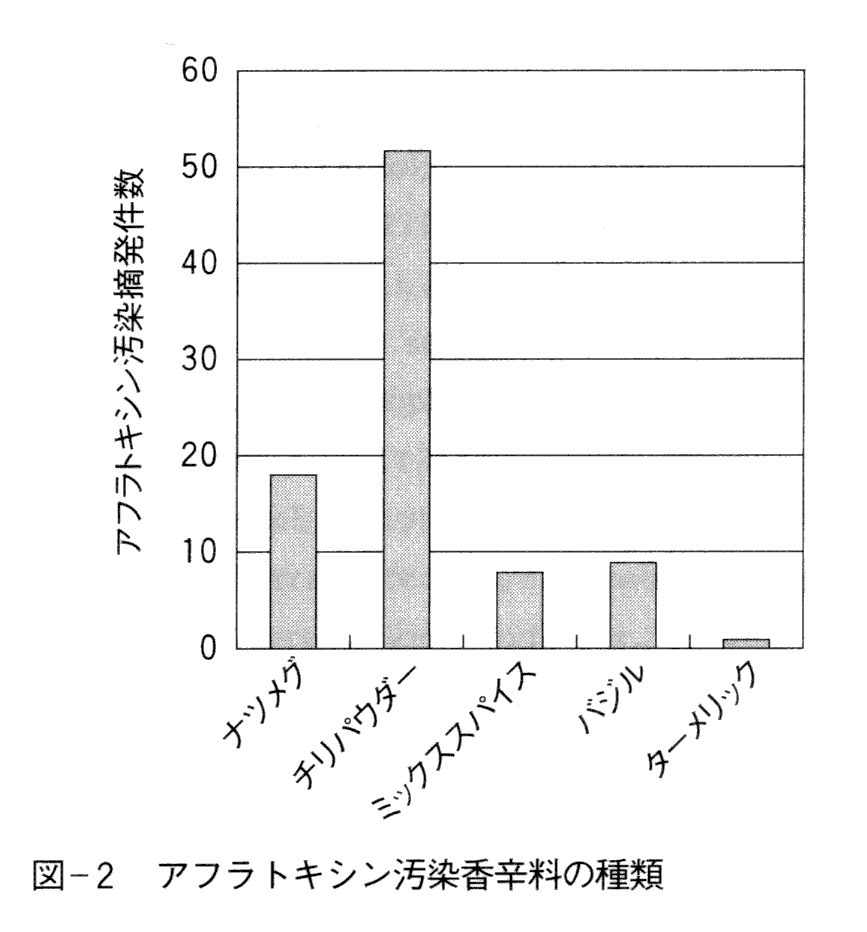 |
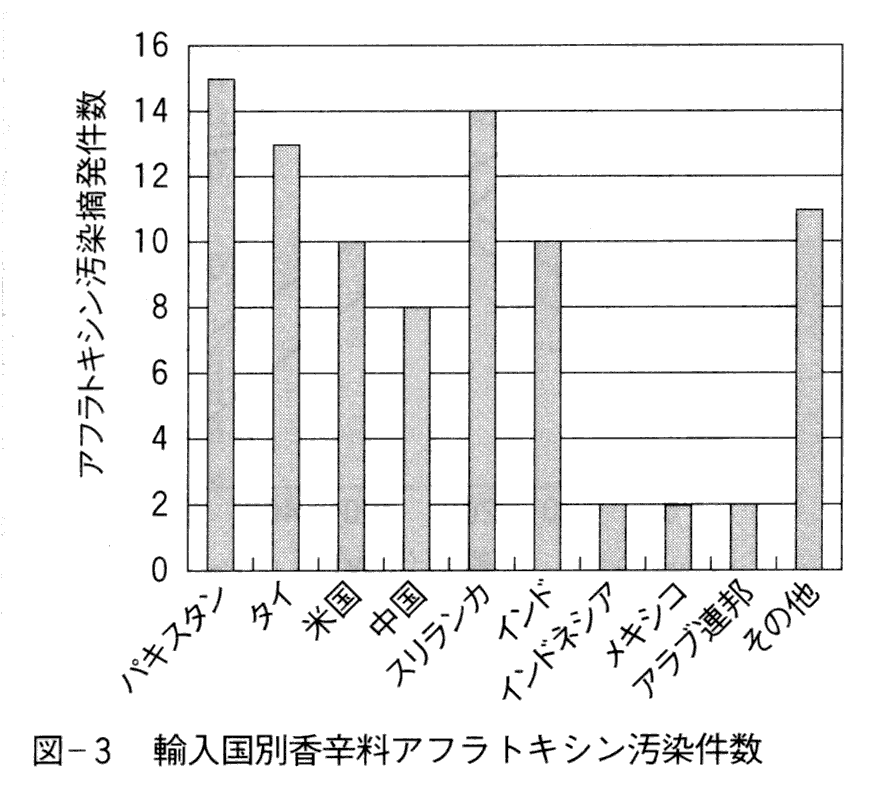 |
アフラトキシンは地上最強の天然発がん性物質であり、16種類が知られている。その内B1、B2、G1、G2の4種類と代謝物であるM1及びM2 の6種類が代表的なものであり、食品中の汚染物質として重要である。なかでもアフラトキシンB1の毒性が最も強く、ダイオキシンの10倍以上といわれている。主に、肝細胞がんを引きおこす原因物質として知られている。日本では、アフラトキシB1 について食品中に10 ppb以下という基準が定められている。これらアフラトキシンの分析にはHPLCが用いられ、B1、B2、G1、G2の4種類(図-4)を容易に分析・定量することができる。
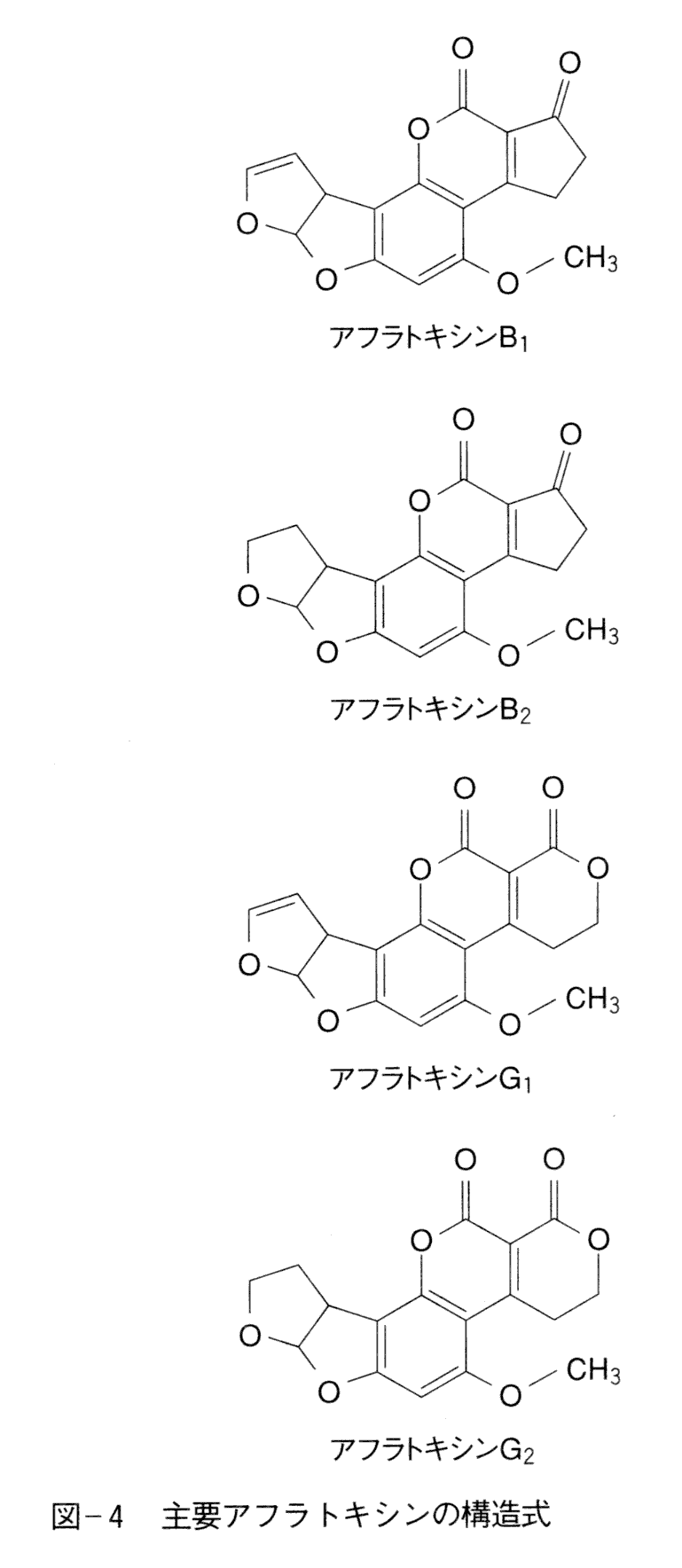 |
香辛料の汚染菌の中から分離されたアフラトキシンを産生する可能性のある糸状菌A. flavus群11株について、アフラトキシン産生能を調べた結果、2株に産生能が認められた2)。標準株に比べるとその産生量は1/3程度であるが、毒性の高いB1が多く含まれることが明らかにされている。
これらA. flavusの放射線殺菌曲線を図-5に示す。懸濁液中でのD10値は300 Gyであるが、乾燥状態では放射線に対して感受性が低く2倍の線量600 Gyが必要である。完全殺菌線量を、乾燥状態のD10値600 Gyの12Dとして求めると7.2 kGyとなる。
香辛料の一種ナツメグを用いて、実際の香辛料中での放射線殺菌効果を調べた結果を図-6に示す。総菌数(大部分は放射線に対して抵抗性の高い有芽胞細菌)は10 kGy照射でも1g当り10個生残している。アフラトキシン産生菌であるA. flavusを含む糸状菌は比較的放射線感受性が高く、5 kGy程度で検出限界以下になる。また、これら照射ナツメグの貯蔵試験の結果でも、8 kGy照射区では糸状菌の生育は認められず、滅菌効果が実証されている。このように、糸状菌は放射線感受性であり、芽胞菌より低い線量で滅菌することが可能である。
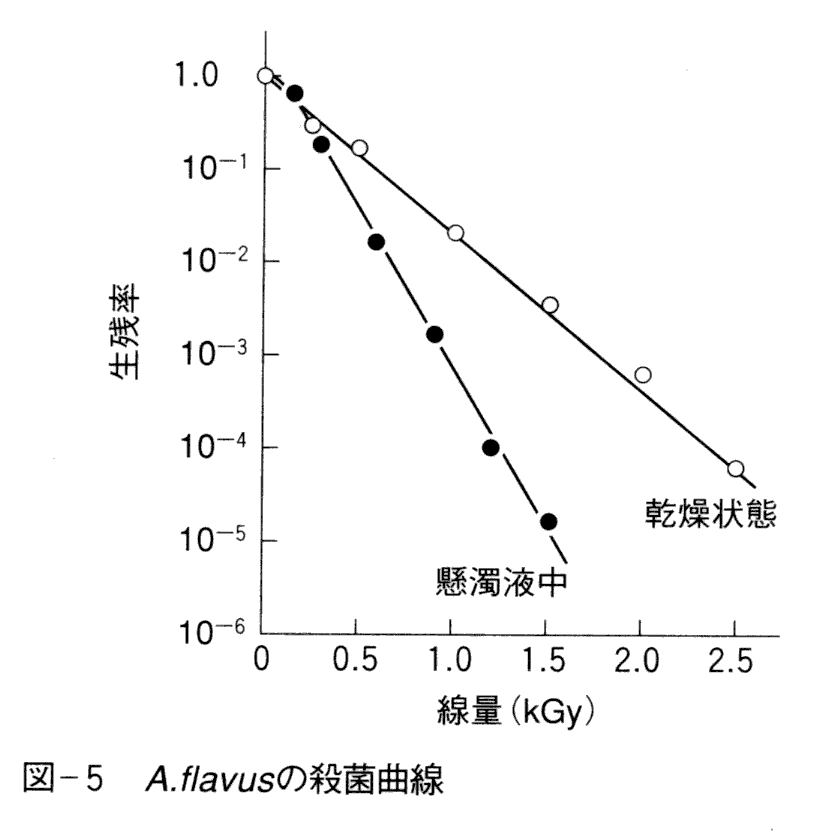 |
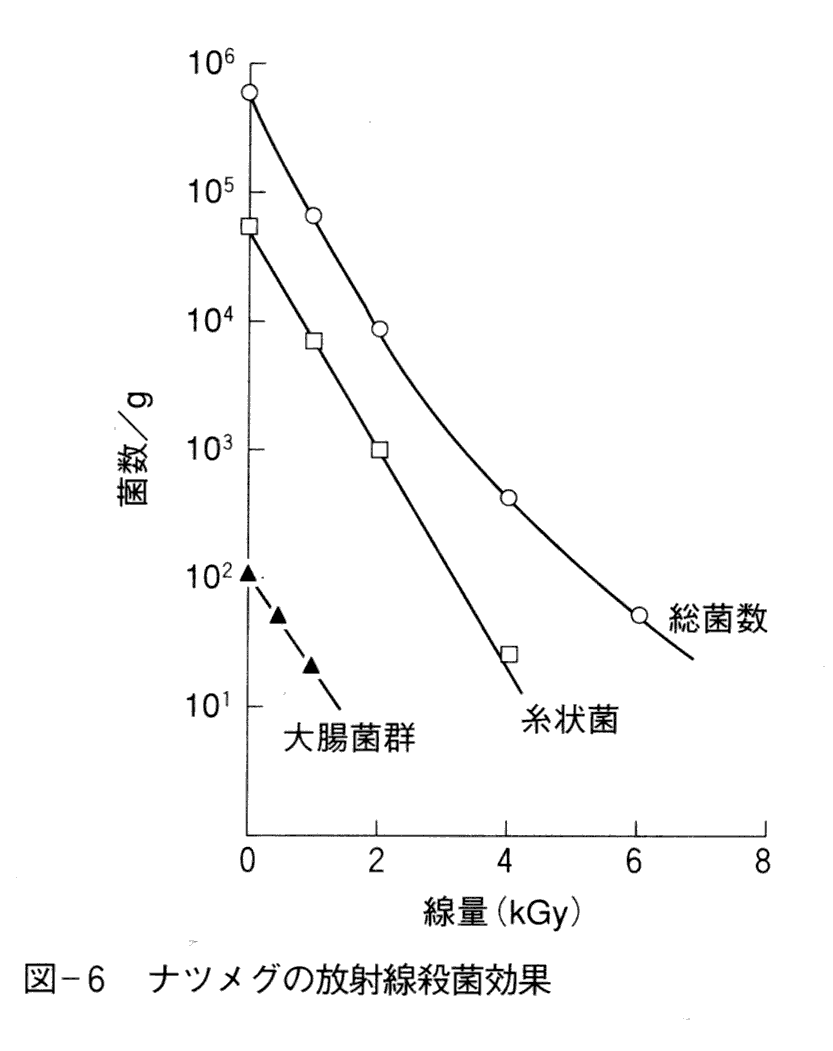 |
コメを培地としてA. flavusを培養してアフラトキシンを産生させ、放射線による分解効果を調べた結果2)を図-7に示す。食品中に含まれるアフラトキシンは、放射線に対して極めて安定で、分解のためには500 kGy以上の高線量が必要である。G1及びB1はG2及びB2に比べ比較的放射線感受性が高い。これは構造の違いに基づくものであり、構造図(図-4)左端の5員環に二重結合を有するG1及びB1が分解されやすい。水溶液中での分解も食品中の場合と同様にG1>B1>G2>B2の順に分解されやすく、食品中に比べ100倍壊れやすい(図-8)。
以上の結果から明らかなように、アフラトキシンを放射線で分解することは可能である。しかし、食品中のアフラトキシンを分解するためには、食品成分の劣化が生じてしまう高線量が必要である。したがって、食品照射で用いられる線量でアフラトキシンを分解することは実用上不可能である。
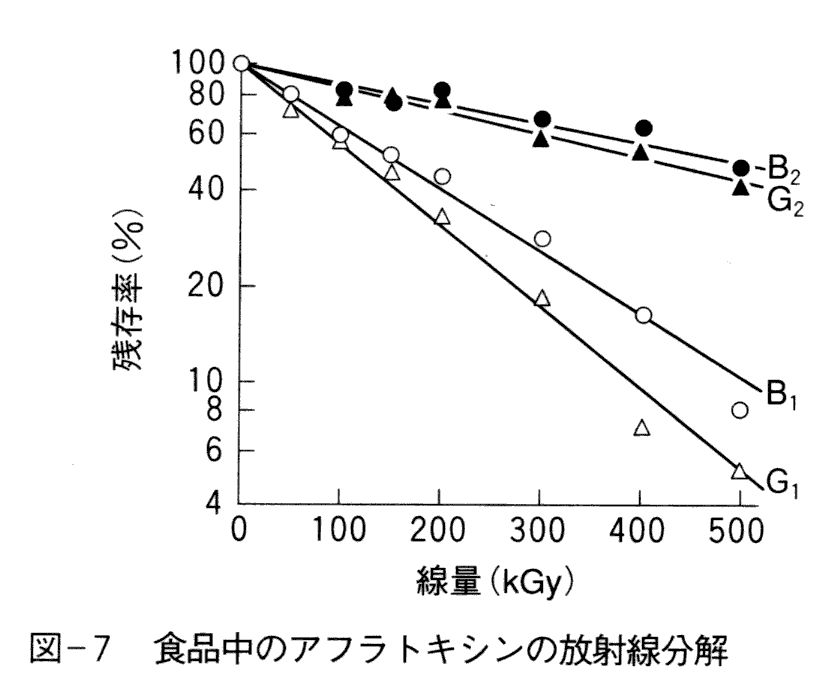 |
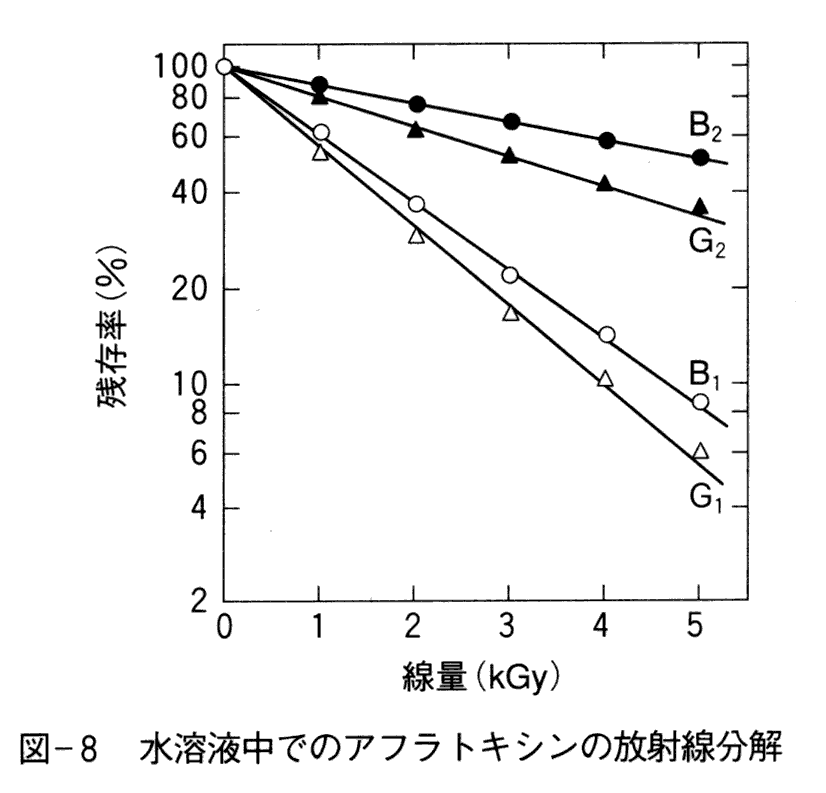 |
微生物学的安全性とは、照射食品に生残する微生物による影響や照射による微生物の突然変異に関する安全性である。すなわち、放射線照射が、病原性や毒性または放射線などに対して抵抗性が増大した突然変異株の誘発を増加させるのではないかといった懸念に関する検討である。
アフラトキシンについては、放射線の突然変異によるアフラトキシンB1産生能の増加の有無、低線量照射によるアフラトキシンB1産生促進効果の有無について、A. flavusを用いた研究結果が報告されている。これらの結果は、繰り返し照射を行っても産生量が増加することは無い、糸状菌の生育は減少しアフラトキシンの産生も減少する、といった放射線照射がアフラトキシンの防止に有効であるとする報告と、照射によりアフラトキシンの産生能が増大する可能性があると指摘する報告がほぼ半数ずつある。
アフラトキシン産生能が照射により増大するとの懸念を示す報告についてみてみると、以下の4項目に分類することができる。
強力な発がん性を有するカビ毒アフラトキシンを放射線で分解することは難しく、とくに乾燥状態や食品中では非常に高線量を要する。これに対して、アフラトキシンを産生する糸状菌は比較的放射線感受性が高く、8kGy程度の照射で完全殺菌できる(図-9)。したがって、アフラトキシンの防止には、アフラトキシンが産生される前に産生菌を完全殺菌しておくことが有効である。
低線量照射や繰り返し照射によってアフラトキシンが増加する可能性があるという報告は、1980年前後に多く発表された。しかし、これらは実用照射とはかけ離れた条件で、しかも非常に低い確率での可能性が指摘されたものである。香辛料の10 kGy照射という実用条件では産生菌の生残の可能性は無く、また万一の事故で照射線量が不十分で生残するという事態があったとしても、繰り返し照射されるようなことはあり得ない。また、照射後に水分の高い状態で再汚染がおこると産生量が増えるという可能性についても、GMP(適正製造規範)に則った照射後の管理が守られる限り起こり得ない。したがって、香辛料の実用照射において、微生物学的安全性を懸念する必要性は全く無いと断定することができる。
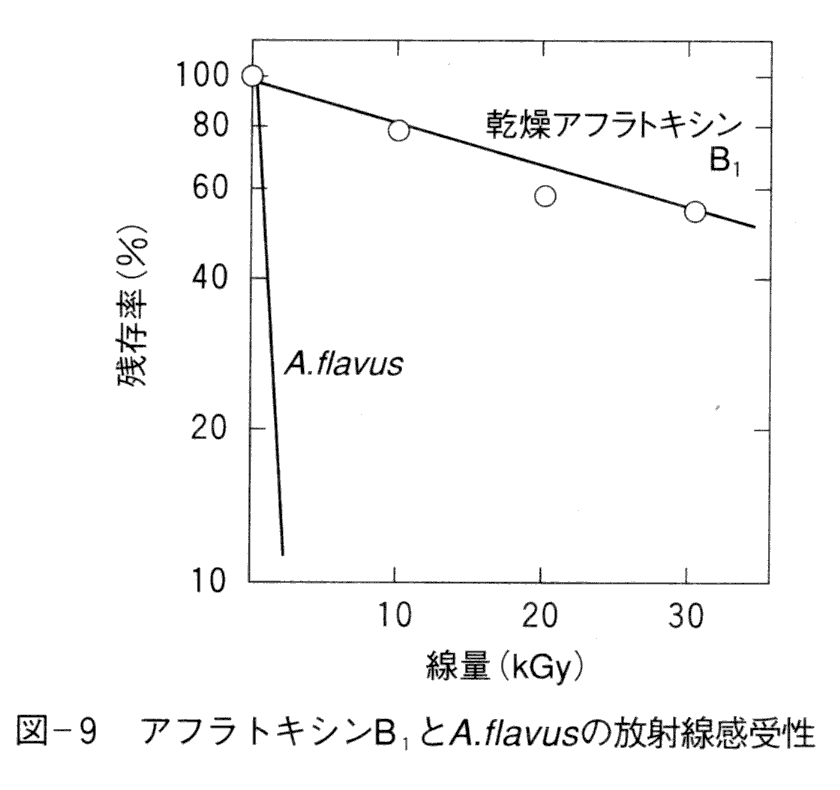 |
1) http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html
2) T. Kume, H. Ito, H. Soedarman, I. Ishigaki, Radiat. Phys. Chem., 34, 973-978 (1989).
3) A. Sharma, A. G. Behere, S. R. Padwal-Desai, G. B. Nadkarni, Appl. Environ. Microbiol, 40, 989-993 (1980).
4) G. T. Odamtten, V. Appiah, D. L. Langerak, Int. J. Food Microbiol., 4, 119-127 (1987).
5) E. Priyadarshini, P. G. Tulpule, Food Cosmet. Toxicol., 14, 293-295 (1976).
6) H. K. Frank, R. Munzner, J. F. Diehl, Sabouraudia, 9, 21-26 (1971).
7) A. F. Schindler, A. N. Abadie, R. E. Simpson, J. Food Protec., 43, 7-9 (1980).
8) 伊藤、食品照射研究委員会研究成果最終報告書(日本アイソトープ協会)、235-244 (1992).
|
|