表ー1 穀類・生鮮果実に対する各種害虫・防虫処理法の比較
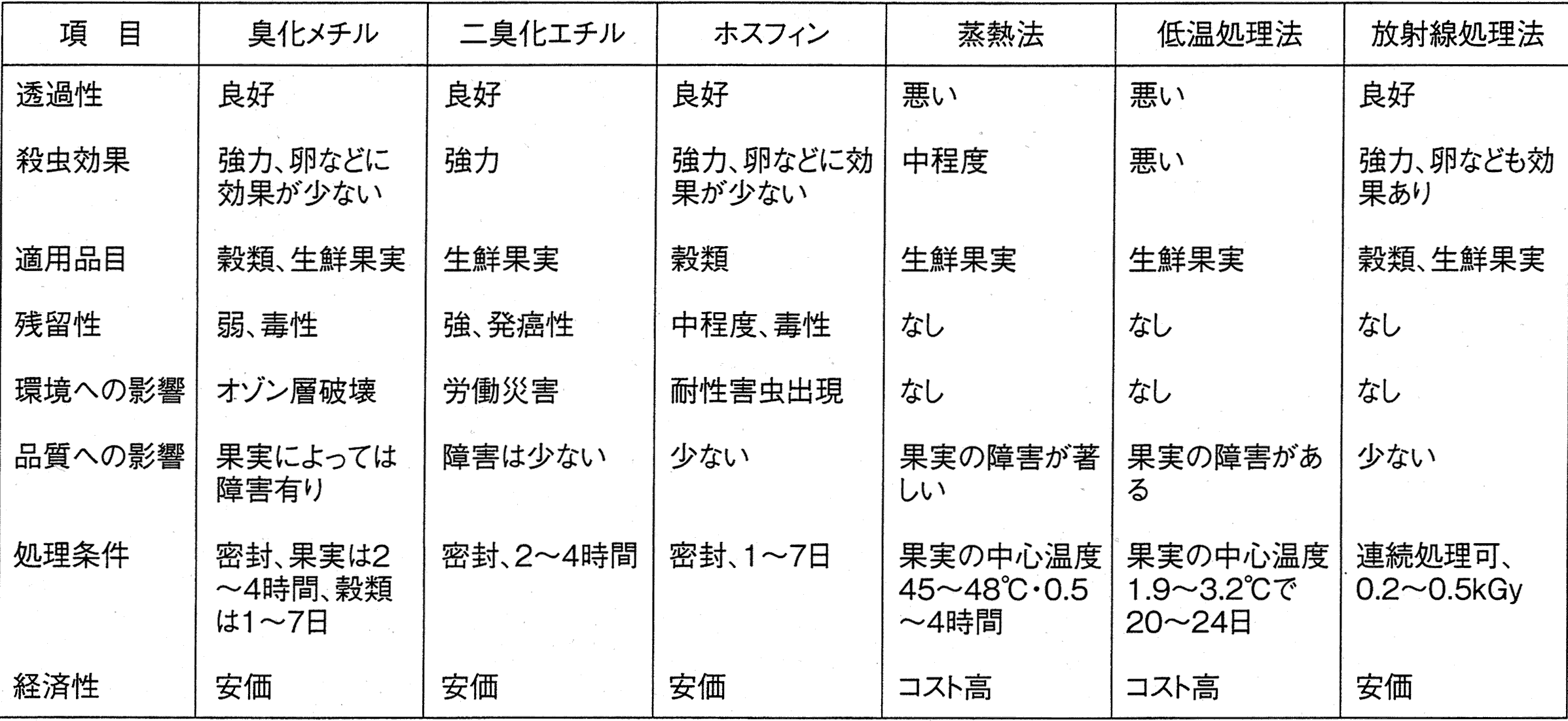 |
私達の身近には食料品が満ちあふれており、飽食の状態が続いている。そのような状況下では食品照射の必要性は感じられず、「何も食品に放射線を照射しなくとも良いのでは?」という意見もあるようである。しかし、わが国の食料自給率はカロリーベースで約40%と先進国の中で著しく低く、大量の食料を輸入に依存している。海外の国々には当然のことながら、わが国に分布していない害虫や寄生虫、人畜の病原菌、植物病原菌などが生息しており、輸入食料などを通じてわが国に侵入してくる可能性がある。しかし、検疫処理に使われていた臭化メチルなどの薬剤の多くは人体への毒性やオゾン層破壊原因物質として使用できなくなっている。また、腸管出血性大腸菌O157などのように国内に広く生息してしまったものもある。一方、わが国は高齢化社会に入りつつあり、食中毒の危険性が増加している。そして、食品の安全性や生活習慣病対策として減塩食品や保存料などを用いない食品の供給が求められている。
これらの課題に対し、放射線による殺虫・殺菌などの処理は検疫処理や衛生化処理、減塩食品での有害菌の生育抑制、有害な保存料や薬剤の大幅な低減などに有効な技術である。そして、海外では食品照射の実用化が進展しており、わが国でも食品照射の実用化を進めるべき時期にきている。なお、照射食品の安全性については参考文献1)に述べているように全く問題がなく、世界保健機関も実用化を勧告している。
以下、各種食品の処理法の現状、放射線処理の方法とその効果について述べる。
穀類や輸入生鮮果実などの殺虫処理は長い期間にわたって臭化メチルでの燻蒸で行われてきた。臭化メチルは穀類や果実内等への浸透性に優れ、殺虫効果も強力である。わが国は米国に次ぎ世界で2番目に多く臭化メチルを使用してきた(国内の68%は土壌燻蒸)。しかし、1992年のモンテリオール議定書によって臭化メチルはフロンガスと同様にオゾン層破壊物質であるとされ2)、先進国は2005年に使用を原則禁止することが合意された。フロンガスや臭化メチルなどはオゾン層破壊ばかりでなく温室ガス効果も炭酸ガスに比べて極めて高いことが知られている3)。このため、輸入穀類は検疫処理せずに国内に入り、一部はホスフィン(リン化水素)で燻蒸されているが薬剤耐性虫が発生しやすい。米などの穀類は15℃以下の低温で貯蔵されているが、輸入穀類などには外来穀類害虫のヒメカツオブシムシやスジマダメイガなどが繁殖する可能性がある。ことに、ヒメカツオブシムシは低温でも増殖し燻蒸処理にも耐性が強い。しかも、輸入穀類や香辛料などには日本に分布していないアフラトキシンなどの発癌性カビ毒を産生するカビ類で汚染している可能性がある。これらのカビ類は乾燥状態での水分含量13%程度では生育しないが、害虫の増殖により穀類等の水分含量や温度が上昇して水分含量が16%以上になると生育しやすくなりカビ毒を産生する可能性がある。カビ毒にはアフラトキシン、オクラトキシン、ステリグマトシスチンなどがあり、熱帯地方に分布するアスペルギルス・フラバスが産生するアフラトキシンは地球上で最強とも言われる経口発癌性物質である。
飼料原料となるトウモロコシやコウリャンなどの穀類の年間輸入量は1,500万トン以上あり、様々な昆虫のサナギや卵、雑草種子などが混入した状態で輸入されている。輸入後の飼料原料は低温貯蔵されずホスフィンで燻蒸されているが害虫の一部は生き残って増殖し、カビ毒で汚染された飼料原料も家畜に与えられるため、畜産製品を通じてカビ毒が食卓に微量ながらも提供される可能性がある。生き残った外来昆虫の中には国内に住み着くものもあり、農林業や地域の生態系に被害を与える可能性がある。また、外来雑草種子も農業に被害を与えている。なお、臭化メチルやホスフィンなどの殺虫剤は害虫の卵やサナギには効果が不十分なため、時々燻蒸を繰り返す必要がある(表ー1)。一方、輸入生鮮果実は臭化メチルや二臭化エチル燻蒸の代わりに蒸熱処理法で殺虫されている。これは、ミバエなどの農業害虫が国内に侵入するのを防止するためであるが、生鮮果実は45〜48℃、0.5〜4時間加熱されることにより変質し味も低下する。
放射線処理は通常0.2〜0.5 kGyで行い、環境に悪影響を与えることなく穀類の病害虫の発生を抑制でき、米や小麦、大豆などは食味や栄養成分も低下しない1,4)。また、害虫が殺滅されているため、カビ毒産生菌が増殖する可能性も減少するであろう5)。一方、飼料原料穀類の場合には雑草種子の不活性化も必要なため、1 kGy前後での処理が必要であろう6)。なお、この線量でも栄養成分や嗜好性の低下は無視することができる1)。輸入生鮮果実などの殺虫線量は0.1〜0.5 kGyであり、果実の鮮度が保たれ食味や栄養成分も変化しないため米国などで実用化されている。
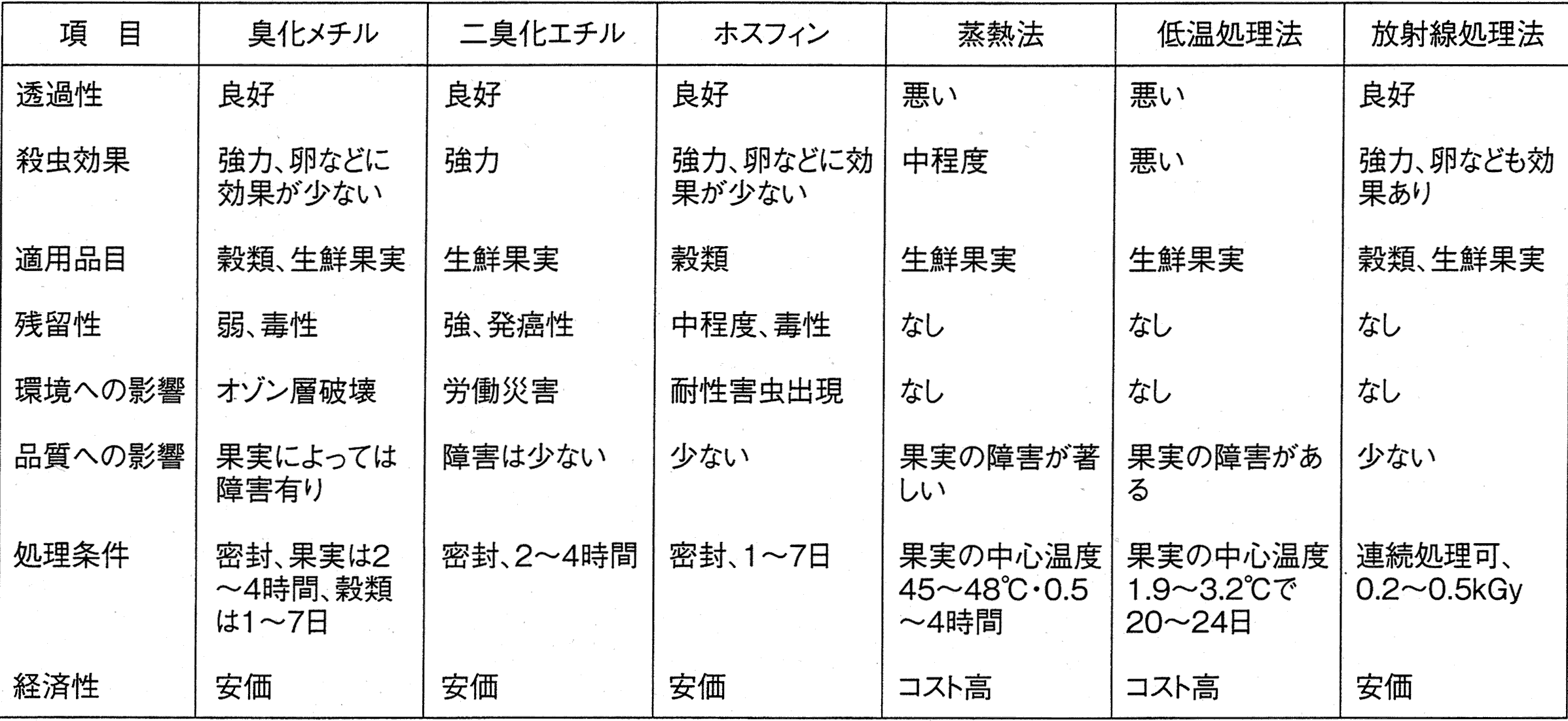 |
馬鈴薯やタマネギ、ニンニクなどの根茎野菜は長期間貯蔵すると発芽や発根、貯蔵中の腐敗により食用に向かなくなってしまう。また、馬鈴薯のように発芽時にソラニンなどの毒素を産成するものもある。根茎野菜の発芽防止にはマレイン酸ヒドラジドやクロロプロファムが欧米諸国で広く使用されてきている。しかし、わが国の食品衛生法では毒性の問題から使用が禁止されている。一方、農林水産省は2000年前後までは根茎野菜の収穫前のマレイン酸ヒドラジドの散布を認めてきた。すなわち、マレイン酸ヒドラジドを散布すると収穫後の根茎野菜の発芽が抑制されるため、広く用いられてきた。しかし、2003年にマレイン酸ヒドラジドから生成するヒドラジドに発癌性があることがわかり、1 ppm以上は有害と国際的に規制されたため収穫前の散布が禁止となった7)。
このため、ニンニクの発芽防止法として−2.5℃で貯蔵する方法が採用されたが、常温にもどすと腐敗や発芽が起こるため、流通は低温下で行う必要が生じた。一方、馬鈴薯は寄生菌の問題で生鮮品の輸入が禁止されている。しかし、ポテトチップなどの加工品は輸入可能であり、クロロプロファムで発芽防止された馬鈴薯で製造された輸入ポテトチップなどが流通している。クロロプロファムも毒性が強く、欧米諸国はポテトチップなどの残留基準を10 ppm以下としている。国産のポテトチップなどもクロロプロファムの使用が黙認されており、青果市場で流通する馬鈴薯のみが使用禁止されている。
放射線による根茎野菜の発芽防止(0.02〜0.15 kGy)は馬鈴薯、サツマイモ、タマネギ、ニンニクなどに適用でき、常温でも長期にわたって貯蔵・流通でき、貯蔵中の腐敗も少ない安全で優れた処理法である。また、エネルギー消費、二酸化炭素発生の削減にも寄与できる。すなわち、ニンニクやタマネギも休眠期間中に放射線処理することにより発芽防止され、常温での流通が可能となり、農家の安定経営にも役立つ技術である4)。
2009年の夏には牛肉のカット肉(角切りステーキ)で腸管出血性大腸菌O157による食中毒が多発した。牛肉によるこの種の食中毒はカット肉ばかりでなく、牛肉のタタキや挽肉でも多発している。このことは、わが国の牛肉にも腸管出血性大腸菌(O157以外にも病原性大腸菌の分類に用いる血清型に同じ病原性を示す多くの型がある)が広く汚染していることを示している。筆者らの1998年の報告8)でも国産牛肉1 g当たり1,900個の大腸菌O157で汚染していると推定される例が示され(表ー2)、鶏肉からもO157が若干分離されている。牛肉のカット肉やタタキ、挽肉で食中毒が多いのはO157等が牛肉内部でも増殖するためであり、筆者らが分離したO157は10℃でも活発に増殖する能力があった8)(一般の大腸菌は10℃では生育が遅い)。腸管出血性大腸菌による集団食中毒は1996年に大発生したが、その後も日本各地で発生しており、老人施設での発生件数が多い傾向がある。この菌は病原性が高く、幼児や老人では10個以下でも発症する可能性がある。一方、肉類にはサルモネラや黄色ブドウ球菌、カンピロバクター、リステリア菌なども汚染しており、筆者らが調べた結果でも鶏肉の約20%からサルモネラ、約50%からリステリア菌が検出されている4)。これらの肉類を十分に加熱せずに調理すれば食中毒になる可能性がある。
魚介類の場合も夏場の海水温度下では腸炎ビブリオ菌や人喰いビブリオ菌のビブリオ・ブルニフィカス、コレラ菌近縁のビブリオ・ミミカスなどが海水中で増殖し、魚介類に汚染する可能性がある。一方、低温の海水ではエロモナス菌が増殖して魚介類に汚染する。これらの菌は輸送・貯蔵中に増殖して食中毒の原因になる。表ー3は輸入した冷凍エビに汚染していた病原ビブリオ菌の分布を筆者らが調べた結果であるが4)、同じような結果は日本の海水等でも報告されている9)。魚介類の多くは刺身または加熱調理して食べられているが、夏場には食中毒が多発している。そして刺身や貝類などからの食中毒が約65%、加熱調理品が約30%という報告もある10)。食中毒の多くは腸炎ビブリオ菌やビブリオ・フルビアリスによるものであるが、肝臓が悪い人では人喰いビブリオ菌によって死亡する場合もある。エロモナス菌は北洋産の魚介類で汚染しており、5℃の貯蔵温度でも増殖し食中毒の原因になることがある。
肉製品のハムやソーセージ、魚肉製品のカマボコなどの水産練り製品は保存料のソルビン酸塩や亜硝酸塩などが添加され健康への影響が懸念されている。ソルビン酸塩には多種類の細菌の生育を抑制する作用があるが、毒性はほとんど無いとされている。しかし、保存料添加食品を食べ過ぎると腸内細菌群に悪影響を与え下痢などの原因になる可能性がある。一方、ハムなどに添加されている亜硝酸塩は肉の赤色発色やボツリヌス菌抑制の目的で添加されている。ハムなどには肉製品1 kg当たり100〜160 mgの亜硝酸塩が添加されるが、アミン類と反応して発癌性のニトロソアミンを生成することが知られている11)。一方、発色を目的とする場合1 kg当たり25 mg以下で十分である。しかし、保存料無添加品の場合には食中毒性細菌が繁殖しやすくなる可能性がある。なお、肉製品や水産練り製品は製造時に70〜80℃で加熱するがほとんどの菌類は生き残り低温貯蔵中でも増殖する12)。
放射線による殺菌は食中毒の危険性を低減し、保存料添加の必要がなく、有害な生成物がない優れた技術である。多くの食中毒性細菌(薬剤耐性菌を含む)は非凍結下では1〜3 kGyで殺菌でき、ボツリヌス菌やセレウス菌などの耐熱性の有芽胞細菌も10℃以下の低温貯蔵と組み合わせれば3 kGy以下で食中毒の危険性を著しく低減することが可能である1,4)。ことに、腸管出血性大腸菌や腸炎ビブリオ菌、人喰いビブリオ菌、エロモナス菌、カンピロバクターなど多くの食中毒性細菌は非凍結下では1 kGyでも十分に殺菌効果があり、低温貯蔵と組み合わせれば食中毒の低減が可能となる。すなわち、魚介類の多くと牛肉製品は1 kGyでも殺菌効果が期待でき、鶏肉などは2〜3 kGy必要であろう。ハムなどの肉製品や水産練り製品は3 kGy程度で貯蔵期間を延長でき、健康への影響もない。しかし、貯蔵中の酸化劣化や照射による食味変化を防止するために、窒素ガス置換または真空包装した状態での照射が望ましい4)。なお、凍結した肉や魚介類も食中毒性細菌は生き残っており、解凍時に急速に増殖するため殺菌しておく必要がある。凍結した肉や魚介類の放射線殺菌線量は非凍結に比べ約2倍必要であり、2〜7 kGyである。この理由は、凍結下ではフリーラジカルの拡散が抑制されるので殺菌効率が低下するためであり、栄養成分の低下はほとんどない。
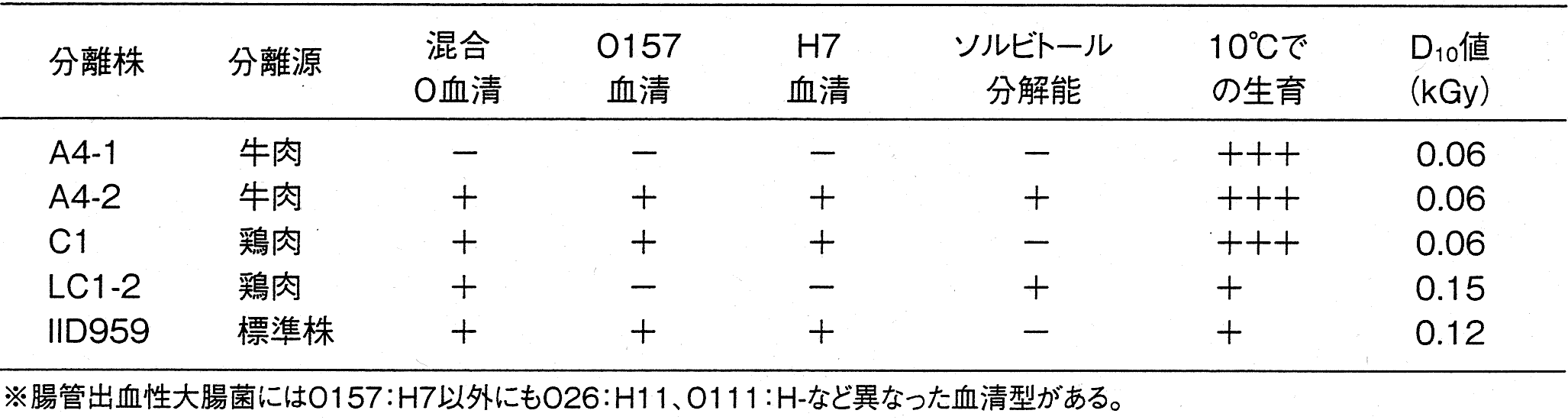 |
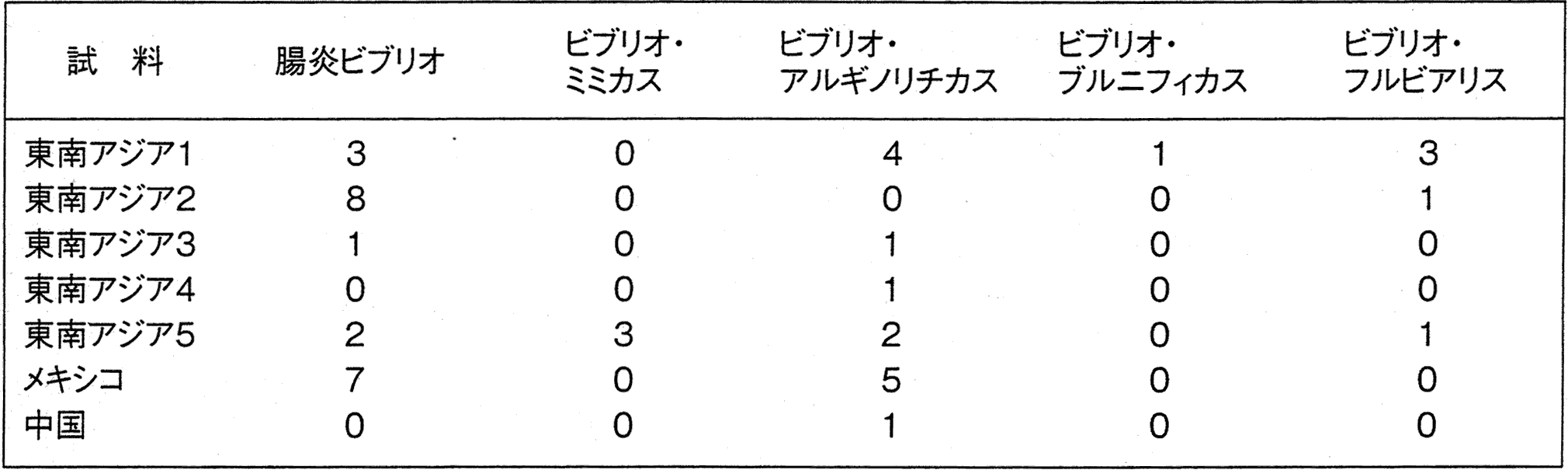 |
香辛料の多くは東南アジア等の熱帯地域で生産されており、耐熱性の有芽胞細菌やカビ毒を産生するカビ類で汚染されているものが多い13)。有芽胞細菌には枯草菌などが多いが、セレウス菌やボツリヌス菌などの食中毒性細菌も汚染している。そして、香辛料の多くは1 g当たり1万〜1億個の微生物で汚染しており(表ー4)、ハムや水産練り製品などに添加されると菌が増殖して食中毒の原因になることがある。香辛料や乾燥野菜調味料などの殺菌は1990年以前にはエチレンオキシドで処理されることもあった。しかし、エチレンオキシドは発癌性のエチレンクロロヒドリンを生成するため食品衛生法では使用が禁止されていた。これに代わる殺菌処理法として日本で開発された技術が気流式過熱水蒸気法であり、180℃で2〜7秒処理して殺菌される。食品衛生法では肉製品や水産練り製品などに添加される香辛料等は1 g当たり千個以下の微生物数まで殺菌することが義務づけられている。これは、セレウス菌やボツリヌス菌など耐熱性の有芽胞細菌による食中毒を防ぐのが目的である。事実、セレウス菌の著しい増殖が10℃で保存した保存料無添加ウインナソーセージで認められている12)。わが国では食品加工に用いる香辛料等は気流式過熱水蒸気法によって殺菌されている。しかし、過熱水蒸気による殺菌処理では微粉末化した香辛料の香気成分が消失し色調も変化するため、粗挽きの状態で殺菌処理している。この粗挽きの状態でも香気成分の10〜30%14)またはそれ以上が失われ退色も起こる。また、香辛料の加工処理工程も複雑となるため加工コストも高くつくという問題点もある。
一方、家畜飼料には家畜の病気を防ぐために抗生物質が多用されることがある。魚粉や骨粉、肉粉、食料廃棄物などの高タンパク質飼料原料にはサルモネラなどの病原性細菌で汚染していることが多く1)、家畜の病気の原因となることがある。ことに、幼動物の場合には飼料由来の病気は深刻である。この対策として、飼料に抗生物質を添加して家畜の病気を防いでいる。しかし、バンコマイシンと化学構造が似た抗生物質などの使用によって抗生物質耐性菌が生じ、病院での患者の治療が困難となっている。高タンパク質飼料原料も殺菌処理すれば抗生物質の使用を大幅に低減できるし、耐性菌の発生も減少できると思われる。しかし、蒸気殺菌は栄養成分が低減するし、処理コストが高くつき現実的ではない。
放射線による香辛料の殺菌線量は7〜10 kGyであり、香気成分や色調も変化しないし、抗菌性や抗酸化性も変化しない1, 14)。香辛料の放射線殺菌は約60ヶ国で許可となっており、国際間貿易でも流通している。高タンパク質飼料原料中のサルモネラ等の病原菌は約5 kGyで殺菌でき1)、栄養成分の低減もない15)。無菌の実験動物用飼料については、わが国でも30〜50 kGyで滅菌されたものが40年以上にわたって実用化となっており、安全性も十分に証明されている15)。
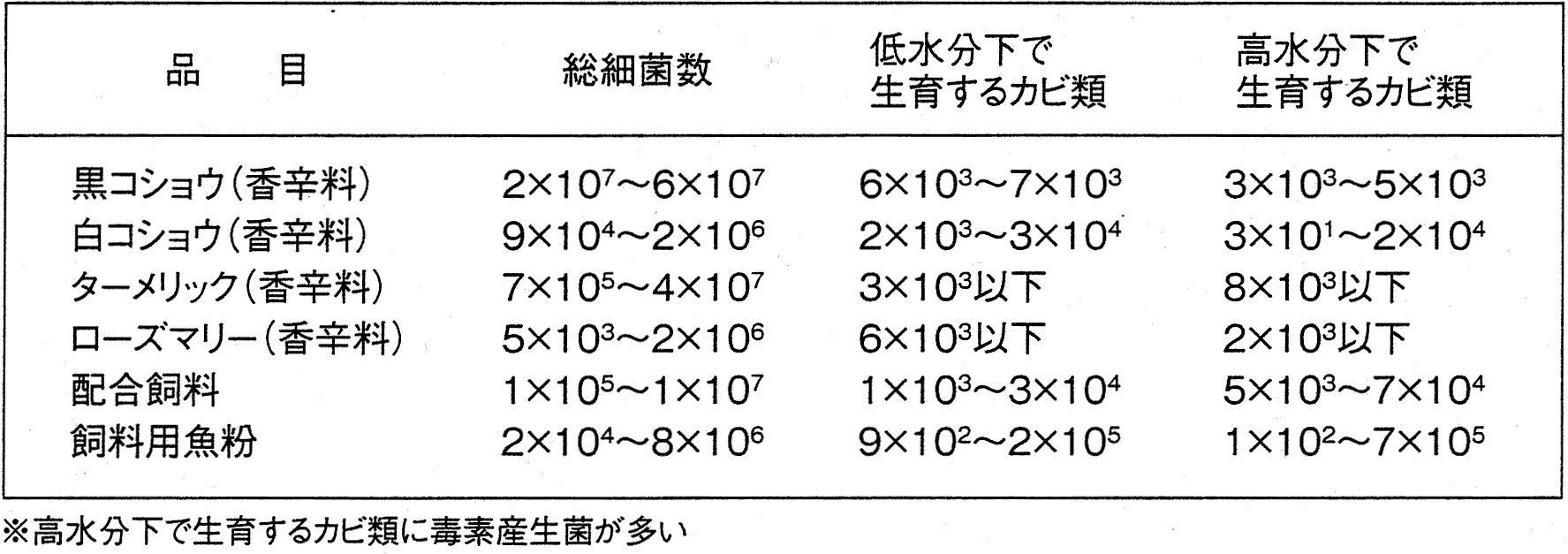 |
違法照射された輸入食品が摘発される事件が時々起こっている。その一部は香辛料であるが、多くはアガリクスとかホッキ貝、乾燥シイタケなど照射の目的がはっきりしないものが多い16)。乾燥シイタケなどは船での輸送中にカビが発生するのを防止するのが目的と思われる。輸入食品は検疫問題や病原菌汚染ばかりでなく、輸送時の腐敗や虫害などの問題もある。例えば、ポリエチレン包装した乾燥食品でも海上での湿気や酸素ガスが十分透過するためカビや虫の繁殖が可能である。
私達の周囲には食品に汚染している病原菌の問題や薬剤耐性菌、検疫時の農業害虫の侵入、高齢化人口の増大による食中毒リスクの増加など様々な問題が存在している。食品照射はこれらの問題解決に貢献できる技術であり、我が国の食生活の維持・向上のためには必要・不可欠なものと考えられる。海外でも日本と同様に衛生管理や検疫などで様々な問題を抱えており、米国などでの食中毒の被害は日本の10〜100倍であると報告されている17)。日本の食料事情は世界の動向とも密接に関係している。すなわち、わが国を取り巻く米国や中国、台湾、韓国、東南アジア諸国などで食品照射の実用化が進展しており、科学的に安全性が実証されている食品照射はグローバルな手法となってきており、国際的な資源流通の観点からも日本も前向きな対処が必要な事項と思われる。
さしせまって食品照射の実用化が必要な品目は香辛料やニンニク、検疫時の輸入果実、高タンパク質飼料原料などであり、牛肉や鶏肉の放射線処理も早急に検討するべき課題であろう。
1) 林 徹編著、“食品・農業分野の放射線利用”(幸書房、2008).
2) UNEP, “Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer”, 1994 Report of the Methyl Bromide Technical Options Committee, 1995 Assessment.
3) 国連環境計画事務局長 アヒム・シュタイナー、朝日新聞、2009年9月24日夕刊、11面.
4) 伊藤 均、“なぜ食品照射か−その歴史と有用性[3]食品の照射効果と衛生化”、放射線と産業、No.112, 36 (2006).
5) 伊藤 均他、“殺虫線量照射による玄米の発芽率変化と糸状菌発生の抑制”、日本食品工業学会誌、29、423 (1982).
6) 高谷保行、伊藤 均、“外来雑草種子の繁殖防止を目的とした放射線照射効果”、食品照射、34、23 (1999).
7) 農林水産省告示第784号(ロッテルダムPIC条約)、2003年.
8) 伊藤 均、Harsojo、“食肉中の大腸菌O157:H7の放射線殺菌効果”、食品照射、33、23−32(1998)。
9) K. Venkateswaran,et al., “Characterization of toxigenic Vibrios isolated from the fresh water environment of Hiroshima, Japan”, Appl. Environ. Microbiol., 55, 2613 (1989).
10) 業界ルポ企業、“「腸炎ビブリオ菌食中毒防止」に真剣に取り組みを見せる水産業界”、食品工業、8.15、25 (2000).
11) ダイジスト オブ ハイライト、“加工肉の亜硝酸塩によるキュア処理の抑制”、食品工業、11下、75 (1983).
12) H. Ito , T. Sato , “Changes in the microflora of vienna sausages after irradiation with gamma-rays and storage at 10℃”, Agric. Biol. Chem., 37, 233 (1973).
13) M. L. Juri, H. Ito, et al., “Distribution of microorganisms in spices and their decontamination by gamma-irradiation”, Agric. Biol. Chem., 50, 347 (1986).
14) 金子信忠、伊藤 均他、“香辛料の精油成分及び脂質に対するγ線照射の影響”、日本食品工業学会誌、38、1025 (1991).
15) Joint FAO/IAEA Division of Atomic Energy in Food and Agriculture, “Decontamination of Animal Feeds by Irradiation”, STI/PUB/508, IAEA, Vienna, 1979.
16) 伊藤 均、“食品照射を巡る最近の状況”、放射線と産業、No.121、38(2009).
17) 吉田隆夫、“アメリカにおける食品安全とHACCP”、食品工業、7.30、81 (1997).
|
|