Fig.1 Exponential survival curves of irradiated IBR virus in IBR antibody free serum at room temperature.
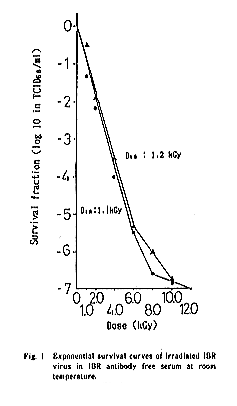 |
放射線利用は近年、医療器具の滅菌、実験動物用飼料の殺菌及び食品への応用等広がっているものの、食品分野における使用は日本では、馬鈴薯の発芽防止に限り認められている。
動物検疫所では、種々の畜産物の検疫を実施しており、輸入畜産物の消毒は現在、ホルマリンガス、EOガス、次亜塩素酸ソーダ、硫化ソーダ及び水酸化ナトリウム等により実施している。しかし、近年輸送の高速化と輸出地域の拡大に伴い輸入畜産物も多岐に亘り、新しい消毒方法の開発が求められている。
わが国では食品への放射線利用がごく一部に限定されているが、海外においては野菜、果実、魚介類、肉類、穀物及び香辛料等品目と線量は限定されているもののγ線照射が許可されている報告〔1〕〔2〕がある。このような現状から諸外国の放射線利用の広がりに関心をはらうとともに、今後放射線で処理された畜産物が、わが国へ本格的に輸入される可能性も考慮していかなければならない。
放射線の殺菌効果については、これまでに細菌及び糸状菌に関する研究成果が数多く報告されているところから、ウイルスに対する不活化条件を検討する目的で牛伝染性鼻気管炎(IBR)ウイルスを用いてγ線照射を実施した。
動物検疫所で分離、同定したIBRウイルスBK−4株をIBR抗体フリー血清及び市販調製培地中に浮遊させ2ml/tubeずつ分注し、それぞれ室温及びドライアイス凍結でγ線照射試験に供した。
γ線照射前のウイルス力価は、室温照射で7.30〜7.80log10/ml、ドライアイス凍結で6.47〜7.131log10/mlであった。
なお、市販調製培地の特徴はグルコース含量が通常の牛血清に比べ3倍程度多い組成であった。
細胞培養に使用している非働化プール牛血清を2ml/tubeに分注し試験に供した。
照射線量はウイルス不活化試験に用いた線量と同一線量を照射し、セルロース・アセテート(CA膜に0.8μl/0.8cmで45分間通電し、蛋白分画の変化を調べた。
電気泳動像は、ボンソー3Rで染色後デカリンで処理しコンピューティングデンシトメーターで測定した。
γ線照射は日本原子力研究所高崎研究所で実施し室温照射では、照射当日ウイルス液を調整し室温約20℃で照射した。ドライアイス凍結照射では、ウイルス浮遊液を調整し−80℃で凍結、照射当日は凍結したままドライアイスに入れ輸送した。また、照射中もドライアイス下に置いた。試験は室温照射及びドライアイス凍結照射をそれぞれ2回ずつ実施した。線源はコバルト60を用いて、160kCi,6kGy/hr又は10kGy/hrの位置で照射を行なった。なお、各照射位置及びデュワー瓶中の吸収線量は、Frickeの鉄線量計で測定した。 室温照射では、0,1,2,4,6,8,10,12kGyの8段階で実施した。
ドライアイス凍結では、デュワー瓶中0,1.6,2.4,4.7,7.0,9.4,11.7,14.0,16.3,18.6,21.0,23.3kGyの12段階とさらに25.6,30.3kGyを加えた14段階の2方法で実施した。
γ線照射後のウイルス力価を測定し、ウイルス不活化の効果を調べた。ウイルスの測定は、96穴マイクロプレートに培養したMDBK細胞を用い細胞変性効果(CPE)を観察し、Behrens−Karber法によりTCID50を算出した。
細胞はIBR抗体フリー血清を用いた培養液に浮遊させ0.1ml/穴分注し、37℃5%CO2下で2〜3日間培養しシートを形成させて準備した。照射後のウイルス液は原液より10倍階段希釈し、それぞれ0.05ml/穴接種後、維持培養液0.1ml/穴を分注し37℃5%CO2下で培養してCPEを観察した。
室温照射での不活化試験では、IBR抗体フリー血清中のウイルス(7.63log10/mlと7.80log10/ml)及び市販調製培地中のウイルス(7.30log10/mlと7.47log/10ml)は8kGy照射ではいずれも完全に不活化が出来なかった。しかし、10kGy照射ではIBR抗体フリー血清中のウイルスを除いて完全に不活化された。
10kGyで不活化出来なかったウイルスも12kGy照射で完全に不活化された。
室温照射でのIBR抗体フリー血清中のウイルスのD10値は、1.1〜1.2kGyであった(Fig.1)。また、市販調製培地中のウイルスのそれは、1.3〜1.4kGyであった(Fig.2)。
ドライアイス凍結での不活化試験では、IBR抗体フリー血清中のウイルス(7.13log10/mlと6.47log10/ml)及び市販調製培地中のウイルス(6.97log10/mlと6.80log10/ml)のうち、IBR抗体フリー血清中のウイルスで照射前の力価が6.47log10/mlのものと市販調製培地中のウイルスで照射前の力価が6.8log10/mlのウイルスは、23.3kGyで完全に不活化されたが、これよりも照射前の力価が高いウイルスは完全には不活化されなかった。
ドライアイス凍結でのIBR抗体フリー血清中のウイルスのD10値は、3.4〜3.6kGyであった(Fig.3)。また、市販調製培地中では、3.9kGyとなった(Fig.4)。
室温及びドライアイス凍結におけるIBRウイルス不活化試験でのD10値を比較するとIBR抗体フリー血清及び市販調製培地ともドライアイス凍結照射では室温照射の約3倍であった。
γ線照射による血清蛋白の変化は、CA膜を用いた電気泳動で、アルブミン分画、ならびにグロブリンのα分画、β分画及びγ分画の4峰が0,1,2kGyに認められたが、4kGy照射ではα分画及びγ分画の峰は明確には認められなくなり、6kGy照射ではαとβ分画は1峰となりγ分画もβ分画の一部となった。8kGy以上の照射では、グロブリンの3分画は1峰となりアルブミン分画との計2峰を認めた(Fig.5)。
ドライアイス凍結での電気泳動像は、非照射ではアルブミン分画、α分画、β分画及びγ分画の4峰を示し、30kGy照射でもアルブミン分画、α分画、β分画及びγ分画の4峰を認め、非照射と30kGy照射後の牛血清分画像に著しい変化は認められなかった(Fig.6)。
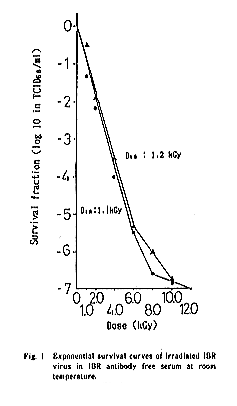 |
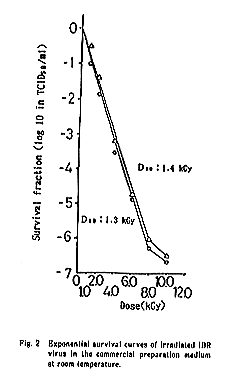 |
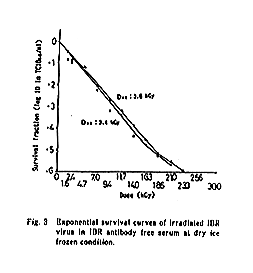 |
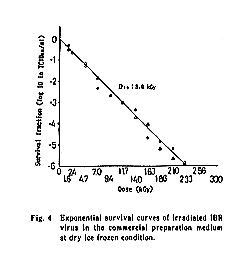 |
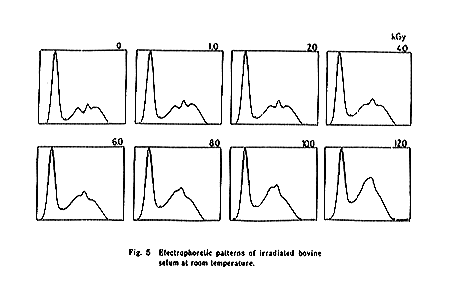 |
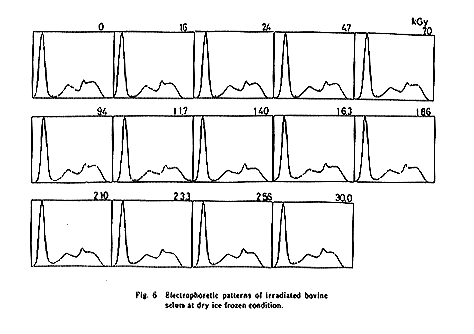 |
γ線による殺菌効果は、水分が多量に存在する系では主に水に直接作用することによって生成するラジカルの間接作用によって起こる。水が電離することによりヒドロキシラジカル(.OH)などの水分解ラジカルが生体内DNA鎖切断を引き起こし、これが殺菌作用の原因と考えられている。しかし、水分がほとんどない乾燥状態やラジカル移動が妨げられる凍結状態では、γ線の直接効果が大きくなる〔3〕。また凍結状態ではラジカルの移動が妨げられるため照射による成分変化が著しく抑制されると報告〔4〕されている。
今回実施したIBRウイルス不活化試験では、室温照射で血清中及び市販調製培地中のウイルス(7.30〜7.80log10/ml:TCID50)は、12kGy照射により完全に不活化された。
一方、ドライアイス凍結での不活化試験では、溶液中よりも低い力価のウイルス(6.47〜7.13log10/ml:TCID50)であったが、このうち力価の高い検体は23.3kGy照射後も完全に不活化はされなかった。
IBRウイルスのD10値は室温照射の場合、IBR抗体フリー血清及び市販調製培地で、それぞれ1.1〜1.2及び1.3〜1.4kGyであった。ドライアイス凍結では、それぞれ3.4〜3.6及び3.9kGyであった。
ドライアイス凍結ではγ線の直接作用が中心でラジカルによる間接作用は少ないためD10値が高くなったと考える。
Johnson〔5〕はペプトン、グルタチオン、チオウレアが緩衝液中及び過酸化水素中でウイルス不活化を一定の割合で弱める作用があり、また過剰な蛋白質は、x線によ不活化に対し保護的な作用をすると報告している。室温照射とドライアイス凍結照射の一部にそれぞれ10及び23.3kGyで原液にのみわずかにCPEが認められるのは、おそらく血清中の蛋白質及び市販調製培地中のグルコースがγ線の不活化を阻止するように働き、ウイルスの不活化に対して保護的に作用するのではないかと考えられる。
Baldelli〔6〕はEarle液に、0.5%の割にラクトアルブミンを加えた溶液中で口蹄疫ウイルス(FMDV)O.A.Cタイプのγ線不活化試験を実施したところ、ウイルスを浮遊した溶液中では、6.6log10/ml:DCP60(50%Cytopathogenic Doses)程度のウイルスは30kGyで、また凍結乾燥状態では40kGyで完全に不活化出来、タイプ間にはγ線に対する感受性の差は認められなかったと報告している。
また、γ線によるウイルスの不活化に関してウイルスの大きさと線量は負の相関関係にあると報告〔6〕されている。
今回供試したIBRウイルスはDNAウイルスで分子量は54×10・E(6)、径は150〜200mμであり、FMDVはRNAウイルスで分子量は9.2×10・E(6)、径は22〜28mμと報告〔7〕されている。IBRウイルスはFMDVよりウイルス粒子の径が大きいためFMDVの不活化線量よりも低い線量で溶液中のIBRウイルスを不活化出来たと考える。水分解ラジカルの作用がなくなる乾燥状態でウイルスを不活化するためには、溶液中よりも高い線量が必要との報告〔6〕は、今回のドライアイス凍結での照射が溶液中よりも高い線量が必要である成績と一致している。
電気泳動による血清蛋白の分画像を調べたところ室温照射でグロブリンの分画像に変化が認められ8kGy以上の照射では、グロブリンの各分画が不明瞭となりアルブミン分画との計2峰の分画像となった。
ドライアイス凍結では、30kGy照射後でもアルブミン分画、α、β及びγグロブリン分画の4峰を認め、分画像に著しい変化は認められなかった。
γ線照射による牛血清分画像を指標として成分変性の程度をみたところ、液体では水分解ラジカルにより6kGy照射以上で成分の著しい変性を認めたが、ドライアイス凍結状態では30kGy照射後も著しい成分変性を認めなかったことは、凍結下では水分解ラジカルの作用が少ないことを裏づける結果となった。
γ線照射により培養液中のウイルスを不活化する場合、培養液中の血清の有無が影響することも考え市販調製培地とIBR抗体フリー血清中にウイルスを浮遊させ比較したところ、市販調製培地の方が僅かであるが高い線量を必要とした。このことは、市販調製培地の高濃度のグルコースがラジカルに対する保護作用を示したためと思われる。
また、ウイルスの凍結状態での不活化に及ぼす影響を検討したところ、血清中のウイルスの不活化には常温よりも凍結下での照射の方が高い線量を必要とした。このように、凍結状態の方が高い線量を必要とするが血清成分の変性は少なく、実際の血清中のIBRウイルスの不活化には、凍結下、20〜25kGyの照射が必要であると結論づけた。
〔1〕伊藤 均:RADIOISOTOPES,36,290−298,
(1987)
〔2〕松山 晃:Isotope News,10,12−15.
(1987)
〔3〕伊藤 均:ニューフードインダストリー,28,12,17−22
(1986)
〔4〕伊藤 均:防菌防黴,14,223−232(1986)
〔5〕C.D.Johnson:Microbiological
Problems in Food Preservation
by Irradiation.IAEA,65−75(1967)
〔6〕B.Baldelli:Microbiological
Problems in Food Preservation
by Irradiation,IAEA,77−86(1967)
〔7〕保坂康弘ら:ウイルス図鑑、講談社、66−67(1972)
|
|